釣行予定の日が雨上がり──。
「雨の後って魚釣れるのかな?」と不安に思ったことはありませんか?
実は、雨後の状況によって魚の活性が一気に上がることもあれば、まったく反応がなくなることもあるのが釣りの難しいところです。
この記事では、1000回を超える私の実釣経験と釣果データをもとに、雨の後でも釣れる魚・釣れにくくなる魚を魚種別に整理して徹底検証。
さらに、安全面・仕掛け選びの注意点まで詳しく解説しています。
「雨の後に釣りへ行っても大丈夫か?」と悩んでいる方は、ぜひ最後まで読んでみてください。
雨の後、魚は本当に釣れるのか?

結論からいうと、魚種やポイント、水質の変化によって釣果は大きく左右されるというのが現実です。
「雨の後は活性が上がる」と言われることもありますが、それはあくまで条件が揃った場合の話。
特に海釣りでは“水潮”の影響が大きく、状況によってはほとんどの魚が釣れなくなるケースもあります。
一方で、シーバスやチヌ(クロダイ)など一部の魚種はむしろ好機になることも。
まずは「雨によって何が変わるのか?」という点から、魚たちの行動を紐解いていきましょう。
雨の後の海や川の状況はどう変化するのか?
雨が降ったあとの海や川では、水温・濁り・塩分濃度・酸素量などが大きく変化します。
これらの要素は魚の活性や回遊ルートに強く影響するため、釣果にも直結します。
例えば海では雨によって表層が真水に近づき「水潮」状態になることがあり、これが原因で魚が散ってしまうことも。
逆に淡水魚の場合は、増水や濁りによってカバーに隠れていた魚が動き出し、釣りやすくなることもあります。
つまり、「雨の後=釣れない」というわけではなく、状況に応じた見極めと戦略が重要なのです。
釣れる魚と釣れない魚の特徴
雨の後、釣れるか釣れないかは魚の性質や水質への耐性によって大きく変わります。
特に影響するのは、濁りの程度・増水の規模・水潮の範囲です。これらの条件によって、同じ釣り場でも釣れる魚と釣れない魚がはっきり分かれることがあります。
釣れやすい傾向のある魚の特徴:
✔ 濁った水でも行動できる感覚を持っている
✔ 流れや変化を好み、濁りや低水温に強い
✔ 底付近を好み、視覚に頼らない捕食スタイル
釣れにくくなる魚の特徴:
✖ 視覚に強く依存し、濁りを嫌う
✖ 流れの変化や急な水質変化に敏感
✖ 群れで回遊しやすく、水潮を嫌って離れてしまう傾向がある
つまり、雨の後の状況では釣れる・釣れないの差は魚種というよりも水中環境に対する“適応力”に左右されると言えます。
雨の後に魚が釣れやすくなる条件
雨の後でも、ある条件が揃えば魚の活性が一気に上がり、思わぬ爆釣につながることもあります。重要なのは「どんな状況で魚が釣れやすくなるのか」を把握することです。
以下は、実際の釣行データから見えてきた釣果につながりやすい条件です。
- 小雨や短時間の降雨だった場合
水質の急変が起きづらく、魚の警戒心が薄れやすいです。 - 流れや潮の変化が生まれるタイミング
淡水と海水が混じり流れが複雑になると、捕食のチャンスが増えます。 - 適度な濁り
澄みすぎているよりも適度に濁っていた方が、魚の警戒心が薄れヒット率が上がるケースも。 - 雨後の晴れ間
天気が回復しはじめると、急激に魚の活性が上がることがあります。 - ベイト(小魚・エビ類など)の動きが活発
雨によって栄養が流れ込むことで、ベイトが接岸→それを追って魚も寄ってきます。
ちなみに私自身の過去1000回以上の釣行データでも、弱い雨の後はむしろ晴れが続いていた日よりも釣果が良かったというケースが何度もありました。
こうした一見マイナスに見える雨の影響を、プラスに変える条件が整っていれば、むしろ雨後は大チャンスになり得ます。
逆に釣れにくくなる原因(水潮・濁り・酸素低下)
雨の後といっても、すべての状況で釣果が上がるわけではありません。
特に注意が必要なのが「水潮」「過剰な濁り」「酸素濃度の低下」といった要因です。
- 水潮
雨水が表層にたまってしまうことで、塩分濃度が低くなり魚が嫌う「水潮」の状態になります。魚が底へ潜ったり沖へ離れたりして、非常に釣りづらくなります。 - 過度な濁り
濁りが強すぎると、視界を失った魚がルアーやエサを認識できなくなり、警戒心が増すこともあります。 - 酸素濃度の低下
特に海や汽水域では、大雨で表層の淡水が入り込むと酸素濃度が薄くなり、魚の活性が大きく下がる原因になります。
基本的に大雨や長時間の雨の後は荒れやすく、釣果が落ちやすいのが現実です。
ただしその一方で、極端な状況が「釣り場のバランスを崩す」ことによって、想定外の大物が釣れることもあるのです。
例えば、私の実際の雨の後の釣行で起こった出来事では
普段は小さなシーバスしか釣れない河川で、雨後にランカーサイズ(80cm以上)が突然釣れたり、豆アジしか回ってこない漁港でいきなり尺アジが釣れた事もあり
いわゆる「バグった釣果」を経験した事があります。
条件は厳しいけれど、一発逆転のチャンスが眠っている。それが雨後の釣りの醍醐味とも言えます。
魚種別|雨後の釣果傾向まとめ

雨の後の釣果は、魚種によって大きく異なります。中には活性が上がりやすくなる魚もいれば、逆に釣れづらくなる魚も存在します。
ここでは、過去様々な釣りでの1000回以上の私の釣行データをもとに、「雨の後に釣れる魚」「釣れにくい魚」それぞれの傾向を分かりやすくまとめました。
ターゲットにする魚種によって雨後に狙うべきか見送るべきかの判断材料にしてみてください。
雨の後に釣れる魚(シーバス・チヌなど)
雨が降っている最中に釣れやすいことで有名な魚といえば、シーバスやチヌ。
これは雨音や濁りによって人の気配やルアーの存在感が薄れ、魚の警戒心が下がるためです。
実は雨の後もこの傾向は継続しやすく、流れ込みや排水溝周り、濁りが広がったエリアでは特に釣果が伸びやすくなります。
雨によってプランクトンやベイトが流れ込むことで、餌を探している魚が岸近くまで寄ってくるため、シャローでもヒットが期待できます。
私自身の釣行でも、雨の翌朝にランカーシーバスが釣れたケースや、チヌの連発モードに突入したパターンも複数ありました。
晴天続きでは反応がなかったポイントでも、雨後には急に状況が一変することも少なくありません。
雨の後に釣れにくい魚(アジ・青物・イカなど)
雨の後にやや警戒したいのが、アジや青物などの回遊系の魚やアオリイカ等です。
これらの魚は水質の変化や水潮に弱く、雨による濁りや急な塩分濃度の低下で活性が落ちることがあります。
水深のないエリアだと特に影響が大きく、釣果がガクッと落ちてしまうことも。
ベイトが濁りを嫌って移動してしまうと、後を追う形でアジや青物も離れてしまう傾向があります。
とはいえ、極端な大雨や急激な濁りが無い限りは、むしろ活性が上がることの方が多いというのが実際のところ。
私の釣行データでも、雨の翌日にナブラが連発した日や、アジの尺クラスが数釣れた日もありました。
さらに、水深がある漁港などでは、沖からベイトとともに入り込むパターンも見られるため、一概に釣れないとは言えません。
雨後こそ、ポイントの選定と状況判断がより重要になってくるのです。
雨の後の釣りで気をつけたいポイント

雨の後は魚の活性が変化するだけでなく、釣り場の環境自体にも大きな変化が起きます。
安全面のリスクや、釣果を上げるためのコツなども意識しておくことで、雨後の釣行を成功に導くことができます。
ここでは、釣果アップだけでなく、安全に釣りを楽しむための注意点を詳しく解説していきます。
安全面(増水・滑りやすさ)
雨の後の釣行でまず最も重要なのが 安全面 です。
河川や流れ込み周辺では 急な増水 や 流れの変化 が起きており、普段とまったく違う環境になっていることもあります。
特に テトラ帯や磯場 は非常に滑りやすく危険です。
雨の後はコケが湿ってさらに滑りやすくなっており、足を滑らせての転倒や落水事故が起きやすい状況になります。
私自身、そういった釣り場の雨後の釣行では 必ずフェルトスパイクのブーツを着用 するようにしています。
釣果も大事ですが、それ以上に 安全を最優先 して釣行を計画することが大切です。
釣果アップのコツ(時間帯・潮回り・ポイント)
雨の後でも釣果を上げたいなら、タイミングと場所の選び方がカギです。
まず意識したいのは時間帯。朝マズメや夕マズメは、普段以上に魚の活性が上がる傾向にあります。
また、潮回りも重要です。
特に中潮〜大潮の上げ始めは、雨による濁りや水温変化が緩和され、魚が岸寄りに入ってくるタイミングになりやすいです。
ポイント選びでは、濁りの少ない場所や水通しの良い場所を優先すると良い結果につながりやすいです。
例えば、サーフなら払い出しの流れができる場所や、堤防なら外向きの潮通しの良い先端部などがおすすめです。
雨の影響を「プラス」に変えるためには、釣れる条件が整う瞬間を見逃さないことが最も大切です。
雨後でも効果的な仕掛け・ルアー選び
雨の後は濁りや水温の変化が大きく、魚の視界や活性に影響を与えます。そんな中でも安定して釣果を上げるためには、ルアーや仕掛けの選び方が非常に重要です。
例えばルアーの場合、波動の強いバイブレーション系や、シルエットの大きいワームが濁りの中でもアピールしやすく効果的です。
色はチャート・ゴールド・黒系などコントラストの強いカラーを意識すると、視認性が高まり反応を得やすくなります。
仕掛けについては、雨後に多くなるゴミや漂流物を避けるために、シンプルな構成が基本です。サビキ釣りなら仕掛けを短くし、エサの出方を調整することで喰わせやすくなります。
また、ジグ単や軽めのジグヘッドでスローに見せる展開は、水潮などで活性が低い魚に有効です。雨後こそ、仕掛けとルアーの最適化が釣果を分けると言えるでしょう。
雨後の釣りに関するよくある質問Q&A

雨の後の釣りに関しては、よく聞かれる疑問がいくつかあります。
ここでは、釣行前に知っておくと安心できるポイントをQ&A形式で解説していきます。
雨の翌日は釣れる?釣れない?
結論から言えば、小雨の後であれば釣れる確率はむしろ高まることが多いです。
実際に私の1000回以上の釣行データ1000回以上でも、前日が小雨や弱い雨だった翌日は高確率で釣果が出ていました。
一方で、豪雨の後は水潮や濁りの影響で活性が落ちるケースも多く、タイミングや場所によっては釣りづらくなります。
特に、水深が浅く流れの影響を受けやすい場所は、雨後に一気に環境が変わるため注意が必要です。
但し、普段釣れないランカーシーバスや尺アジが上がった経験もある為、”バグった釣果“を得られる可能性もあります。
つまり、雨の強さやその後の天候、水質の変化によって釣果が大きく左右されるということです。
水潮の見分け方とは?
水潮とは、雨水や河川水が海水の上に覆いかぶさるように溜まってしまい、表層の塩分濃度が極端に下がっている状態です。
この状態では多くの魚が嫌って移動してしまうため、釣果がガクッと落ちる原因になります。
実際に水潮かどうかを判断する方法はいくつかあります:
- 表層だけが濁っている(下の潮はクリア)
- 雨の後に急にアタリが無くなった(魚が散ってしまう)
- 極端に泡が残る(雨水の成分で水が乳白色っぽくなる)
- 臭いが強い(生活排水や泥の匂いが混じることも)
このような状況が当てはまる場合は水潮の可能性が高く、表層よりも深場を狙うなど対策が必要です。
釣り初心者が雨後に注意すべきことは?
雨の後の釣りは、魚の活性が高まるタイミングでもありますが、初心者にとっては危険や注意点も多いのが現実です。
- 足場の滑りやすさ:濡れたテトラや岩場は非常に滑りやすく、転倒事故も少なくありません。
- 増水・流れの変化:河川や堤防では、急な増水で水位が上がったり、流れが速くなることがあります。
- 水潮の影響:初心者はアタリがない=釣れないと判断しがちですが、上層が水潮になっている場合はレンジ(タナ)を変えるなどの工夫が必要です。
- 安全装備:滑り止め付きのフェルトスパイクやライフジャケットは必須。特に初めて行く釣り場では油断せず準備を。
釣果を伸ばすには、こうした変化を「悪条件」と決めつけず、地形や潮の変化に対応する練習の場だと捉えるのがおすすめです。
まとめ|雨の後でも釣果を出すには?

雨の後の釣りは、「釣れる魚」「釣れない魚」「釣りやすい条件」「危険な状況」などが複雑に絡み合う、ハイリスク・ハイリターンのタイミングです。
ただ、釣行データ1,000回以上の私の経験からも、しっかり条件を見極めて釣りをすれば「雨後こそ爆釣」の可能性も十分あります。
ポイントは以下のとおりです。
- 釣れる魚と釣れにくい魚を把握する
- 濁り・水潮・増水など状況の変化を読む
- 雨後でも効果的なルアーや仕掛けを使う
- 安全対策を徹底する
「釣れない」と決めつけて釣りに行かないのはもったいない。チャンスに変える力が雨後の釣りにはある──そんな気持ちで、ぜひ次回の釣行に活かしてみてください。
釣果アップを狙うなら、この潮を狙え!
雨の後でも釣れやすい潮回りは確実にあります。特に潮がよく動く日を狙うことで、濁りや水潮の悪影響を打ち消しやすくなります。下記の記事では、それぞれの潮の特徴と釣り方を詳しく解説しています。
▶ 大潮の日に釣果を伸ばすコツとは?
干満差が大きく、潮がよく動く大潮は、雨の影響をリセットしやすい日。特に濁りや水潮が流れ出すタイミングに注目したい方はこちらの記事へ。
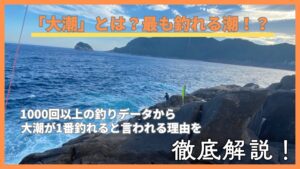
▶ 中潮が実は一番釣りやすい?実釣データで解説!
「釣果が安定しやすい」と言われる中潮。実は、大潮よりも釣りやすいというデータも?釣行回数1,000回超の筆者の体感ベースで詳しく掘り下げます。
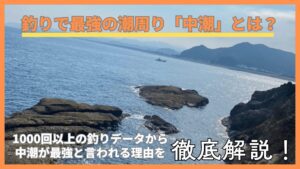

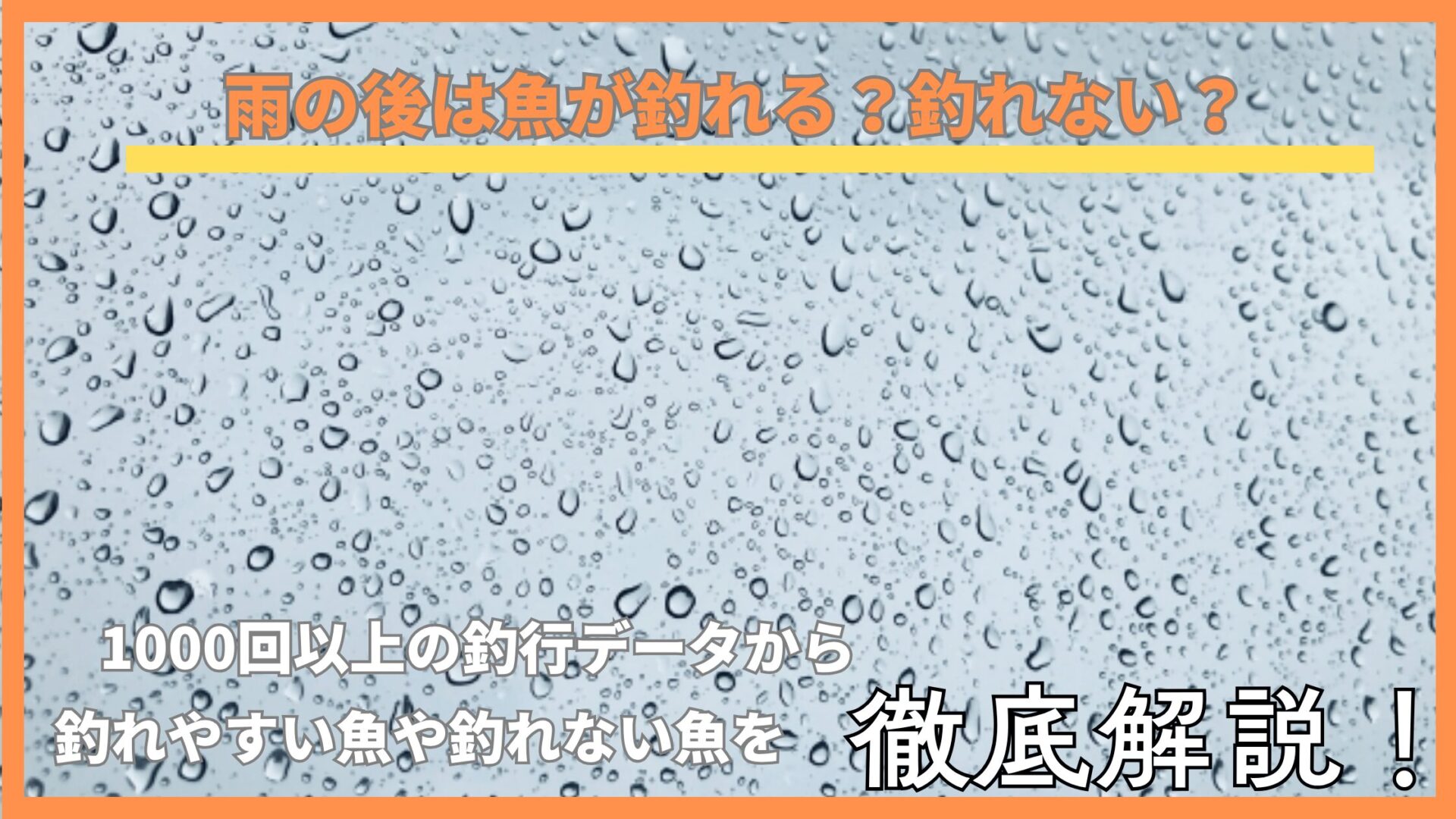

コメント