アジの刺身やなめろう、タタキなど、生食で楽しむ人も多い人気の魚「アジ」ですが、「アニサキスがいるのでは?」と不安に感じたことはありませんか?
実はアジにもアニサキスが潜んでいるケースはあります。
しかも、釣り人の中でも知らずに当たってしまった…という声も少なくありません。
私自身、アジをこれまでに1000匹以上釣って捌いてきた経験があり、その中で実際にアニサキスを発見したことも何度も有り、誤って食べて当たってしまったこともあります。
この記事では、そうした実体験をもとに
✅1000匹以上捌いてアジにアニサキスがいた確率
✅刺身だけでなくなめろうも危険なのか?
✅アニサキスの見つけ方や安全な対策法
等を、釣り人・料理する人、どちらにも役立つ情報を徹底的に解説します。
「アジを安全においしく食べたい!」という方は、ぜひ最後までご覧ください。
アジのアニサキス寄生確率はどれくらい?実体験と公的データ比較

釣り人にも人気のターゲットであるアジ。私自身、これまでに1000匹以上のアジを釣って捌いてきました。
その中でアニサキスを実際に発見したこともあれば、当たった経験もあります。
本記事では、公的なデータに基づいた「アジのアニサキス寄生率」に加えて、私の釣果と体験談を交えて、よりリアルな確率を解説していきます。
私の実体験|1000匹以上捌いたアジのアニサキス寄生の確率は?
私はこれまでに釣ったアジを中心に、これまで1000匹以上のアジを捌いてきました。
その中で、少なくとも10匹以上はアニサキスらしき寄生虫を発見しています。
特に秋〜冬にかけての脂がのったアジを刺身で食べるのが好きで、自分で釣ったアジだけでなく、美味しそうな鯵を見つけた時はスーパーの刺身用アジもよく購入してきました。
実はそのスーパーのアジでも、過去にアニサキスを見つけたことがあります。
詳細な匹数までは数えていませんので感覚的な話にはなりますが
おそらく100匹に1.5匹ほどの確率(約1.5%)で見つけている印象です。
アジは小さい個体だと「一度に複数匹まとめて捌いて食べる魚」なので、他の魚よりも寄生虫に出会う機会は多いと感じています。
アジのアニサキス寄生率は0.5〜3%って本当?公的調査等の数字を整理
“アジにアニサキスがどれくらいの確率で寄生しているか“さらに正確な数字が気になる方も多いと思います。
アジに寄生するアニサキスの確率について、いくつかの公的なデータも調べて見ました。
まず、公的なデータとしては、内閣府食品安全委員会の国立医薬品食品衛生研究所が行った調査では以下の通りでした。
調査対象:アジ397匹
寄生が確認された個体数:3匹
寄生率:約0.75%
情報参照元:内閣食品安全委員会
この数値を見る限り、アジのアニサキス寄生率は「1%未満」とかなり低めに感じます。
一方で、個人ブログが発信している情報では、1〜5%程度というデータも多く見られました。
小規模な漁協・保健所の調査結果は0%~最大3%程度と、かなりムラがありました。
基本的には1%前後と確率は低めですが、まれに局地的に高い寄生率が報告されることもあり、油断は禁物です。
実際に私自身1.5%前後の確率で確認しているので、地域差やその年ごとの海の状況で前後する恐れがあります。
大型回遊アジや季節でアニサキス発生率に違いはあるのか?
一般的に、大型の回遊アジほどアニサキスのリスクが上がると考えられています。
その理由は、食物連鎖の上位にいる魚を捕食するため。
アニサキスを保有している小魚をエサにする機会が増え、それに伴ってアニサキスに寄生される確率も高くなるわけです。
実際に私も、10cm以下の豆アジから40cmを超えるテラアジまで数多く捌いてきましたが、明らかに大きい個体の方が寄生確率が高いと感じています。
とはいえ、小アジでもアニサキスが見つかることはあるので油断は禁物。
100匹に1匹いるかいないかというレベルではありますが、ゼロではありません。
また、アニサキスの寄生リスクは春から初夏にかけてやや高まる傾向があります。
これは産卵や水温変化により、魚の捕食行動が活発になることが関係していると考えられています。
アジのアニサキスを見つける方法とは?簡単に出来るアニサキス対策

アジの刺身やなめろうを楽しみたいけど、アニサキスが心配で不安…という方も多いのではないでしょうか。特に最近では「アジにもアニサキスがいる」という情報がSNSやメディアで広がり、慎重になる方が増えています。
しかし、アニサキスによる被害は、ちょっとした処理の工夫や知識で大幅に防ぐことができます。ここでは、家庭でも簡単にできるアニサキス対策を分かりやすく解説します。
釣ったアジを刺身で食べたい方や、スーパーで買った生アジを安心して調理したい方は、ぜひ参考にしてみてください。
内臓除去&即冷却が最も簡単で効果的
アジに限らず、アニサキス対策として最も効果的かつ現実的なのが「内臓除去」と「即冷却」です。
特にアニサキスは主に内臓に寄生しており、死亡後に筋肉に移動するとされているため、釣ってすぐに内臓を処理すれば、その移動リスクを大幅に下げられます。
実際に私もアジを生食(刺身やなめろう)で楽しみたい場合は、家に持ち帰る前に現地で内臓を除去するようにしています。
慣れてしまえば、ハサミやナイフがなくても手だけで「鯖折り」と呼ばれる方法で首と内臓を一緒に外すことができ、数秒で処理が可能です。
また、内臓を抜いた後は氷水にすぐ浸けて冷却することで、アニサキスの動きを止める効果も期待できます。
美味しく安全に食べる為に、釣行時にはクーラーボックス+氷は必須です。
このように、「内臓除去+即冷却」は誰でも簡単にできる上に、アニサキス対策として最も現実的な手段です。
対策にはブラックライト(アニサキスライト)の使用がオススメ!
アニサキス対策の中でも最も手軽かつ確実な方法のひとつが、ブラックライト(通称:アニサキスライト)の使用です。
アニサキスは紫外線(UV)を照射すると青白く発光する性質があるため、捌いた魚の内臓や身にライトを当てるだけで、肉眼では見つけにくいアニサキスも簡単に発見できます。
実際に私も使用しているおすすめは、ハピソンの「津本式アニサキスライト YF-980」。
津本式の究極の血抜きで有名な津本光弘氏監修で、アニサキス発見に特化した専用設計で、とにかく視認性もよく、白身魚や内臓の寄生等のわかり辛い部分でもハッキリとアニサキスが浮かび上がります。
実際に私自身、目視で見落としたアニサキスにあたって病院で1万円近くの出費をした経験があり、コスパで考えても、たった1回のアニサキス事故を防げるなら十分すぎる価値があるアイテムです。
アニサキスを見つけた時の対応と注意点
釣った魚をさばいていてアニサキスを見つけてしまったら、まずは落ち着いて対応しましょう。気持ち悪いとは思いますが、発見できたのはむしろラッキーです。
基本的にはアニサキスがいた部分とその周囲の身を少し多めに削ぎ落とせば問題ありません。
私はいつも、該当部分の身を大きめにカットして除去し、それ以外の部位を料理に使用しています。
取り除けば刺身でも食べられますが、心配なら加熱や冷凍処理を施した方が安心です。
それぞれ、必要な条件は以下の通りです。
- 冷凍:−20℃で24時間以上冷凍
- 加熱:70℃以上で加熱(または60℃なら1分以上)
(参照:厚生労働省公式ページ)
生食用にする場合は特に慎重に確認し、少しでも不安があるなら加熱調理や冷凍保存での対応が無難です。
もしもアニサキスにあたってしまったら(私の実体験込み)
アニサキスにあたってしまった場合、まず最優先で行うべきなのは医療機関を受診することです。
軽い腹痛で済むケースもありますが、激しい痛みや嘔吐を伴うこともあり、素人判断は禁物です。
実は私も過去に2回アニサキスに当たった経験があります。
1回目は鯖の刺身を食べた数時間後に、軽い胃の不快感と腹部の張りを感じました。
痛みも特に無かったので、水分を多めにとって安静にしていたところ、数時間で症状は治まりました。
この経験から「アニサキスは大したことない」と少し油断してしまっていたのですが、2回目のアジで当たった時は全く違いました。
夜にアジの刺身を食べ、翌朝激しい胃の痛みと嘔吐に襲われて、すぐに病院へ。
胃カメラを使って確認してもらったところ、アニサキスが1匹見つかり、その場で摘出してもらいました。
過去に体験した事もない、冷や汗の出るような形容し難い痛みでしたが、大の大人が耐えられない程の痛みでした。
この経験からわかったのは、同じアニサキスでも症状の重さは体調や個体差によって異なるということ。
たとえ前回が軽症だったとしても、次もそうとは限りません。
少しでも異変を感じたら、迷わず病院で診てもらうことをおすすめします。
アジのアニサキス対策と安全性を比較―刺身・なめろう・冷凍・加熱

アニサキスによる食中毒を防ぐためには、魚の食べ方にも注意が必要です。
とくに釣り人や自宅で魚をさばく人にとっては、「どんな調理法が安全なのか」を知っておくことが大切です。
ここでは、生刺身・なめろう・冷凍・加熱といった代表的な魚料理について、アニサキスのリスクを比較しながら、安全性を詳しく解説します。
私自身、刺身でアニサキスに当たった経験があるからこそ、リアルな視点で「危険な調理法」と「安全な調理法」の違いをお伝えできればと思います。
生刺身のリスクと注意点
アニサキスによる食中毒の多くは、生の魚を刺身で食べた際に発症しています。
実際に私も過去アニサキスにあたってしまったのは2回とも刺身で食べた時でした。
とくに内臓付近に寄生していることが多いため、処理の遅れた魚や鮮度の落ちた魚はリスクが高まります。
また、目視での発見が困難なケースも多く、透明で細長いアニサキスが身の中に潜り込んでいることも。
さらに、魚種によっては筋肉部分にも移動するため「内臓を取れば安全」とは言い切れません。
特にリスクが高いのは以下のようなケースです。
⚠️釣ってから内臓処理まで時間が空いた魚
⚠️鮮度が落ちた状態で刺身にされた魚
⚠️家庭で捌く際に目視で見落とすケース
安全に刺身を楽しむためには、釣った直後に内臓を抜いて速やかに冷却・保管すること、そして食べる前には細かくカットし、よく観察することが大切です。
アジのなめろうはアニサキス対策として安全なのか?
アジのなめろうやアジのたたきは「細かく叩いているから大丈夫」と思われがちですが、アニサキス対策としては万全とは言えません。
確かにアニサキスは切断されれば死滅しますが、非常に小さくて細い寄生虫なので、たとえなめろうにして細かく切り刻んでも完全に切断できない場合があります。
そのため、たたきやなめろうだから安心ということはなく、刺身と同じく「生食」のリスクは伴います。
特にアジやサバなどアニサキスが寄生しやすい魚を使用する場合は、新鮮なものを使う・内臓をすぐに処理するなどの基本的な対策が大切です。
どうしても心配な場合は、1度冷凍してから使うのも有効です。
なめろうにした後に揚げ焼きにするのも、実際に私自身よくやっている調理法で非常に美味しくてオススメですよ。
安全度高い調理法:冷凍・加熱の具体的条件
アニサキス対策として最も確実なのは、「冷凍」か「加熱」処理です。
実際に私も不安な魚を生で食べるときは、必ずどちらかの処理を行うようにしています。
特に刺身として食べたいときには、先に冷凍することで安心感が段違いです。
▼ 冷凍処理の条件:
– マイナス20℃以下で24時間以上の冷凍が必要
– 家庭用の冷凍庫(−18℃程度)では48時間以上がおすすめ
▼ 加熱処理の条件:
– 中心温度60℃で1分、または70℃以上で瞬間的に加熱すれば死滅
– フライや唐揚げ、鍋物、煮付けは基本的に安全
どうしても生食が心配な場合は、一度冷凍してから刺身に戻すのが一つの手段。 また、なめろうにしたあとに揚げ焼きにするのも、私自身よくやる調理法で非常に美味しく、家族にも好評です。
安全性と美味しさを両立する方法として、ぜひ覚えておくと安心ですよ。
まとめ|アジのアニサキスは「低リスクだがゼロではない」ことを意識しよう

アジにアニサキスが寄生している確率は高くはありませんが、極端に低いとも言い切れないのが現実です。
特に刺身やなめろうといった生食メニューではリスクが残るため、十分な対策が必要です。
もし生で食べるなら、
- 釣り場で内臓をすぐに抜く
- しっかり氷締めして持ち帰る
- 帰宅後にブラックライトなどでの目視チェック
この3点を意識することで、リスクはかなり軽減できます。
とはいえ「不安が残る」という方は、冷凍(-20℃で24時間以上)または加熱(70℃以上)をすれば確実に安全です。
しっかり対策した上で、安心してアジの美味しさを楽しみましょう!

関連記事|他の魚のアニサキス寄生状況もチェック!
これまで何千匹もの魚を釣って実際に捌いて食べてきた経験から、アジ以外の魚のアニサキスの寄生状況についても詳しく解説しています。気になる魚種があれば、ぜひ参考にしてみてください。
▶ 真鯛にアニサキスはいる?安全に刺身で食べる方法とは

▶ ブリにアニサキスは寄生する?実体験と対策を紹介

▶ タチウオにもアニサキスはいる?釣り人の注意点まとめ

▶ イカにアニサキスはいる?捌き方とリスクの回避方法

▶ マゴチに寄生虫はいる?アニサキスとの関係も解説


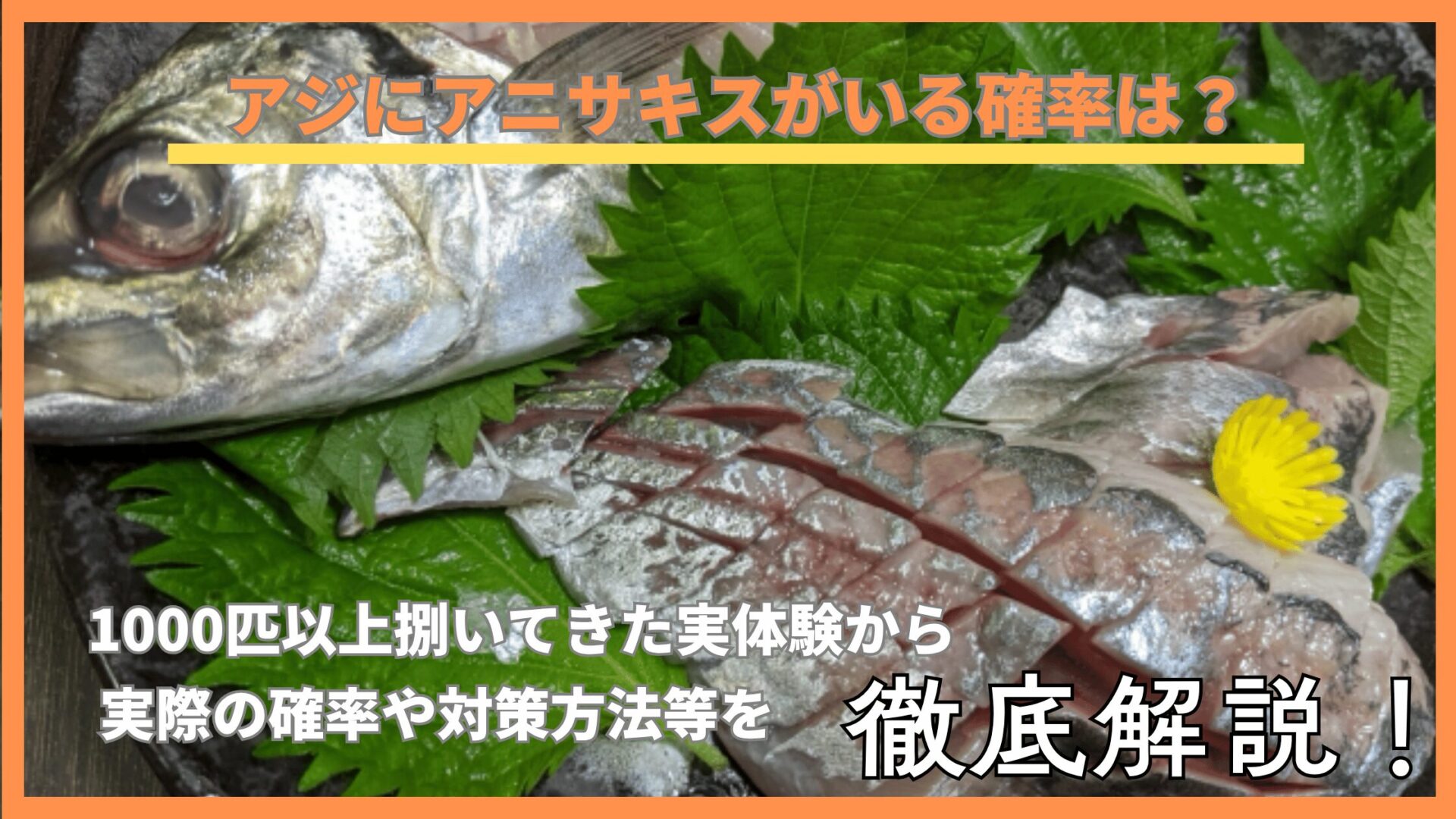

コメント