「青物ってルアーだけじゃないの?」と思っている方、実はエサ釣りでもしっかり釣果が狙えるんです。私自身、ルアーではまったく反応がなかった日でも、エサ釣りに切り替えた途端にヒラマサやワラサがヒットした経験があります。
この記事では青物のエサ釣りにフォーカスして、堤防や船での釣り方、釣果アップの仕掛け・エサ選び、そして実践で気づいたリアルな注意点までを徹底解説します。
初めて青物をエサで狙う方でもわかりやすく、実体験を交えながらまとめています。ぜひ最後まで読んで、大物青物との出会いを掴んでください。
青物のエサ釣りを始める前に知っておきたい基本知識

青物は回遊魚のため、ルアー釣りのイメージが強いかもしれませんが、実はエサ釣りでも十分に狙えるターゲットです。むしろ、活性が低いタイミングやプレッシャーの高い状況では、エサ釣りの方が食わせやすいケースも少なくありません。
特に秋〜初冬にかけては、ブリやカンパチ、ヒラマサなど大型青物が堤防からでも狙える季節。エサ釣りはそうしたタイミングにおいて、初心者でも比較的釣果が出やすい手法のひとつです。
ここでは、まず「堤防」と「船」それぞれのエサ釣りスタイルについて、私自身の経験をもとに解説していきます。
堤防から楽しむ青物エサ釣りの魅力と実践法
堤防からの青物狙いは、エサ釣り初心者にとって非常に魅力的なスタイルです。道具もシンプルで、足場も安定しており、安全かつ気軽に大物が狙える点が大きなメリット。
使用する仕掛けは「ウキ釣り」や「泳がせ釣り」が主流で、遠投性能のある磯竿と中型リールの組み合わせが定番。エサはアジやイワシの生き餌、あるいはサバの切り身などもよく使われます。
実際、私が通う青物狙いで通う堤防でも、ルアーマンより泳がせ釣りの方が多いです。
なお、堤防釣りではタモの準備や混雑時のマナーにも注意。安全に配慮しながら、ゆとりを持った釣行が理想です。
船から狙う青物のエサ釣りは効率とスリルが段違い
一方で、青物のエサ釣りでもっとも効率的に釣果を狙えるのが船釣りです。私も年に数回は乗合船を利用していますが、やはりアタリの数・サイズともに船ならではの魅力があります。
エサはコマセ釣りや泳がせが主流で、特にコマセによって青物を寄せる「カゴ釣り」は強力。オキアミを使った撒き餌と、同調させた付けエサを一緒に流すことで、高確率でヒットが狙えます。
東京湾では、夏〜秋にかけてイナダやワラサが好調な時期があり、1日で数本の釣果を上げることも珍しくありません。
ただし、船釣りは潮流の知識やタナ取りの精度が重要になるため、初めての場合は船宿スタッフにアドバイスをもらうのが吉です。道具もレンタルできる場合が多いので、気軽にチャレンジしてみてください。
最強の釣り方は「泳がせ釣り」理由も解説

青物のエサ釣りにはさまざまなスタイルがありますが、結論から言えば最強は泳がせ釣りです。生きたエサをそのまま使うことで、他の釣法ではなかなか反応しない大型の青物にもしっかり口を使わせることができます。
ここでは泳がせ釣りの優位性に加えて、併用テクニックや注意点など、現場で使える実践的な情報をお伝えします。
泳がせ釣りが青物に圧倒的に効く理由
泳がせ釣りは、生きたアジやイワシなどを使って青物を狙う釣法です。人工的な動きではなく、本物のベイトの動きで誘えるため、青物の警戒心をくぐり抜けてバイトを引き出すことができます。
近所に餌屋さんがあればそこで生き餌を買っていく事もできますが、餌となる魚を釣り場で釣ればお金がかからないのも嬉しいポイント。
特に回遊魚である青物は“スイッチ”が入ると一気に食い気が立ちますが、そのスイッチを入れるにはリアルな動きと存在感が必要。この点において、生き餌の泳がせは他の釣法を圧倒しています。
経験上、ルアーや切り身では無反応なタイミングでも、泳がせに替えた瞬間に強烈な引きがくることは何度もありました。迷ったらまずは泳がせ、というのが私の結論です。
ルアーフィッシングと併用できる泳がせ釣りの魅力
泳がせ釣りのもうひとつの強みは、ルアー釣りと同時進行できるという点です。私は堤防釣りの際、泳がせ仕掛けを1本出しておいて、もう1本でショアジギングを楽しむ、というスタイルをよく採用しています。
泳がせの仕掛けは一度流してしまえば基本的には“待ちの釣り”になるので、その間にアクティブにルアーをキャストできるのが魅力。
しかも、活き餌が自然に泳いでアピールし続けてくれるので、無駄のない効率的な釣り方としてもおすすめです。時間を最大限に活用したい方にはぴったりのハイブリッド戦術です。
泳がせ釣りを安全&スマートに楽しむための注意点
泳がせ釣りは強烈なバイトを引き出す反面、トラブルや事故も起きやすい釣り方でもあります。特に注意したいのが「竿の固定」です。
私自身、タックルをしっかり固定せずに置き竿にしていたところ、突然のブリのバイトで竿ごと海に引きずられた経験があります。それ以来、泳がせの竿はしっかりと竿受け+ベルトで固定するようにしています。
また、泳がせ釣りは広範囲に渡って餌の魚を自由に泳がせる釣りですので、他の釣り人の邪魔になりがちです。周囲との間隔を多めにとるのがマナーですので、人が密集してる場所では行わないようにしましょう。
強力な釣法だからこそ、周囲への配慮と安全管理を徹底することが、トラブルを避けて楽しむための必須条件です。
青物のエサ釣りで失敗しないための実践アドバイス

青物のエサ釣りは、仕掛けやエサがシンプルだからこそ小さな差が釣果に直結します。私自身も最初は「タナが合っていなかった」「エサの状態が悪かった」といった初歩的なミスで釣り逃した経験が何度もあります。
ここでは、初心者がやりがちな失敗とその対策、さらに実体験をもとに感じた「このタイミングが一番釣れる」というポイント、そして最後にもう一度青物のエサ釣りで押さえておきたい心構えをまとめてお伝えします。
初心者がやりがちなミスとその対策
青物のエサ釣りでありがちなミスのひとつがタナの設定ミス。堤防釣りでよくあるのが「ウキを浮かべっぱなしで反応がない」という状況です。これはタナ(狙う水深)が合っていないことが多く、青物が通るレンジに仕掛けが届いていないためです。
対策としては、周囲の釣り人の様子をよく観察し、タナや潮の流れを参考にすること。また、エサの状態にも注意が必要で、切り身の場合は乾燥しすぎないように、小まめに交換することも大切です。
もうひとつの失敗例は、仕掛けの選び方。市販仕掛けに頼りすぎて、現場の状況と合っていないパターンです。風や潮流の強さに応じて、オモリの号数やウキの浮力を見直す癖をつけましょう。
実体験から学んだ青物エサ釣りのベストタイミング
私が一番釣果を上げている時間帯は、なんといっても朝マヅメ(夜明け前後の1〜2時間)です。特に堤防釣りでは、太陽が昇る瞬間に青物の群れが一気に接岸してくるのを何度も目撃しました。
また、潮の動きも非常に重要。「上げ三分〜下げ三分」といわれるように、潮がしっかり動いているタイミングが最もアタリが出やすいです。
逆に日中の潮止まりは、魚の活性が下がりがち。そんな時は無理に粘らず、エサの管理や仕掛けの調整に時間を充てる方が効率的です。
タイミングが合えば、泳がせ釣りで80cm超のブリやヒラマサが掛かることもあるので、短時間勝負の意識を持って臨むと良い結果が出やすいです。
青物のエサ釣りで釣果を出すために必要な心構えとは
最後に、青物のエサ釣りで実に釣果を出したいなら、ただ仕掛けを投入するだけでなく、変化に敏感になることが大切です。
天候、潮、風、魚の動き…そのすべてが変わる中で、エサの種類やタナ、仕掛けの微調整を繰り返す柔軟さが釣果を左右します。
また、情報収集の重要性も忘れてはいけません。釣果情報、潮見表、地元の釣り人のSNSなどから、前日の状況や釣れた時間帯を把握しておくだけでも、当日の戦略が立てやすくなります。
何より、「今日は釣れないかもしれない」という日も前向きに楽しめる気持ちが、最終的には大きな釣果につながることを、私自身の経験からも強く感じています。

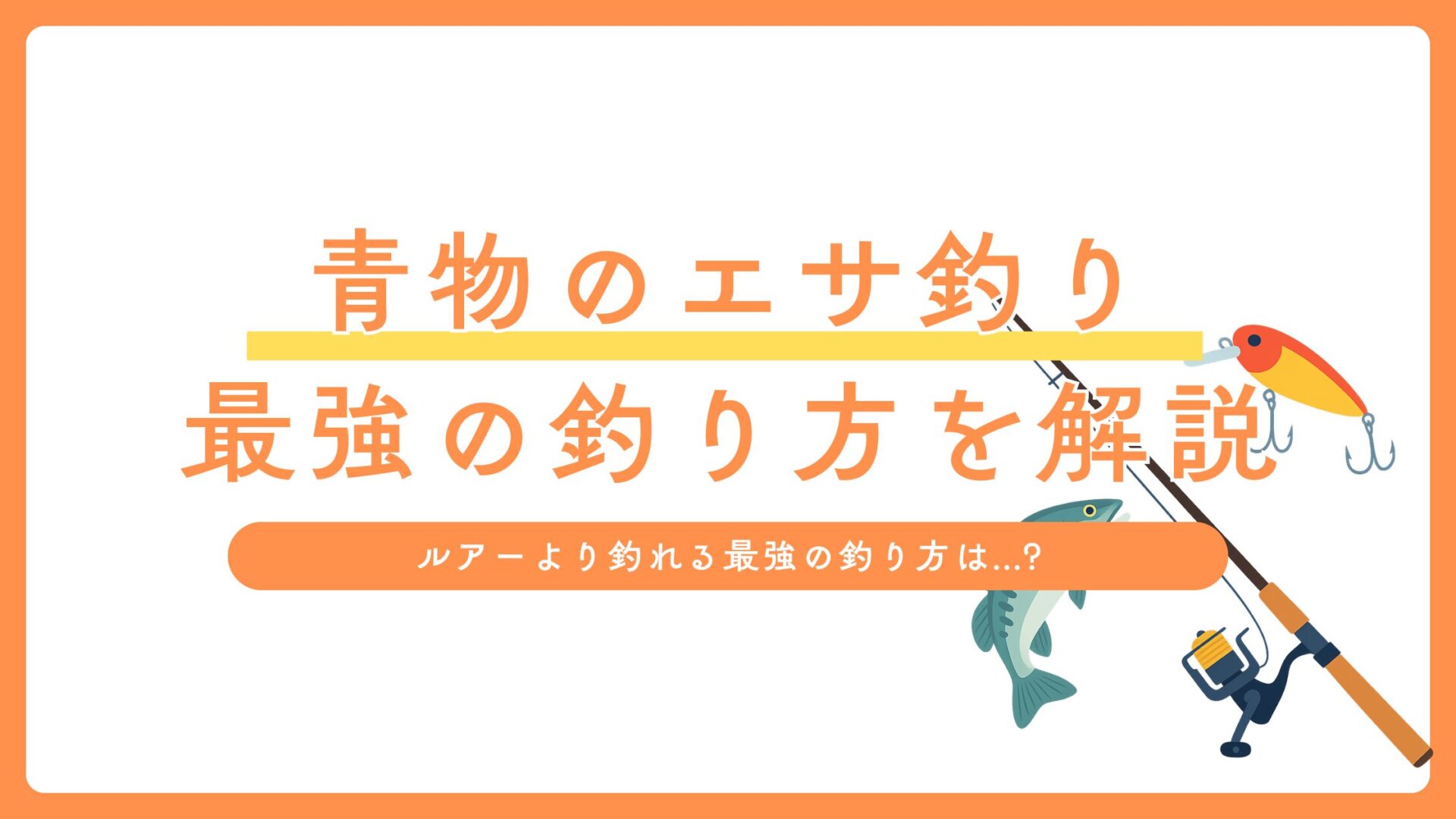
コメント