こんにちは、つりはる代表のはるです。
私はシーバス歴10年以上、ここ5年は毎年100匹以上をキャッチしてきました。
特にバチ抜けシーズンには、1日で10匹以上釣れることもあり、毎年この時期が待ち遠しくて仕方ありません。
そんな中でよく耳にするのが「そもそもバチ抜けって何?」「どの時期に起こるの?」といった疑問です。
私も最初の頃は仕組みやタイミングがわからず、せっかくフィールドに立っても釣果につながらないことが多くありました。
でもバチ抜けを理解すると、シーバス釣りの難しい時期が一気に爆釣シーズンへと変わるんです。
この記事では、これまでの経験と実際の釣果を踏まえて、バチ抜けとは何か・シーバスが釣れる時期や条件についてわかりやすく解説していきます。初心者の方はもちろん、これから本格的にシーバスを狙っていきたい方の参考になれば嬉しいです。
そもそも「バチ抜け」とは?シーバスとの関係を解説

「バチ抜け」とは、多毛類(ゴカイやイソメなど)が産卵のために一斉に水面へと浮上する現象を指します。
普段は砂や泥に潜って生活しているバチが、特定の時期になると群れで水中を漂い始めるため、水面や水中に無数の小さな生物が泳ぎ回る光景が見られます。
この現象こそが「バチ抜け」であり、釣り人の間ではシーバスが爆釣する合図として知られています。
なぜなら、バチはシーバスにとって格好のベイト(餌)だからです。普段は捕食の難しいシーバスも、この時期だけは水面近くで大量のベイトを容易に捕食できるため、活性が一気に高まります。実際にナイトゲームで水面を見ていると、無数のライズ(捕食音)と共にシーバスがバチを追いかけ回す光景に出会うことができます。
私自身、シーバス歴10年以上の中で「バチ抜けシーズンほど釣れる時期はない」と断言できます。ここ5年は毎年100匹以上を釣っていますが、その大部分を占めるのがこのシーズンです。
ときには1晩で10匹以上キャッチすることもあり、まさに「バチ抜け=シーバスのハイシーズン」と言っても過言ではありません。
つまりバチ抜けは、ただの季節的な生態現象ではなく、シーバスアングラーにとって年間最大のチャンスをもたらす出来事です。バチ抜けを理解することで「釣れない時期」を「爆釣シーズン」へと変えることができます。
バチ抜けが起こる時期や時間帯は?
バチ抜けは「いつ起こるのか?」を理解することが、シーバスを効率よく狙うために欠かせません。
大きく分けると時期(シーズン)と時間帯(釣行のタイミング)の2つがポイントになります。
バチ抜けの時期
一般的にバチ抜けは1月〜5月頃に起こることが多いですが、地域やフィールドの違いによって発生する時期は変わります。
河川では水温変化が早い影響で1〜2月頃から始まることも多く、港湾部は水温が安定しているため4〜6月にピークを迎えることが多いです。
また、南のエリア(九州や四国など)では12月からスタートすることもあり、北のエリアでは5月〜6月頃が中心になる場合もあります。
私の地域では、ここ数年は6月にバチ抜けが発生するケースが多く、例年より遅めに釣果が伸びる傾向があります。
地域や年ごとの水温・潮流の影響で発生時期が前後するため、フィールドごとの特徴を把握しておくことが大切です。
私自身の経験でも、真冬の河川で2月に爆釣したこともあれば、5月の湾奥でまだバチパターンが効いたこともあります。
つまりバチ抜けは地域ごとに発生タイミングがずれるため、長期間楽しめるシーズンともいえるのです。
バチ抜けの時間帯
バチ抜けは暗くなってから起こります。その為狙い目は夕方〜夜間です。
日中は基本的にはバチ抜けは起こらないですが、バチ自体は湧いているので、日中でもバチパターンで釣れるチャンスは十分にあります。
特に日没後の下げ潮で流れが効き始めるタイミングはチャンスで、満潮から下げ3分〜5分にかけてはシーバスの捕食が最も活発になります。
また、大潮や中潮など潮位差が大きい日には一気にバチが抜け出すこともあり、釣果を大きく左右します。
私の体感では、夕まずめ直後にバチ抜けが始まる事はあまり無く、日が完全に沈みきって数時間した夜9時〜深夜0時頃にかけての時間帯に釣果が集中することが多いです。
もちろん場所によっては朝マズメに残りバチを食うシーバスが釣れることもありますが、やはりメインは夜の下げ潮です。
まとめると、バチ抜けを効率的に狙うには時期(季節ごとのピーク)と時間帯(潮の動きと夜間)をしっかり意識することがカギになります。
バチ抜けシーバスが釣れやすい条件とは?

バチ抜けが発生する時期や時間帯を理解したうえで、さらに釣果を伸ばすために重要なのが「条件」です。潮回りや月齢、風や水の流れといった要素が重なると、シーバスの活性が一気に高まります。
ここでは、私自身の経験も踏まえながら釣れやすい条件を紹介します。
潮回り
大潮や中潮の下げ潮は最もバチが抜けやすく、シーバスも捕食行動に移りやすいタイミングです。特に満潮から下げ始めの時間帯は水面に流れが生まれるため、バチが一斉に流れ出し、シーバスのボイル(捕食音)が連発します。
逆に小潮や長潮の日はバチがあまり動かないこともあり、釣果に差が出やすいです。
月齢
バチ抜けは満月前後の夜に発生しやすい傾向があります。月明かりに照らされた水面で、無数のバチが泳ぐ光景を見られることも珍しくありません。
私の地域でも、実際に大潮かつ満月の夜にシーバスの活性が極端に上がり、このパターンで何度も短時間で連発した経験があります。
風や水の流れ
無風または微風で水面が安定している夜は、バチが水面をゆっくり泳ぎやすく、シーバスもライズしやすくなります。逆に強風や波立ちがあると、バチが水中に潜ってしまい、目に見えるほどのボイルが起きにくくなります。
また、流れのヨレ(反転流や合流点)はバチが溜まりやすく、シーバスが着きやすい一級ポイントです。
明暗部
街灯や橋脚の明かりに集まったバチはシーバスの格好の捕食対象になります。
「暗いエリアよりも光のあるエリア」の方が狙いやすいケースが多く、実際に私も橋脚周りの明暗部で1時間に5本以上キャッチした経験があります。
これらの条件を意識して釣行することで、バチ抜けのチャンスを最大限活かせるようになります。単純に「時期だから行く」だけでなく、潮・月・風・流れ・明暗を組み合わせて考えることが、シーバスを効率的に釣るコツです。
バチ抜けシーバスを狙うおすすめのポイント

バチ抜けが起こるとシーバスは広範囲で捕食を始めますが、ただ闇雲にキャストしても効率的に釣果を上げるのは難しいです。
実際に私が10年以上シーバスを狙ってきた経験では、「どこにバチが溜まりやすいか」「シーバスが待ち構えやすいか」を意識して釣行すると、一晩での釣果が2倍以上変わることもありました。ここでは特におすすめできるポイントを詳しく解説します。
港湾部の常夜灯周り
港湾エリアはバチ抜けの定番ポイントです。
常夜灯や岸壁沿いの照明にバチが集まりやすく、それを追ってシーバスも寄ってきます。水面を観察していると、光の当たる部分と暗い部分の境目(明暗部)でバチが漂い、それを狙うシーバスがライズする光景をよく見かけます。
私も過去に、港湾の常夜灯下だけで2時間に8本キャッチした経験があり、「ここを押さえるだけでもシーズンは戦える」と実感しています。
河川の合流点やヨレ
河川は流れが複雑に絡む場所がポイント。支流との合流点やカーブの内側など、水流が緩む場所にはバチが溜まりやすく、そこをシーバスが効率的に狙っています。
特に2月〜3月のまだ寒い時期は、河川バチが先行して抜け始めることが多く、早い時期から釣果を上げたい人におすすめです。私の地域でも毎年「最初の爆釣」は河川から始まることが多いです。
橋脚周り・明暗部
橋脚は潮の流れと光の両方が絡む一級ポイントです。常夜灯や街灯の影にバチが溜まり、そこにシーバスが定位して捕食するため、短時間でも効率よく釣果を伸ばせます。
特に下げ潮で流れが効き始めた瞬間はチャンスタイムで、私も「橋脚に投げるだけで連発」なんてことを何度も経験しました。
テトラ帯や堤防際
テトラ帯や堤防際は流れが緩むスポットで、バチが漂ってきて自然と溜まりやすい場所です。
表層を漂うバチを意識したシーバスが着きやすく、ナイトゲームでは水面直下をスローに引くだけで簡単に釣れることもあります。
特に風が弱くベタ凪の日はバチが水面に長く留まりやすく、シーバスの捕食行動も活発になるのでおすすめです。
このように、バチ抜けは「どこでも釣れる」わけではなく、港湾・河川・常夜灯・流れのヨレ・堤防際といった条件の揃ったエリアを狙うのが効率的です。
私も数え切れないほど失敗を繰り返しましたが、こうしたポイントを意識するようになってからは、1日の釣果が安定して二桁に届くことも増えました。
なぜバチ抜けシーバスは釣れやすいのか?
普段のシーバスはベイトの種類や水温、潮の状況によって行動が大きく変わるため、狙う側にとっては難しい魚です。しかしバチ抜けの時期だけは例外で、シーバスが圧倒的に釣れやすくなります。その理由を解説していきます。
ベイトが限定される
バチ抜けシーズンのシーバスが釣れやすい1番の要因がベイトです。
バチ抜けシーズンは、シーバスが食べるベイトが「バチ一択」になる事が多いです。
普段のようにイワシやハク、サッパなど複数のベイトを追い分けるのではなく、目の前に大量に漂うバチを効率よく捕食します。つまりアングラーにとってはパターンが単純化される=狙いやすいということです。
捕食しやすい形状と動き
バチは細長い体で泳ぎも遅いため、シーバスからすると非常に捕食しやすいベイトです。
動きの速い小魚を追い回すのに比べると、エネルギーをほとんど使わずに捕食できます。このため活性が上がり、表層でライズを繰り返すような光景がよく見られるのです。
ライズによる視覚的なヒント
普段のシーバス釣りでは「どこに魚がいるのか分からない」ことが多いですが、バチ抜けでは水面に無数のライズが出るため、シーバスの居場所が一目瞭然になります。私自身も経験上、ライズの出ている所にルアーを通すだけで何本も連発できたことがあり、初心者でも釣果を伸ばしやすいシーズンだと感じています。
実際の釣果からの実感
シーバス歴10年以上の中で、私が1日で10匹以上釣れた日の半分程はバチ抜けのタイミングでした。
ここ5年間で毎年100匹以上キャッチできているのも、バチ抜けシーズンにしっかり通っているからです。
つまり「なぜ釣れるのか?」という疑問に対する答えはシンプルで、ベイトが偏り、捕食が容易で、視覚的にもシーバスを見つけやすいからこそ、バチ抜けは特別に釣れやすいのです。
バチ抜けシーバスの釣り方とおすすめタックル
バチ抜けシーズンのシーバスは「狙いやすい」ですが、釣果を安定させるにはタックル選びと釣り方が重要です。
ここでは、私が実際に愛用しているタックルと釣り方を紹介します。
バチ抜けシーバス用のロッド
通常のシーバス狙いではMLが人気で定番ですが、バチ抜けでは通常より柔らかめのロッドが扱いやすい為「Lクラス」のライトロッドがおすすめで、バチのようにゆっくり動かすルアーを自然に演出しやすく、繊細なアタリも逃しません。
柔らかいロッドはキャスト時の乗せ感も良く、ルアーを遠くに飛ばすことにも役立ちます。
バチ抜けシーバス用のリールとライン
使用するPEラインも通常のシーバスゲームよりやや細めの0.6号前後がおすすめ。
それに合わせるとリールは2500番が使いやすく、ドラグ性能が安定したモデルが安心です。
バチ抜けはスローな釣りが多く、強引なやり取りが少ないため、細いラインでも十分対応できます。
細くすることでキャスト飛距離やルアーの操作感度も向上します。
バチ抜け用のおすすめルアーを紹介
バチ抜けシーズンのルアーに求められる条件は大きく3つあります。
①軽量でも十分な飛距離が出せること
②水面直下をゆっくり引け、ナチュラルに漂うアクションを出せること。
③細長いシルエットである事
上記の条件を満たすルアーが最適なので、基本的には「シンキングペンシル」か「ワーム」がバチ抜けルアーに最適です。
バチの泳ぎは非常に遅く、ルアーを早く巻いてしまうと一切食ってこないのが特徴です。
わざわざ追いかけてまで捕食する必要がないため、シーバスは「簡単に食べられるもの」しか口を使いません。
バチ抜け用のルアーは各メーカーから発売されており様々なモデルが存在しますが、私が数多くのルアーを試した中で最も信頼しているのがDUOから発売されているシンキングペンシルの「マニック95」です。
軽量ながら飛距離がしっかり出る設計で、広範囲を探ることが可能。水面直下をスローに巻くだけで自然な波動を出し、シーバスの捕食スイッチを簡単に入れてくれます。さらに、沈めて使うことで「うねうね」としたバチそっくりの動きを演出できるのが最大の強みです。
私自身、バチ抜けシーズンでは毎回このルアーをスタメンに入れています。
さらに、バチパターンだけでなく小型ベイトを偏食している状況でも通用するので、まさに万能かつ最強のバチ抜けルアーだと思います。
▼他のおすすめのバチ抜け用ルアーについては以下の記事で詳しく紹介しています▼

釣り方のポイント
基本は水面直下をスローリトリーブすること。バチはスピードが遅いため、早く巻きすぎると不自然になり食わせづらくなります。
また、ルアーを沈めて「うねうね」と泳がせるのも有効。潮の流れに同調させながら弱い生命感を出すと、シーバスが自然に口を使ってきます。
私も実際に、この「マニック95のスローリトリーブ」で1晩に10本以上の釣果をあげたことがあります。
シンプルな釣り方ですが、バチ抜けシーズンには圧倒的な効果を発揮してくれる鉄板ルアーです。
バチ抜けシーバスを狙う際の注意点
バチ抜けシーズンはシーバスが釣れやすい一方で、ちょっとしたミスで「全く釣れない夜」になってしまうこともあります。ここでは、私自身が何度も失敗して学んだ注意点を紹介します。
スレやすさに注意
バチ抜けのシーバスはとにかくスレやすいです。バチは遅いスピードで漂っているため、ルアーを少しでも早く動かすと「不自然」と判断して一切口を使わなくなります。
特に数本釣れたあとにアタリが急に止まることがありますが、その多くは「魚がスレた」サイン。
そういう時はルアーサイズを落としたり、リトリーブスピードをさらに落としてあげると再び口を使ってくれることがあります。
ルアーサイズを合わせる
抜けているバチの大きさにルアーサイズを合わせることも大事です。
長いバチが抜けている時に短いルアーを使っても食いが悪くなり、逆に小型のバチが多い時に大きすぎるルアーを投げても見切られてしまいます。
私自身も実際に、9cmのルアーで反応が無かったのに、7cmに変えた瞬間に連発した経験があります。
シーズン中は複数サイズを持ち歩くのが鉄則です。
キャスト位置とトレースコース
いくらシーバスが湧いていても、ただ投げるだけでは釣れません。
潮の流れに沿ってルアーを流すようにトレースすることが大切です。
真正面に投げて巻くだけだと違和感を与えてしまいます。
斜めにキャストして、流れにルアーを自然に乗せると食わせやすくなります。
これは私も初心者時代によくやってしまっていた失敗で、投げる角度を意識しただけで釣果が大きく変わりました。
魚の活性に応じた巻き方
「早く巻いたら食わない」というのは鉄則ですが、活性が低い時はデッドスローに、活性が高い時はやや早めのスローにするなど微調整も必要です。
ルアーを完全に止めるのも有効で、潮の流れに任せて漂わせるだけで食ってくることもあります。
このように、バチ抜けは「簡単に釣れる時期」ではありますが、逆に基本を外すと全く釣れない時期でもあります。
スレ対策・サイズ合わせ・トレースライン・巻きスピード、この4つを意識するだけで釣果は大きく変わってくるので、ぜひ覚えておいてください。
まとめ|バチ抜けは初心者から上級者まで楽しめるシーバスの好機
バチ抜けは「シーバスが簡単に釣れる時期」と言われるほど、アングラーにとって特別なシーズンです。
時期や時間帯を理解し、港湾・河川・橋脚などのおすすめポイントを押さえれば、普段よりも圧倒的に釣果を伸ばすことが可能です。
また、バチは動きが遅いため、ルアーはスローに、自然に漂わせることが重要。おすすめ条件を満たすルアーの中でも、私が信頼しているDUO マニック95はバチ抜け攻略に欠かせない存在です。
ロッドやラインも柔らかめ・細めを選ぶことで、繊細な釣りがしやすくなります。
もちろん、バチ抜けは「釣りやすいシーズン」である反面、スレやすさやルアーサイズの合わせ方を間違えると全く釣れないこともあります。ですが、基本を押さえれば初心者でも十分楽しめ、経験者なら数釣りやサイズ狙いも可能です。
シーバス歴10年以上の私自身も、毎年このシーズンは釣果の中心になっており、バチパターンで1日に10本以上キャッチできた経験が何度もあります。
ぜひあなたも、バチ抜けシーズンを活用してシーバスゲームを存分に楽しんでください。



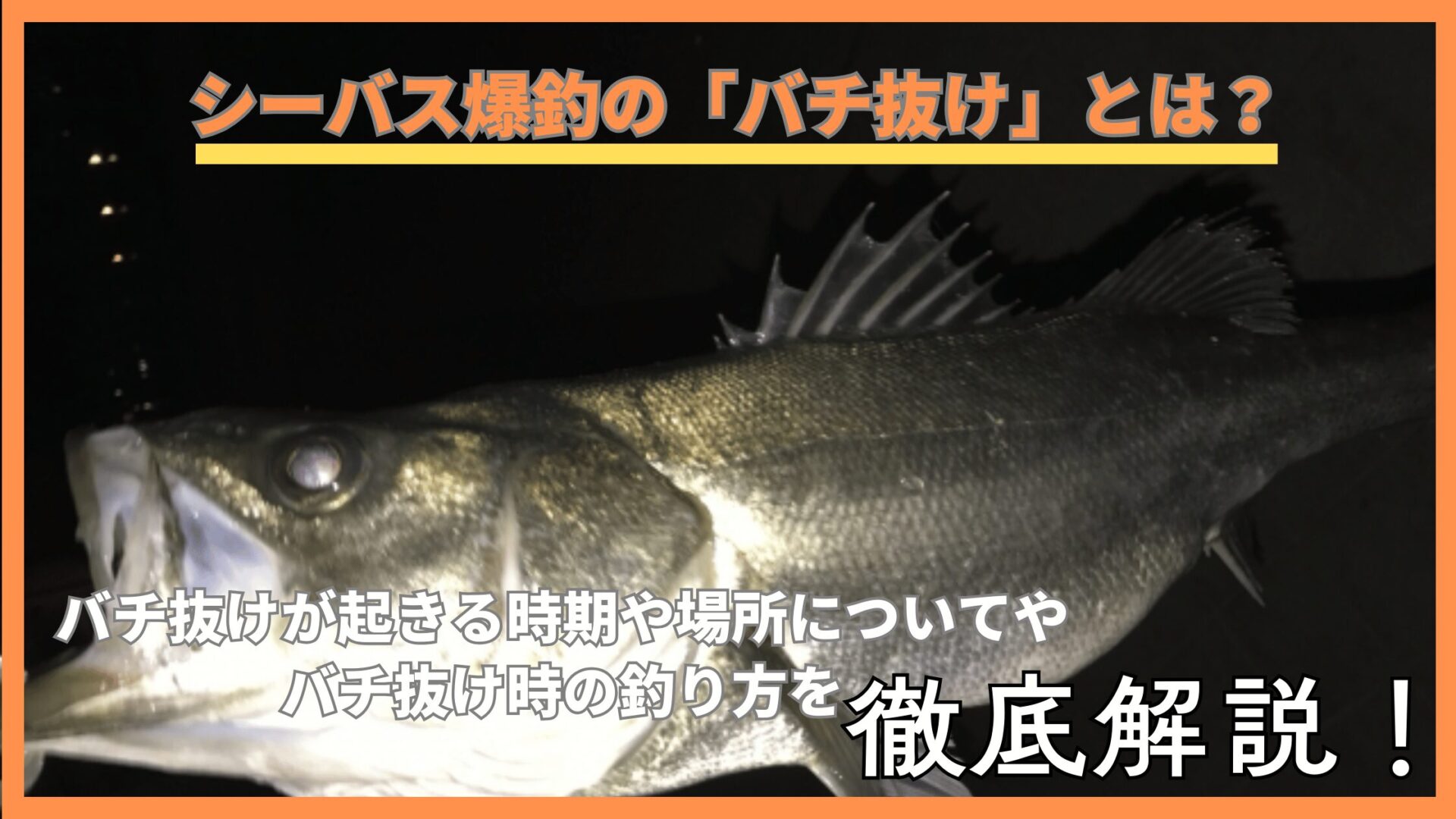



コメント