こんにちは、つりはる代表のはるです。
私は年間200釣行以上をこなし、メバルも小型から尺超えまで毎年100匹以上は釣っています。
メバルは、他の魚が釣れにくい時期でも釣果を出せる貴重なターゲットで、何より見た目がかわいく、個人的にも見た目が一番好きな魚です。
この記事では、そんなメバル釣り歴の長い私が
💡メバルが最も釣れる時期
💡季節ごとの特徴
💡尺メバルが狙いやすいタイミング
などを、実体験をもとに徹底解説します。
メバリングでもエサ釣りでも応用できる内容なので、初心者の方はもちろん、中級者の方にもきっと役立つはずです。
この記事を読めば、「いつ行けば釣れるのか?」が明確になり、時期に合わせた戦略で釣果を安定させられるようになります。
メバルが釣れる季節の目安とベストシーズン

結論から言うと、メバル釣りのベストシーズンは「晩秋〜春」。
この時期は水温やベイトの動きが安定し、メバルの活性も高くなります。特に春先にかけては、数釣りと大型狙いの両方が楽しめる最高の時期です。
ただし、同じ冬でもまったく釣れない時期と爆釣する時期がはっきり分かれるのがメバルの特徴。
その差を生む最大の要因が「産卵前後の行動変化」です。
この記事では、そんな季節ごとのメバルの動きや狙い目の時期を、私の実釣データをもとに詳しく解説していきます。
一年を通した釣れやすい時期とオフシーズン
メバルは一年中岸から狙える魚ですが、季節によって釣果には大きな差があります。
安定して釣りやすいのは「晩秋(11月前後)」と「春(3〜5月)」。
この2つの季節は、水温や日照時間のバランスが良く、メバルの活性が高まりやすいタイミングです。
特に晩秋は冬の産卵に備えて荒食いが始まったり、始春は産卵後の個体が体力回復のために積極的にベイトを追うため、初心者でも釣果を上げやすい時期です。
一方で、夏(6〜8月)はオフシーズン。高水温の影響でメバルが深場に落ち、活性が下がります。夜でも釣れにくく、狙える時間帯がかなり限られます。
とはいえ、潮通しの良い堤防や磯など、水温が低めのポイントを選べばチャンスは十分あります。
年間を通して見ると、秋に接岸 → 冬に産卵 → 春に荒食い → 夏に一時的に深場へというサイクルを繰り返しています。
このリズムを理解することで、季節ごとの狙いどころが分かり、釣果アップに直結します。
メバリング・エサ釣りで最適な時期の違い
同じメバル釣りでも、メバリング(ルアー)とエサ釣りでは最適な時期が微妙に異なります。季節ごとの特徴を理解すると、より安定した釣果につながります。
| 時期 | メバリング(ルアー) | エサ釣り | 特徴・ポイント |
|---|---|---|---|
| 晩秋(11月前後) | ◎ | ◎ | 接岸が始まり釣りやすい。常夜灯周りで表層ただ巻きやウキ釣りが有効。 |
| 冬(12〜2月) | △ | ○ | 産卵期でルアーの反応が鈍く、エサ釣りが有利。産卵前後は荒食いで好機。 |
| 春(3〜5月) | ◎ | ◎ | 産卵後の回復期で荒食いのピーク。サイズも数も狙えるベストな時期。 |
| 夏(6〜8月) | △ | △ | 高水温で深場中心。夜間や潮通しの良い場所でチャンスあり。 |
| 秋(9〜11月) | ◎ | ◯ | 水温が下がり始め復調期。晩秋は荒食いで好シーズン。 |
まとめると、、、
安定した釣果を狙うなら晩秋と春。真冬は活性が落ちる為エサ釣り優勢、メバリングは産卵前後の荒食いを狙うのがコツです。
メバリングについては、以下の記事で詳しく解説しています。



初心者が狙うならこの季節がおすすめ
これからメバル釣りを始める初心者に最もおすすめの季節は、春(3〜5月)と晩秋(11月前後)です。
どちらもメバルの活性が高く、ルアーでもエサ釣りでも釣りやすく・楽しみやすい時期になります。
春は水温上昇とともにメバルが浅場へ回遊してくるため、足場の良い堤防からでも十分に狙えます。
産卵後の個体が積極的にベイトを追うので、表層ただ巻きやウキ釣りで簡単に釣れることも多いです。初心者が最初の1匹を釣るには最適な時期です。
晩秋もまた好シーズン。冬に備えて体力をつけるための荒食いシーズンに入り、どんな釣り方でも反応が出やすくなります。夜の常夜灯周りを狙えば、20cm級の良型が数釣れることも珍しくありません。
反対に真冬(1〜2月)や真夏(7〜8月)は難易度が上がるため、最初は避けたほうが無難です。
まずは春か晩秋のナイトゲームから始めると、気温も快適で釣果も安定します。
メバルの行動パターンと季節の関係

メバルは季節・水温・潮の動きによって行動パターンが大きく変わる魚です。
年間を通して釣れるターゲットではありますが、「いつ・どのレンジに・どんなベイトを追っているか」を把握することで、釣果は一気に安定します。
特にメバルは、主に夜行性で警戒心が強い魚。
昼間は物陰や深場に潜み、夜になるとベイトを追って表層へ浮上します。
そのため、季節ごとにメバルの行動を理解し、狙う時間帯やタナを変えることが釣果アップのカギになります。
ここでは、水温や日照、潮の動きによって変化するメバルの活性や行動パターンについて詳しく解説していきます。
水温・日照・潮の動きで変わる活性
メバルは水温変化や潮の動きに非常に敏感な魚です。
特に水温が15〜18℃前後になると活性が上がり、最も釣りやすいシーズンを迎えます。
反対に、水温が10℃を下回る真冬や25℃を超える真夏は活性が極端に低下し、深場へ移動してしまう傾向があります。
日照時間が短くなる晩秋〜冬は、日中でもメバルが浮きやすくなり、夜は表層でのライズが増える時期。
常夜灯周りや港湾エリアでは、このタイミングが狙い目です。
逆に日照時間の長い夏場は、昼間に姿を見せることが少なく、夜間でもやや深いレンジを意識する必要があります。
潮の動きも重要な要素で、メバルは「潮が動いている時間帯」に活性が高くなります。
特に上げ潮のタイミングでは、ベイトが流れ込むことで捕食行動が活発化しやすいです。
そのため、初心者の方は満潮前後や潮止まり直後を狙うことで、効率的に釣果を上げられるでしょう。
こうした自然条件を理解しておくと、「釣れる時間帯」や「活性の高い層」が明確に見えてきます。水温・潮・光のバランスを意識して釣行を組み立てることが、安定したメバリング成功の第一歩です。
春と晩秋に釣果が伸びる理由
メバル釣りで特に釣果が伸びやすいのは春と晩秋です。この2つの季節には、メバルの活性が上がる明確な理由があります。
春(3〜5月)は、水温の上昇とともに産卵を終えたメバルが体力を回復するために荒食いシーズンに入ります。
この時期は表層〜中層にメバルが浮きやすく、常夜灯周りや港内の明暗部などで数釣りがしやすい時期です。
特に夜の時間帯はベイトを追って活発に泳ぎ回るため、ただ巻き中心のメバリングが非常に有効です。
晩秋(10〜12月)は、産卵前のメバルがエサを溜め込む時期。
このタイミングではサイズの大きい個体が浅場に接岸することが多く、尺メバルの実績も高い季節です。
水温が急激に下がる前に、荒食いをする個体が増えるため、短期間ながらも爆釣するチャンスが訪れます。
つまり、春は数釣りのベストシーズン、晩秋は大型狙いの最盛期。
この2つの季節を中心に釣行計画を立てることで、安定した釣果を狙いやすくなります。
ベイトの種類と釣れるレンジの関係
メバルは季節によって捕食するベイト(エサ)が変化し、それに応じて狙うべきレンジ(層)も大きく変わります。ベイトを理解することで、より効率的に釣果を伸ばすことができます。
春〜初夏は、海中に小魚(イワシ・キビナゴ・カタクチイワシ)やプランクトンが増える季節です。
この時期のメバルは表層〜中層を意識して泳いでおり、表層ただ巻きや表層ドリフトが特に有効です。
ピンテールワームなどナチュラルなシルエットを使うと、浮いたメバルを効率的に狙えます。
夏〜初秋は、水温上昇によりメバルが深場へ移動します。ベイトは主にゴカイ・エビ・カニなどの底生生物。このため、ボトム付近を意識したリフト&フォールやズル引きが有効です。
この時期は特に潮通しの良い岩礁帯や深場のテトラ帯が狙い目になります。
晩秋〜冬は、産卵期を控えたメバルがアミ・小型甲殻類を中心に捕食します。表層や中層をふわふわ漂うアミに反応するため、スローなただ巻きやドリフト釣法が効果的。
特に常夜灯周りでアミが舞うような状況では、軽量ジグヘッド+ピンテールワームが圧倒的に強いです。
つまり、ベイト=レンジのヒント。
「小魚・アミ・プランクトン→表層〜中層」「甲殻類→ボトム」と覚えておくことで、季節ごとに最適な攻め方を自然に組み立てられます。
月ごとに見るメバルの釣りやすさ|何月が1番釣れる?

メバルは一年を通して狙える魚ですが、月ごとに行動パターンが大きく変化します。
特に水温・日照・ベイトの変化によって釣れるレンジや活性が変わるため、季節ごとの特徴を理解しておくことが釣果アップの鍵です。
ここでは、月ごとのメバルの動きや釣れる条件を詳しく見ていきます。
12〜2月(冬)|大型が狙える産卵期
冬のメバルは産卵を中心に行動が変わる特別な時期です。
私のホームポイントでは、他の地域と比べるとやや早い時期に産卵が行われますが、11月末〜12月初旬に産卵前の荒食いが起こり、このタイミングで一気に活性が上がります。
しかし、そのピークを過ぎると活性が急激に落ち、しばらくは「かなり釣りにくい時期」が続きます。
そして、2月初旬〜2月中旬頃に産卵を終えたメバルが再び荒食いを始め、再度釣りやすくなる傾向があります。
このタイミングをうまく掴むと、他の季節では味わえない大型メバル(尺メバル)を狙えるチャンスです。
その年や地域によっては産卵時期に1ヶ月前後の差があり、沿岸水温や潮通しによって前後することもあります。
つまり、「産卵前の荒食い」と「産卵後の荒食い」の間が、年間を通して最も釣りが厳しいシーズンになります。
この時期はメバリングよりも餌釣りの方が安定しやすく、ルアーを使う場合でも、ガルプなどの匂い付き餌が強い味方になります。

3〜5月(春)|数・型ともに最盛期
春はメバル釣りの最盛期。
一年の中で最も数・サイズともに狙いやすく、初心者からベテランまで楽しめる時期です。
産卵を終えたメバルが体力を回復するために積極的にエサを追い、活性が非常に高くなるのが特徴です。
水温の上昇とともにメバルが浅場へ回遊してくるため、常夜灯周りや港内の明暗部が好ポイントになります。
夜間は表層付近でベイト(アミ・シラス・小魚)を捕食していることが多く、軽量ジグヘッド+ピンテールワームでの表層スローリトリーブが効果的です。
一方、日中は日陰やストラクチャー周辺の中層〜ボトムに潜む個体も多いため、スプリットショットリグやフロートリグを使って広く探るのもおすすめ。
この時期は、釣果も安定しやすくメバリングデビューにも最適な季節です。
また、潮通しの良い外向きエリアでは大型メバル(25〜30cm級)の釣果も期待できるため、ライトタックルでもドラグ調整を丁寧に行いましょう。
6〜8月(夏)|高水温期はポイントとタイミング勝負
夏はメバル釣りが最も難しくなる時期のひとつです。
水温が高くなることでメバルの活性が下がり、浅場にいる個体は減少します。
このため、水深のあるポイントや潮通しの良い場所を中心に狙うのが鉄則です。
日中は完全に深場へ落ちてしまうことが多く、ナイトゲームがメインになります。
特に風が弱く、ベタ凪の夜は警戒心が強くなるため、潮が動き出すタイミング(上げ始めや下げ始め)を狙うと効果的。
また、夜光虫が発生するような潮の時期は、メバルが浮きやすく表層でもヒットしやすくなります。
この時期は、ワームサイズを1.5インチ前後に落として小型ベイトを意識したセッティングが有効。
カラーはクリア系・ラメ系を中心に、ナチュラルな誘いを心がけるのがおすすめです。
夏のメバルは警戒心が高く、強いアクションには反応しづらいので、フォール主体や漂わせるような釣りで食わせるイメージを持ちましょう。
9〜11月(秋)|荒食いシーズンの前触れと復調期
秋はメバルが再び浅場に戻ってくる時期で、夏の低調期を抜けて釣果が復調していきます。
水温が下がり始める9月後半〜10月にかけて、少しずつメバルの活性が上がり、小型メバル中心の数釣りが出来ます。
11月には「荒食い」と呼ばれる爆釣シーズン前夜を迎え、サイズも期待出来るシーズンになってきます。
このタイミングでは、産卵に向けて体力をつけようとメバルが積極的にエサを追うため、表層〜中層の回遊個体が増加。
特に常夜灯周り・潮通しの良い堤防の角・小磯のシャローは有力ポイントになります。
ワームのサイズは1.5〜2インチ前後、重さは1〜1.5gのジグヘッドを基準に、レンジキープを意識したスローなただ巻きが効果的。
ベイトが多いタイミングではシャッドテールなど波動系ワームも強く、よりアクティブに誘えるのが秋の特徴です。
秋の終わり、11月後半〜12月初旬にかけては、地域によっては産卵前の荒食いが始まり、良型ラッシュが訪れます。
この時期を逃さず狙えば、シーズン通して最も数と型の両立が狙える絶好のタイミングです。
尺メバルを狙うならこの時期がベスト
尺メバル(30cm超え)を狙うなら、冬〜早春(2〜4月)が最もおすすめの時期です。
特に産卵後の荒喰い期は、メバルが体力を回復しようとして積極的にエサを追うため、数・型ともに狙いやすくなります。
私自身の釣行データでも、2月中旬〜3月中旬にかけて釣果が最も安定しており、尺メバルクラスの実績も集中しています。
この時期は大型個体が浅場に回遊してくるため、港内の常夜灯周り・テトラ帯・外向き堤防などが有力ポイントです。
一方で、海水温が下がりすぎると活性が落ちるため、水温が12〜13℃前後をキープしている時期を狙うのがコツ。
また、潮通しが良く、ベイトが溜まりやすいエリアを選ぶと、より高確率で尺メバルに出会えます。
また、狙うレンジによってルアーの使い分けも重要です。
表層を狙うならプラグがおすすめで、ベイトを追いかけて浮いている大型メバルにナチュラルにアプローチできます。
一方、深場に沈んでいる場合は、重めのジグヘッド+ワームでボトムを丁寧に探るのが効果的です。
バイトがあっても焦って合わせず、送り込むようにフッキングするのが尺メバル攻略のコツです。
地域による時期のずれと狙い方の違い
メバルは日本全国の沿岸に広く分布していますが、地域によって釣れる時期に1〜2ヶ月の差があります。
その理由は、水温や潮流、地形の違いによって、産卵や荒喰いのタイミングがズレるためです。
例えば、東北や北陸などの日本海側では水温が低いため、3〜5月頃がベストシーズンとなることが多く、春が最盛期。
一方で、瀬戸内海・九州・伊勢湾など西日本の沿岸部では、比較的水温が高いため、11月〜2月にかけてすでに荒喰いや産卵期を迎えます。
また、地域によって有効な釣法にも違いがあります。
潮通しが良い外海に面したエリアではプラグによる表層ゲームが有効なのに対し、
内湾や港湾部では軽量ジグヘッド+ワームでのスローアプローチが安定して釣果を出せます。
実際に私も、地域差を意識してシーズン序盤は南のエリア、終盤は北方面へ遠征するようにしています。
水温の高い地域から順にシーズンが始まり、北上するにつれて終盤戦へと移っていくため、季節を追って釣りを楽しむことができるのもメバル釣りの魅力です。
地域ごとの水温傾向や潮回りを把握し、産卵や荒喰いのタイミングに合わせて狙うことで、釣果を大きく伸ばすことが可能です。
時間帯と潮回りで変わる釣果の差

メバル釣りでは、季節だけでなく時間帯と潮回りによっても釣果が大きく変わります。
同じ場所でも、「いつ釣るか」で反応がまったく違うことも珍しくありません。
特にメバルは夜行性であるため、時間帯の選び方が最も重要なポイントになります。
また、潮の流れや干満差も釣果に直結します。
潮が動くタイミングでは活性が上がり、逆に潮止まりでは口を使わないことも多いです。
ここでは、時間帯ごとの特徴と潮回りの関係を解説します。
ナイトゲームが有利な理由
メバルは夜行性の魚で、昼間は岩陰やテトラの隙間などに潜んでいて、夜になると表層付近まで浮き上がり、プランクトンや小魚を捕食します。
そのため、夜釣り(ナイトゲーム)が圧倒的に釣りやすいです。
常夜灯周りなどの明暗の境目は、エサとなる小魚やプランクトンが集まりやすく、メバルが最も活発に捕食するポイント。
特に日没後1〜2時間、もしくは深夜の潮が動くタイミングが好機です。
メバリングでは、常夜灯周辺の表層をスローリトリーブで引いてくると反応が出やすく、
逆に暗い場所ではジグヘッド+ワームで中層〜ボトムを意識して探るのがおすすめです。
また、餌釣りの場合は、ゴカイ・イソメ系の匂いのある餌が夜間でも強くアピールし、安定して釣果を出しやすいです。
メバル釣りは夜が基本、と覚えておくと間違いありません。
朝夕マヅメの狙い方と釣れるタイミング
夜に次いで釣りやすい時間帯が朝マヅメ・夕マヅメです。
夜明け前後や日没前後は、光量が変化することでメバルの警戒心が一時的に緩み、活性が上がる時間帯です。
特に夕マヅメは、夜に備えて捕食行動が活発になるため、一日の中でも釣果が集中するタイミング。
常夜灯が点き始める頃から反応が出始め、完全に暗くなる直前にピークを迎えることが多いです。
一方、朝マヅメは短時間勝負。
夜の間に表層で捕食していたメバルが、明るくなるにつれて深場へ戻るため、夜明け直前〜30分後が最もチャンスです。
この時間帯は風が弱く潮も落ち着いていることが多いため、軽めのジグヘッド+ピンテールワームでナチュラルに誘うのがおすすめです。
また、どちらの時間帯も潮の動きが重なるとより効果的です。
マヅメ+上げ潮・下げ潮が動くタイミングを狙うことで、魚の活性が一気に高まり、短時間でも爆釣することがあります。
潮の動きとメバルの活性の関係
一般的に魚は潮が動けば動くほど活性が上がるため、中潮や大潮が「釣れる潮」として知られています。
これはメバルにも基本的には当てはまりますが、実は他の魚種とは少し違った特徴を持っています。
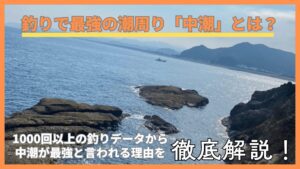
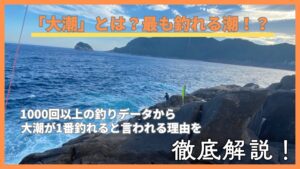
メバル釣りでは昔から「凪(なぎ)を狙え」という言葉があるように、潮が動かない日でも安定して釣れることが多いです。
特に長潮や小潮のように潮の動きが緩い日でも、他の魚に比べて釣果が落ちにくく、むしろ静かな状況の方が口を使いやすい個体もいます。
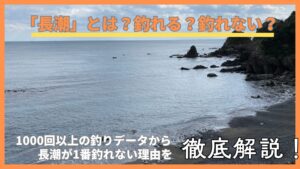
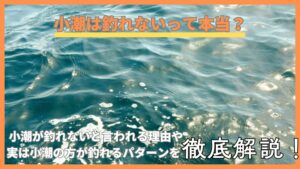
また、エサ釣りの場合は潮が動かない時間帯でも匂いが広がりやすいため、長潮や小潮で釣果が上がるケースもあります。
この点はルアー釣り(メバリング)と異なる魅力といえるでしょう。
一方で、潮が動きすぎると小型のメバルは流れの弱い場所へ避難する傾向があります。
その反面、大型メバルは遊泳力が高く、潮が動いている時ほど活発にエサを追うため、良型を狙うなら潮の効いているタイミングを意識するのがおすすめです。
季節ごとのポイント選びと地形の見方

メバルは季節によって付き場(居場所)が大きく変化します。
同じエリアでも「どの地形を狙うか」で釣果がまったく違ってくるため、地形や潮通しの特徴を理解することが重要です。
ここでは季節ごとの代表的なポイントや狙い方のコツを紹介します。
堤防・テトラ・磯など地形別の狙い方
メバルは「障害物(ストラクチャー)」を好む魚で、堤防・テトラ・磯・岩礁帯など、身を隠せる場所を中心に生息しています。
そのため、地形を意識してポイントを選ぶだけで釣果が大きく変わります。
堤防では、常夜灯周りや角、スロープの際など、潮通しが良く変化のある場所を狙うのが基本です。
夜は常夜灯周辺にプランクトンが集まり、それを追う小魚やメバルが集まるため、ナイトゲームの定番ポイントといえます。
ただし、メバルは警戒心が強い魚なので、常夜灯の明暗の境あたりを狙った方が釣果が上がりやすいです。
テトラ帯はメバルの隠れ家そのもので、昼夜問わず人気のポイント。
特にテトラの隙間にワームを落とし込む釣り方が効果的です。
ただし足場が悪いので、安全対策(スパイクシューズやライフジャケット)は必須です。
磯場は大型メバル(尺メバル)を狙うのに最も適したポイント。
潮通しがよく、餌となるベイトも豊富なため、活性の高い良型個体が集まりやすいです。
風裏になる場所や潮の当たるサラシの横など、「流れと障害物の境目」を意識すると良い釣果に繋がります。
季節が進むにつれてメバルは深場へと移動しますが、春や秋の高活性期は浅場の地形変化を意識した釣りが効果的です。
潮通しと水深で決まる好ポイント
メバルは潮通しが良く、かつ水深に変化がある場所を好みます。
理由はシンプルで、潮が通る=ベイトが運ばれるため、食事のチャンスが多いからです。
特におすすめなのは、以下のようなポイントです。
- 堤防の先端や角:潮の流れがぶつかる場所で、常に新しいベイトが流れ込みやすい。
- 岬や地磯の張り出し部:潮が当たりやすく、ベイトが溜まるため大型メバルの実績が高い。
- 落ち込みやブレイクライン:水深の変化がある場所はメバルの待ち伏せポイントになりやすい。
ただし、潮が速すぎるエリアは、メバルの遊泳力を超えてしまうため避けるのが無難です。
活性が低い時期ほど、流れが緩やかなエリアや反転流のある場所を意識するのが効果的です。
また、潮通しが良くて水深がある堤防は、季節を問わず安定した釣果が出やすい鉄板ポイントです。
私自身も迷った時はまずこうしたポイントから攻めるようにしています。
初心者でも探しやすい場所の特徴
メバルは障害物の近くや潮の流れが緩いエリアを好む魚ですが、初心者でも狙いやすいポイントはいくつかあります。
釣果を安定させるためには、「安全で足場が良く、メバルの着きやすい条件」を意識することが大切です。
- 常夜灯のある港内:夜になるとプランクトンが集まり、それを追ってメバルが寄ってくる。明暗の境目を狙うのが鉄板。
- スロープや堤防の際:水深が浅くても地形変化があり、メバルが身を寄せやすい。ワームを底すれすれに通すと高確率で反応。
- テトラの外側・内側:外側は良型狙い、内側は数釣りに向いている。安全な足場を選び、落とし込みや際狙いが効果的。
私自身もメバリングを始めた頃は、こうした常夜灯周り+スロープ+潮通しの良い港を中心に狙っていました。
この条件を満たす場所なら、初めてでも釣果を出しやすいです。
初心者でも探しやすい場所の特徴
メバルは障害物の近くや潮の流れが緩いエリアを好む魚ですが、初心者でも狙いやすいポイントはいくつかあります。
釣果を安定させるためには、「安全で足場が良く、メバルの着きやすい条件」を意識することが大切です。
- 常夜灯のある港内:夜になるとプランクトンが集まり、それを追ってメバルが寄ってくる。明暗の境目を狙うのが鉄板。
- スロープや堤防の際:水深が浅くても地形変化があり、メバルが身を寄せやすい。ワームを底すれすれに通すと高確率で反応。
- テトラの外側・内側:外側は良型狙い、内側は数釣りに向いている。安全な足場を選び、落とし込みや際狙いが効果的。
私自身もメバリングを始めた頃は、こうした常夜灯周り+スロープ+潮通しの良い港を中心に狙っていました。
この条件を満たす場所なら、初めてでも釣果を出しやすいです。
メバルの季節(時期)別の釣り方まとめ

メバル釣りは季節によって狙うレンジやアクション、使うルアーが大きく変わります。
ここでは季節ごとの特徴に合わせた基本的な釣り方をまとめました。
年間を通して狙える魚ですが、季節に合ったアプローチを取ることで、釣果が安定しやすくなります。
冬〜春はスローに誘って確実に
冬〜春は水温が下がることでメバルの活性が低くなり、積極的にベイトを追わなくなる時期です。
そのため、手返しの早いルアーゲームよりもエサ釣りの方が有利になることが多いです。
ただし、ルアーを使う場合でも工夫次第でしっかり釣ることができます。
この時期に特におすすめなのが、ガルプ ベビーサーディンなどの“匂い付きワーム”。
匂いによる集魚効果が高く、活性の低いメバルでも思わず口を使ってくれます。
アクションはスローに誘うのがポイント。
ジグヘッドを~1gの軽めにして、表層〜中層を「ゆっくり巻いて止める」を繰り返すと反応が出やすいです。
スローで丁寧に探ることが、低水温期のメバリングで釣果を伸ばす最大のコツです。

春〜初夏は表層ゲームで数釣り
春〜初夏にかけては、水温が上がり始めてメバルの活性が一気に上がるタイミングです。
この時期のメバルはベイトを積極的に追うようになり、表層を意識した「数釣りシーズン」に突入します。
おすすめは軽量ジグヘッド+ピンテールワームでの表層スイム。
リールをゆっくり巻きながらレンジをキープする「ただ巻き」が最も効果的です。
特に「メバル弾丸」のような弾丸型のジグヘッドは、浮き上がりづらくスローに誘う事が出来るのでおすすめです。
ベイトが小魚(シラスやカタクチ)中心の時は、ワームのサイズを1.5〜2インチにすると反応が良くなります。
また、ナイトゲームでは常夜灯下の明暗部を狙うのが定番。
群れが入っていると入れ食いになることも多く、初心者でも釣果が出しやすい時期です。
私自身、年間で最も数を釣るのがこの春のメバリング。
ルアー選びやアクションよりも群れを見つけることが鍵になります。
夏〜秋は深場と明暗を意識した攻め方
夏〜秋は水温が高くなりすぎるため、メバルは表層から離れて深場へ移動する傾向があります。
特に昼間は岩陰やストラクチャーの奥に隠れてしまうことが多く、夜間や朝夕のマヅメが狙い目になります。
この時期のキーワードは「深場」と「明暗」。
堤防の先端や潮通しの良いポイント、常夜灯の下やその外側の暗いエリアが好ポイントです。
重めのジグヘッド(1.5〜3g)+ワームを使い、ストラクチャーを中心に丁寧に探るのが有効です。
さらに、少し重めでダートさせるボトムワインドも非常に有効。
底付近を軽くトゥイッチしながらルアーを左右に跳ねさせることで、リアクションバイトを狙うことができます。
特におすすめなのがデコイ「デルタマジック」。
矢じり型のヘッド形状でキレのあるダートを生み出し、夏の低活性時でも反応を引き出せます。
また、潮が動かないときは餌釣りも強いシーズン。
虫餌やエビ餌を使うと、深場に潜んでいる個体も反応しやすくなります。
夏〜秋はサイズこそ小さめですが、パターンを掴めば安定して釣れる時期でもあります。
私の場合、夏場は日中の釣行を避け、夜間に潮が動く時間帯だけを狙うようにしています。
暑さ対策にもなり、釣果も安定しやすいおすすめのスタイルです。
まとめ|メバル釣りを楽しむための時期選びのコツ
メバル釣りは、年間を通して楽しめるライトゲームの代表格ですが、もっとも安定して釣れるのは晩秋〜春にかけてです。
この時期は水温やベイトがメバルの行動パターンにマッチし、初心者でも釣果を出しやすい最高のシーズンとなります。
ただし、冬は産卵の前後で大きく状況が変わるため、産卵前・産卵後の「荒食い」タイミングを狙うことがポイント。
春は表層ゲームで数釣りが楽しめ、夏〜秋は深場や明暗部を意識することで安定した釣果を狙えます。
また、メバリングとエサ釣りを季節で使い分けることで釣果が安定します。
活性が高い春や秋はルアー中心、活性が低い冬や夏はエサ釣りや匂い付きワーム(ガルプシリーズなど)を使うのがおすすめです。
最後にもう一つ大切なのは、地域ごとの時期差を理解すること。
私の経験上、南の地域はシーズンが早く始まり、北の地域ほど遅くまで楽しめます。
実際に私も、シーズン序盤は南方面へ、終盤は北方面へ遠征して安定した釣果を出しています。
メバルは小型でも引きが強く、見た目もかわいい魚。
他の魚が釣れない時期でも成立する最高のターゲットです。
時期とパターンを掴めば、誰でも一年中楽しめるライトゲームになります。









コメント