釣りにおいて「ルアーの沈下速度(フォールスピード)」は、釣果を左右する重要な要素です。
メタルジグ、エギ、ジグヘッドなど、どのタイプのルアーを使うにしても、沈み方の違いは魚の反応に直結します。
この記事では、沈下速度が決まる物理的な仕組みや、実釣における目安の出し方を解説しています。
今すぐルアーごとの沈下速度の目安を知りたい方は、下記の自動計算ツールをご利用下さい。
簡単に調べたい?【沈下速度自動計算ツール】
ここまでの理論や体感を元に、手軽に使えるようにと考案したのが、
👉 **「ルアー沈下速度 自動計算ツール」**です。
ルアーの重さや水深を選ぶだけで、おおよそのフォールスピードを自動で算出してくれるので、現場での判断に役立つ目安としてぜひ活用してみてください。
🔹 メタルジグ沈下速度自動計算ツール【ショアジギング】
▶ メタルジグのフォールスピードを計算したい方は、メタルジグ沈下速度自動計算ツールをどうぞ。
🔹 エギ沈下速度自動計算ツール【エギング】
▶ エギのフォールスピードを計算したい方は、エギ沈下速度自動計算ツールをどうぞ。
🔹 ジグヘッド沈下速度自動計算ツール【アジング】
▶ メタルジグのフォールスピードを計算したい方は、ジグヘッド沈下速度自動計算ツールをどうぞ。
沈下速度の考え方(物理的な観点)

ジグやルアーの沈下速度を正確に求めるには、物理学の「流体力学」に基づいた計算が必要です。
水中で物体が落ちるスピードは、**重力(引力)と水の抵抗力(抗力)**とのバランスによって決まります。
理論的な沈下速度の式
終端速度(V)= √((2 × m × g) ÷ (ρ × Cd × A))
- m:物体の質量(kg)
- g:重力加速度(9.8 m/s²)
- ρ:水の密度(約1000 kg/m³)
- Cd:抗力係数(ルアーの形状により異なる。1.0〜1.3が目安)
- A:投影面積(m²)= 正面から見たときの面積
この式は空気中の「終端速度」を応用したもので、ルアーが一定速度で落下すると仮定しています。実際には、水中で徐々に加速し、ある程度の速度で安定するため、この式で得られる値はあくまで理論上の目安と考えましょう。
現実的な問題点と計算の難しさ
物理式が使えるといっても、実際の釣りにおいてこの式をそのまま活用するのは困難です。理由は以下の通り:
- **Cd(抗力係数)やA(面積)**をルアーごとに正確に測るのはほぼ不可能
- 潮の流れ、風、ラインの影響など、外的要因が沈下速度を大きく変える
- ルアーの姿勢(水平か垂直か)や回転によって水の抵抗も変化する
そのため、釣りの現場では「おおよその経験値から沈下速度を予測」するのが一般的です。
実釣時の沈下速度の把握方法
実際の釣りでは、「フォールスピード目安表」や「カウントダウン方式」など、感覚に頼った方法が活用されます。
筆者の実例:
私自身も釣り歴15年以上の中で、沈下速度は常に意識してきました。
たとえば水深10mのポイントでメタルジグを投入し、着底までに5秒かかった場合、「1秒あたり約2m沈んだ」と判断します。
このように逆算して、その日の潮の影響やジグの沈み方のクセを把握するようにしています。
この体感を重ねていくことで、
- 今のジグは沈むのが遅い?
- 潮に押されて流されてる?
といった状況判断がしやすくなり、釣果にもつながるわけです。
各ルアーごとの沈下速度の違い
メタルジグの場合(ショアジギング)
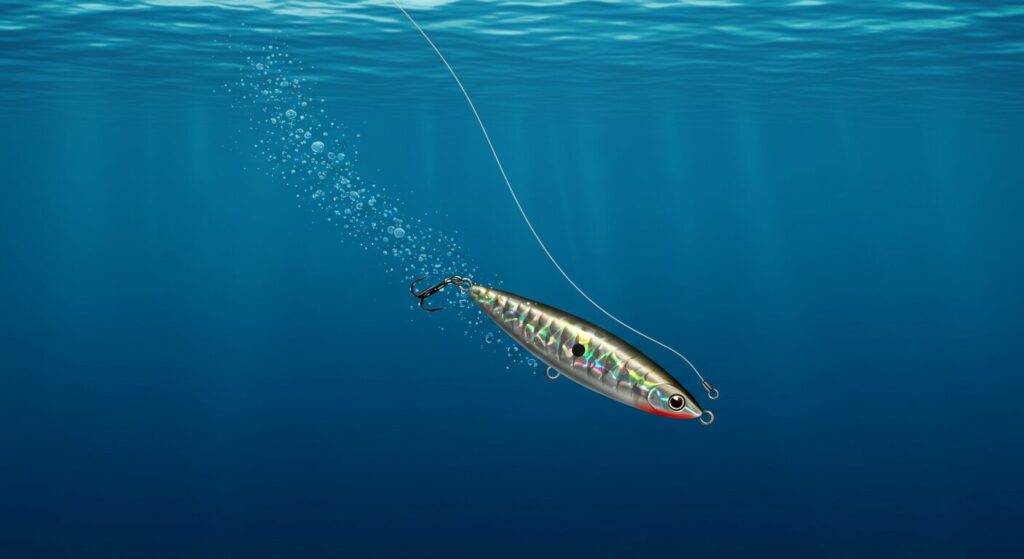
メタルジグは一般的に重さに対して沈下速度が速く、特にタングステン製のジグは非常に高比重であるため、同じ重量でもフォールスピードが速くなります。
これは、タングステンの密度が鉛やその他の金属よりも高く、水中での抵抗を抑えながらスムーズに沈むことができるためです。
一般的なルアーの中で最もフォールスピードが早い為、早い動きを好む青物を狙うのにはメタルジグが最適と言われている訳です。
また、ジグの重心バランスによっても沈下速度に差が出ます。
たとえば、センターバランスのジグは水平に近い姿勢でフォールしやすく、水の抵抗を適度に受けながら沈みます。
一方、リアバランスのジグは後方に重心があるため、より直線的に速く沈下しやすいという特徴があります。
形状も重要な要素です。
スリムなシルエットのジグは水の抵抗が少なく、速く沈みやすいのに対して、幅広でフラットなジグは受ける水の抵抗が大きいため、ゆっくりとした沈下になります。これにより、魚にアピールするフォールアクションの選択肢も広がります。
具体的には、同じ40gのジグでも、スリムタイプやタングステン製のものは1秒で約1.5〜2m沈むのに対し、幅広でフラットな鉛製のジグでは、1秒で1.0〜1.3m程度になることがあります。
つまり、ジグの選び方一つで沈下スピードと釣りのテンポが大きく変化します。
釣りのスタイルや狙う魚種、水深、潮流の強さなどによって適切なジグを使い分けることで、効率良く釣果を伸ばすことが可能になります。
エギの場合(エギング)

一般的な目安で言うと「3.5号=約3秒で1m」と言われていますが
エギは重さと沈下速度の関係が比例しづらい傾向にあります。
「10gだから沈下速度は**秒」と言う簡単な計算は出来ません。
何故かと言うと、エギは製品ごとのそもそもの構造が違う事が多い為です。
主に以下の3つの種類に分けられます。
- ノーマル用:1m/3秒程度
- シャロー用:1m/6秒程度
- ディープ用:1m/2秒程度
これらは「浮力のあるボディ」や「沈み方を調整するための構造」が施されており、単純な重さだけで沈下速度が決まるわけではないからです。
その為、製品ごとに沈下速度が明記されていることが多く、記載されている場合はそれを参考にするのが1番良いでしょう。
さらに、潮流やラインの太さ、シャクリの姿勢によっても実際の沈下速度は大きく変わるため、状況に応じた選択と調整が必要です。
軽量ジグヘッドの場合(アジング)

アジング等で使われる0.8g〜1.5gのジグヘッドは非常に軽量で、沈下速度が遅いため、レンジキープに向いています。
軽量のルアーで沈下速度を考える上で、1g以下の軽量ジグヘッドを深場で使用する際には注意が必要です。
水深が深くなるにつれて、水の抵抗・潮流・風などの影響が大きくなり、ジグヘッドが沈みにくくなります。
例えば、1gのジグヘッドを1m沈めるのに5カウントだとして、単純に2m沈むには2倍の10カウントというわけではなく、3倍以上のカウントが必要になることが多いです。
水深4mではさらに多くのカウントが必要になることもあります。
これは、水の抵抗力(抗力)が速度の2乗に比例して増加するため、沈むにつれて抵抗が増し、加速度的に沈みづらくなるためです。
さらに、軽量ジグヘッドは空気抵抗や潮の影響も大きく受けやすく、沈下速度は深くなるほど鈍化する傾向にあります。
どうしても深場を狙いたい場合は、タングステン製のジグヘッドや、空気抵抗を減らしたラウンド型を使用すると、比較的スムーズに沈めやすくなります。
また、ジグヘッドだけでなく、ワームの形状も沈下速度に大きく影響します。
小さめで抵抗の少ないワームは沈みやすく、大きめのワームやリブが多いワームは水の抵抗を受けて沈みにくくなります。
このように、軽量ジグヘッドは環境やリグの条件によって沈み方が大きく変化するため、都度状況を見て判断することが重要です。
ルアーの沈下速度に関してのまとめ
この記事では、ジグ・エギ・ジグヘッドといった主要なルアーの沈下速度について、物理的な仕組みと実釣での考え方を詳しく解説しました。
沈下速度は単純に「重さが重いほど速い」とは言い切れず、ルアーの形状や姿勢、水中での抵抗、潮流や風、さらには装着するワームによっても大きく変化します。
たとえば、同じ40gのジグでも形状によって1秒あたりのフォールスピードは大きく異なりますし、軽量なジグヘッドは水深が深くなるにつれて沈みにくくなる傾向があります。また、エギにおいては製品ごとに異なる沈下速度モデルが存在し、選び方一つで釣果に影響する場面も少なくありません。
つまり、沈下速度を「感覚」ではなく「目安」として把握することが、釣果アップへの第一歩です。
そんなときに便利なのが、実際のルアー条件からおおよその沈下速度を自動で計算できる便利ツールです。
↓こちらから沈下速度をチェックできます↓
▶ エギのフォールスピードを計算したい方は、エギ沈下速度自動計算ツールをどうぞ。
▶ メタルジグのフォールスピードを計算したい方は、メタルジグ沈下速度自動計算ツールをどうぞ。
▶ 軽量ジグヘッドのフォールスピードを計算したい方は、ジグヘッド沈下速度自動計算ツールをどうぞ。
フィールドでの実釣感覚と、こうした数値的な根拠を組み合わせて、より精度の高いアプローチを目指してみてください。

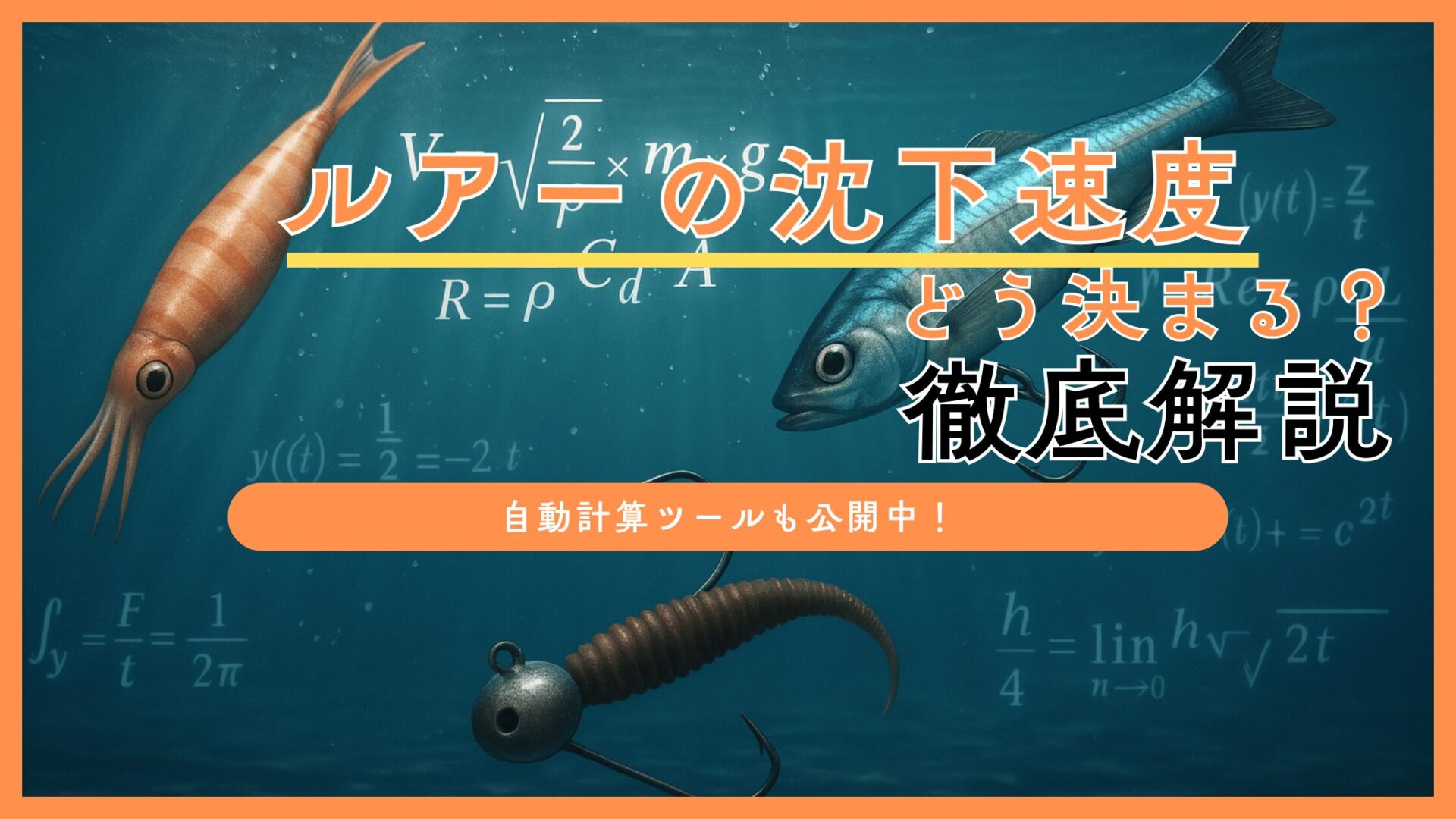
コメント