ヒラメといえば高級魚として知られ、刺身や煮付けなどさまざまな料理で楽しまれていますが、意外と知られていないのが「肝(きも)」の存在です。
「ヒラメの肝って食べられるの?」「寄生虫とか危なくない?」「どんな味?」と気になる方も多いのではないでしょうか。
結論から言うと、ヒラメの肝は正しく処理すれば非常に美味しく食べられます。
ただし、鮮度管理や寄生虫リスク、下処理の手順を知らずに生で食べるのは危険です。
本記事では、ヒラメの肝は本当に食べていいのか?という疑問にお答えしつつ、味の特徴・下処理方法・おすすめの食べ方・安全な楽しみ方まで丁寧に解説していきます。
釣ったヒラメを余すことなく楽しみたい方も、飲食店での提供例が気になる方も、ぜひ参考にしてみてください。
ヒラメの肝は食べられる?|基本情報と注意点

まずは気になる「ヒラメの肝はそもそも食べても大丈夫なのか?」という疑問から確認していきましょう。
ヒラメの肝は、釣り人だからこそ味わえる“隠れたごちそう”のひとつ。
市場にはほとんど流通せず、飲食店でもまずお目にかかれないため、自分で釣ったときにだけ楽しめる特別な部位ともいえます。
ただし、内臓である以上、鮮度管理や寄生虫リスクへの正しい理解と対処が必要です。
「そもそもヒラメの肝は安全に食べられるのか?」という基本情報と、注意点について詳しく解説していきます。
ヒラメの肝は可食部?刺身で食べる人もいる
ヒラメの肝(肝臓)は、下処理を正しく行えば食べることができます。
特に釣り人の間では、刺身に添える「肝醤油」や「肝和え」にして楽しむ方も多く、珍味として人気のある部位です。
ただし、一般的なスーパーではヒラメの肝が販売されることはほとんどなく、釣った個体や丸ごと購入した場合のみ楽しめる希少な部位と言えるでしょう。
注意すべき寄生虫リスクと鮮度管理
ヒラメの肝を食べる際に特に注意したいのが、寄生虫のリスクと鮮度の低下です。
ヒラメはアニサキスやクドアといった寄生虫が検出されることがあり、内臓(特に肝)にはリスクが潜んでいる可能性があります。
厚生労働省によると、-20℃以下で24時間以上の冷凍処理、もしくは60℃以上の加熱(1分以上)で寄生虫は死滅するとされています。 参考:厚生労働省HP
そのため、釣ったばかりの新鮮なヒラメであっても、生食するなら冷凍処理を推奨します。
また、肝は非常にデリケートな部位のため、時間が経つとすぐに風味が落ちてしまうのも特徴です。
捌いた後はすぐに血抜き・下処理をして、冷蔵または冷凍保存することが、美味しく安全に食べるための基本となります。
ヒラメの肝の味は?|カワハギと比較される理由

ヒラメの肝は食べられると知っていても、「実際どんな味がするの?」と気になる方は多いと思います。
一般にはあまり出回らない部位ですし、家庭でヒラメを捌いた経験がないと、なかなか味の想像がつかないかもしれません。
ここでは、私自身が実際に釣ったヒラメの肝を調理して食べたときの感想と、それを一緒に食べた家族の反応をご紹介します。
あわせて、よく比較されるカワハギの肝との違いについても触れていきますので、食べてみたい方の参考になれば幸いです。
濃厚さとあっさりさのバランスが魅力
私が最初にヒラメの肝を食べたのは、真冬の釣行で釣れた50cmオーバーの個体を持ち帰って捌いたときでした。
肝は意外にも大きく、色もきれいなベージュ色。
下処理を丁寧にして、湯引きしてからポン酢と刻みネギで和えていただきました。
ひと口食べてみると…驚くほどなめらかでクリーミー。
ただ、カワハギの肝に比べてクセや苦味がなく、ふんわりとした甘みとあっさり感が際立っていました。
私は濃厚すぎる肝はあまり得意ではないのですが、ヒラメの肝は何口でも食べたくなるちょうどいいコクで、まさに日本酒と合わせたくなる上品な味わいでした。
私と家族の感想|初めてのヒラメ肝に驚きの声も
ヒラメの肝を初めて食べたのは、今までで釣った中で1番大きい78cmの座布団サイズのヒラメを釣り上げた日でした。
せっかくだからと、肝も捨てずにきちんと下処理してみることに。
軽く湯引きしてポン酢と合わせ、試しに小皿に盛って食卓に出しました。
正直なところ、最初はあまり期待していなかったのですが──ひと口食べてびっくり。
クセがなく、ふんわりとした甘みととろけるような舌ざわりが広がり、思わず「うまっ」と声が出ました。
その様子を見ていた妻も「ちょっとだけ…」と味見。
普段レバーや肝類が苦手な妻が、「これ、全然くさみがない。むしろ旨味があって食べやすい」とおかわりを要求するほどでした。
少しポン酢を強めにしたことで、さっぱりした後味と肝のコクがちょうど良いバランスだったようです。
それ以来、我が家ではヒラメを釣ってきた日は肝も調理して食べるのが定番になりました。
全体としては、濃厚すぎず、上品な旨味を持った肝という印象で、カワハギのようなパンチはないものの、刺身と合わせると最高の“脇役”になると感じました。
「釣ったときにしか食べられない味」という特別感もあり、家族で楽しめたいい経験になりました。
カワハギの肝との違い
魚の肝といえば、1番有名でよく食べられているのはカワハギの肝だと思います。
カワハギの肝と食べ比べての私の感想は
私の感覚ではヒラメの肝はカワハギよりもライトで上品な印象です。
カワハギの肝は一口でも「濃厚!」と感じるパンチがありますが、ヒラメの肝はさらりとした中にふわっと香るようなコクがあり、むしろ料理の邪魔をせず素材を引き立てる存在だと感じました。
刺身と合わせる場合も、ヒラメの肝醤油は全体を引き締めてくれるような役割で、飽きのこないバランスの良さが光ります。
ヒラメの肝を美味しく食べる下処理のコツ

ヒラメの肝は、丁寧な下処理さえすればとても美味しく食べられます。
逆に言えば、処理を怠ると臭みが出たり、食中毒リスクにつながることも。
特に「肝=内臓」なので、鮮度管理・血抜き・胆嚢処理が味と安全性のカギを握ります。
家庭でも実践できるヒラメ肝の下処理の手順とポイントをわかりやすく解説します。
胆嚢を傷つけずに除去する方法
ヒラメの肝には胆嚢(たんのう)と呼ばれる袋状の器官がついており、これを破ってしまうと苦味が全体に広がってしまいます。
胆嚢は肝の中央や根元部分にぴったりと付着している緑色の小袋で、注意深く取り除く必要があります。
- ①肝をまな板に置き、裏返して胆嚢の位置を確認
- ②指やピンセットなどでそっとつまんで引き離す
- ③肝を切り分ける際も、包丁が胆嚢に触れないように注意
もし破ってしまった場合、私は食べないようにしていますが、どうしても食べたい方は流水で丁寧に洗ってから加熱用に回すと安心です。
血抜きと臭み取りのやり方
ヒラメの肝には細かな血管が多く通っており、そのまま調理すると血の臭みやえぐみが残ることがあります。
そのため、加熱・生食を問わず、血抜きは必須です。
おすすめの血抜き手順は以下の通りです:
- 竹串や爪楊枝などを使って血管部分を軽く押し出す
- 流水でやさしく洗いながら、表面や隙間の血を除去
- 臭みが気になる場合は、酒に10〜15分ほど浸してから拭き取ると◎
最後にキッチンペーパーで水気をしっかり取ることで、臭みのない仕上がりになります。
私は面倒なのでこの手順で行ってますが、余裕がある方は流水ではなく、氷水に塩を入れてそこで血の部分を取り除いていくのがオススメです。
血の処理を丁寧にするかどうかで、味の印象は大きく変わるので、ぜひひと手間かけてみてください。
ヒラメの肝のおすすめの食べ方|刺身・肝和え・湯引

ヒラメの肝は、下処理をしっかり行えば刺身と合わせても美味しく、火を通せばさらにコクが引き立つ万能な部位です。
ここでは、私自身が実際に試してよかった食べ方や、釣り仲間から教わったレシピなどをご紹介します。
どれも特別な道具や調味料は不要で、家庭でも気軽に挑戦できますので、釣ったヒラメを余すことなく楽しみたい方はぜひ参考にしてみてください。
※ヒラメの肝を生食する際には寄生虫などのリスクが伴います。
生で食べる場合は釣ってすぐの個体を適切に冷却保存し、内臓を早めに除去した上で、十分に下処理・冷凍などの対策を行ってください。
安全に楽しむためにも、生食はあくまで自己責任でお願いします。
肝醤油で刺身を楽しむ方法
もっとも手軽で美味しいのが、ヒラメの刺身を肝醤油で食べる方法です。
湯引きして裏ごしした肝を、濃口醤油やポン酢と合わせてタレにすると、まろやかで奥深い風味が加わり、刺身がまるで別物のような味わいになります。
私はよく、ヒラメの刺身を少し厚めに切り、肝醤油を小皿に少量垂らして薬味代わりにして楽しみます。
わさびとはまた違った「とろみのあるコク」が加わって、驚くほど旨味が増しますよ。
特に脂の乗ったエンガワとの相性は最高で、酒の肴に最高です。
湯引きしてポン酢と和えるレシピ
もうひとつの定番が、湯引きして冷水に取った肝を、ポン酢+薬味で和えるシンプルな一品です。
特に湯引き後の肝は、とろけるような食感と甘みが際立ち、少し酢をきかせることで後味もさっぱり。
お好みで細ねぎ、刻み大葉、おろし生姜などを加えると、酒の肴としても最高の仕上がりになります。
晩酌の一品として、小皿で出すととても喜ばれます。
肝を使った鍋・吸い物など調理バリエーション
寒い季節には、ヒラメのアラや肝を使った潮汁や鍋もおすすめです。
骨付きの肝や、形が崩れた部分などは、加熱調理に向いています。
鍋に少量加えるとスープに深いコクが出て、全体の味がまろやかになります。
私もたまに味噌ベースの鍋に少しだけ肝を溶かして使いますが、濃厚すぎずほんのりとした風味が味に奥行きを与えてくれます。
まとめ:ヒラメの肝は食べられる!

ヒラメの肝は、市場や飲食店で出会えることがほとんどない、非常に希少な食材です。
その理由は、内臓という特性上鮮度管理が難しく、流通や飲食提供のハードルが高いため。
特に肝の状態まで良質なヒラメは限られており、安定供給ができません。
唯一と言っていいほど確実にヒラメの肝を味わえる方法は、自分で釣って持ち帰ること。
釣ったその場で内臓を処理し、しっかりと冷やして持ち帰れば、自宅で新鮮なヒラメの肝を楽しむことができます。
一部の高級店や地元の寿司屋では、釣り人が持ち込んだヒラメを調理してくれる場合もありますが、肝まで出してくれるケースはかなりレア。
その意味で、ヒラメの肝は釣り人だけに許された贅沢な味わいだといえるでしょう。
ヒラメの肝は、下処理次第で絶品になる
本記事では、ヒラメの肝は食べられるのか?という疑問から、味の特徴、正しい下処理の方法、家庭での調理法までを詳しく解説してきました。
肝と聞くとクセが強そうなイメージを持つ方も多いかもしれませんが、ヒラメの肝は意外にも上品でまろやか。
丁寧に血抜きし、胆嚢を取り除いた肝はポン酢や醤油と相性抜群で、酒の肴としても優秀です。
生食にはリスクあり。必ず自己責任で
ただし、ヒラメの肝を生食する場合には寄生虫(アニサキス・クドアなど)のリスクがあることを忘れてはいけません。
食中毒を防ぐためにも、釣った直後に内臓を処理し、冷却保存・冷凍処理などを行うのが基本です。
厚生労働省の指針でも、-20℃で24時間以上の冷凍や、中心部を60℃以上で1分以上加熱することが推奨されています。
以下のページを情報参照元としてご確認ください。
▶️ 厚生労働省|アニサキスに関する注意喚起
釣ったときこそ楽しめる、特別なひと皿
ヒラメの肝は、スーパーにも料亭にもなかなか出てこない、まさに釣り人の特権とも言える部位です。
自分で釣った魚だからこそ、より丁寧に扱いたくなる。そんな「一尾まるごとのありがたさ」を実感させてくれる存在です。
ぜひ一度、ヒラメを釣った際は肝まで味わってみてください。
正しく処理すれば、きっと忘れられない一品になります。



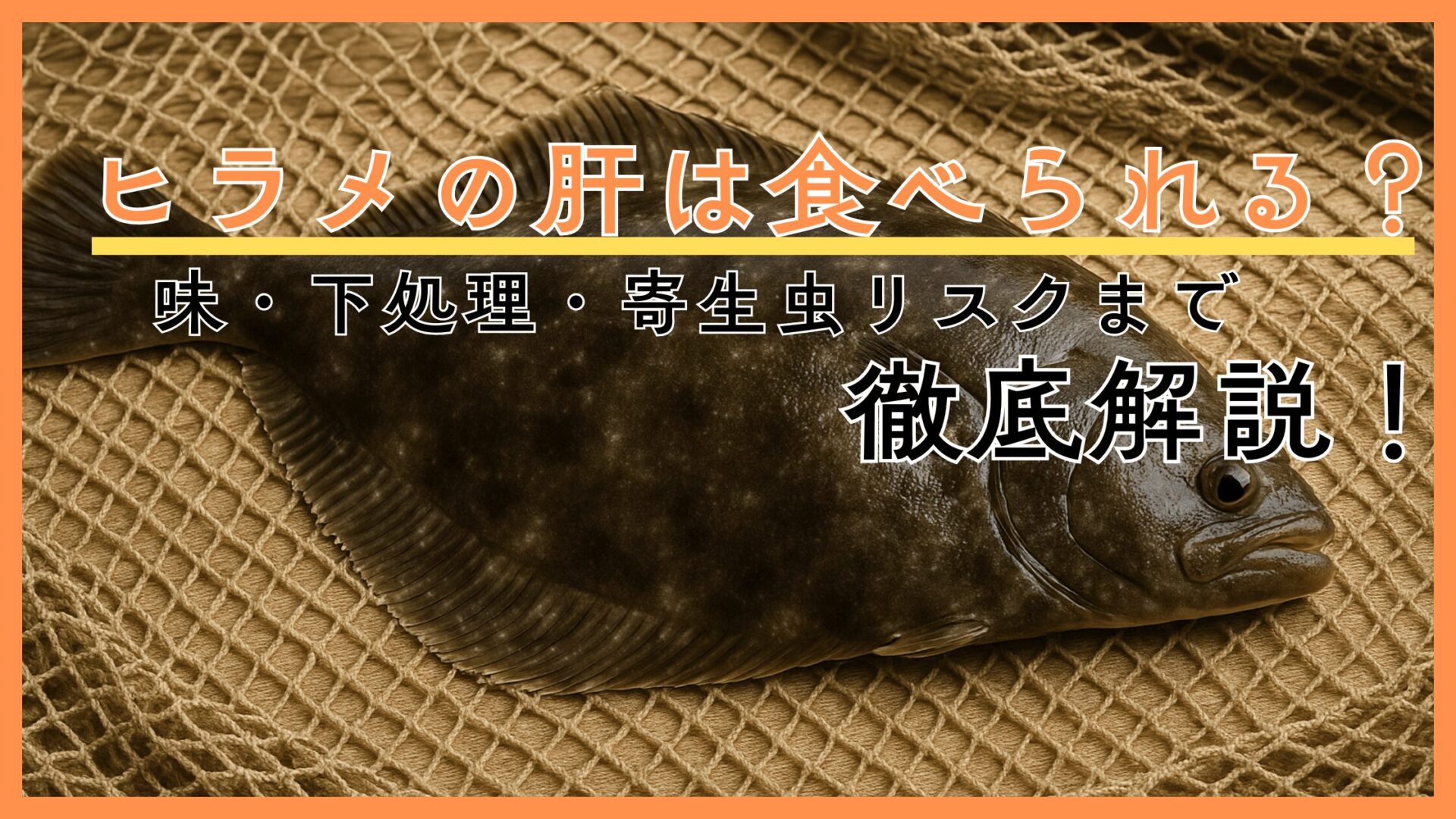
コメント