「セイゴ」とは「スズキ(シーバス)」の小型の個体の事。
「セイゴって小さいけど、食べられるの?」「臭いって聞いたけど本当?」──そんな疑問を持つ釣り人は多いのではないでしょうか。特に初めて釣った場合、リリースすべきか持ち帰るべきか迷う魚でもあります。
私自身、基本的にはセイゴはリリースしていますが、フックで傷つけてしまった個体など、やむを得ない場合は持ち帰って食べることもあります。意外かもしれませんが、丁寧に処理すればクセが少なく美味しく食べられる魚なんです。
実際、私が住む地域では年配の釣り人、特におじいちゃん世代はセイゴをよく持ち帰って食べている印象があります。昔ながらの「魚は全部ありがたくいただく」というスタイルなのかもしれませんね。
この記事では、セイゴの味や食べ方を中心に、下処理の方法やおすすめレシピまで丁寧に解説します。リリースする派の方も、万が一持ち帰る機会があった際の参考になれば幸いです。
セイゴは食べられる?|味・サイズ・安全性を解説

セイゴはスズキの幼魚として知られ、釣り人にはおなじみの存在です。ただ、そのサイズの小ささや「臭い魚」というイメージから、食べるかどうか判断に迷う方も多いのではないでしょうか。ここでは、セイゴの定義や味、安全性についてリアルな視点で解説していきます。
セイゴの定義とサイズ基準【リリースすべき?】
セイゴとは、スズキ属の魚のうちおおむね30cm未満の個体を指す通称です。成長段階に応じて「セイゴ → フッコ → スズキ」と呼ばれ、釣りの世界では特にセイゴサイズはリリースが推奨されることが多いです。
理由としては、まだ成長段階であること、味が劣るとされがちなこと、小骨が多く調理がやや面倒なことが挙げられます。ただし、針を飲み込んでしまったり、傷が深くリリースしても生きられないと判断した場合は、命を無駄にしない意味でも持ち帰るという選択肢も十分アリです。
また、地域によっては「25cm以下はリリース」という自主ルールを設定している釣り場もありますので、釣行時はそのあたりも確認しておくと良いでしょう。
味や身の特徴は?釣り人から見たリアルな評価
セイゴは成魚のスズキに比べて脂が少なく、身もやや水っぽい印象があります。ただし、身質そのものは柔らかく、加熱調理をすればクセの少ない白身魚として十分に美味しくいただけます。
個人的な体感では、釣ってすぐ血抜きを行い、しっかりと冷やして持ち帰れば、刺身でもそこそこ楽しめるレベルです。
ただ、淡白すぎて物足りなさを感じる方も多いため、唐揚げやつみれなど「旨味を引き出す調理法」で食べるのがベターだと感じています。
また、小さいからといって決して「まずい魚」ではなく、丁寧な処理と調理ができれば、「なんでリリースしてたんだろう」と感じるほどのポテンシャルを秘めている魚でもあります。
ヒラスズキ・マルスズキとの味の違いは?
セイゴとヒラスズキ、マルスズキの最大の違いは「脂のノリ」と「身の締まり方」です。
特にヒラスズキは荒磯で育つため筋肉質で、旨味が濃く刺身でも抜群に美味しい魚。
一方、セイゴは湾内や河口など比較的静かな場所に多く、柔らかく水分量が多い傾向があります。
刺身で比べると、セイゴはどうしても風味に欠け、プロの料理人があえて刺身で出すことは少ないです。しかし、揚げ物や煮付けではその柔らかさが活き、スズキよりも優しい味わいになることもあります。
ヒラスズキ・スズキとの比較については、別記事で詳しく紹介していますので、ぜひ参考にしてください。
▶︎シーバス(マルスズキ)は食べられる?味や食べ方を徹底解説!
▶︎ヒラスズキはまずいのか?味やマルスズキとの違いを徹底解説!
セイゴを美味しく食べるための下処理と保存方法

セイゴは丁寧な下処理と保存によって、見違えるほど美味しくなります。臭みが出やすい魚だからこそ、釣った直後の対応が味を大きく左右します。
この章では、初心者でも失敗しにくい処理・保存の基本を紹介していきます。
臭みを抑える下処理のポイントとは?
セイゴの味を大きく左右するのが「血抜き」と「内臓処理」です。釣った直後にすぐ締めて血抜きを行うことで、生臭さの原因となる血液の残留を防げます。
締め方は脳天やエラ下をナイフで切って即座に血を出す「活け締め」でもOKですが、手早く処理したい場合はエラを切って海水に浸けるだけでも効果があります。その後、帰宅前に氷でしっかりと冷やしながら持ち帰るのがベストです。
内臓や血合いは時間とともに腐敗しやすく、臭みの原因になります。持ち帰った後はすぐに鱗を落とし、内臓とエラを丁寧に取り除き、腹の中を流水でしっかり洗い流しましょう。
釣った直後にやっておくべきこと
セイゴを美味しく保つには、釣った「その瞬間」からの処理が重要です。筆者は基本リリース派ですが、傷つけてしまった個体や深く飲まれた場合は持ち帰るようにしており、その際の処理は以下の流れを徹底しています。
- ①針を外した直後にエラを切って血抜き
- ②海水を入れたバッカンやクーラーボックスで血を抜く
- ③冷却用の氷を使って低温状態を保つ
とくに夏場は魚がすぐに傷むため、「氷をたっぷり持っていく」「魚を直射日光に晒さない」といった細かい配慮が、食味を大きく左右します。
自宅での保存・捌き方の注意点まとめ
セイゴを持ち帰ったら、すぐに捌いて保存するのが理想です。すぐ食べない場合は、内臓を抜いてよく洗い、水気を拭き取ったあとでラップに包み、冷蔵または冷凍保存します。
冷蔵なら1〜2日以内、冷凍するなら1〜2週間以内には食べ切るのが目安です。冷凍する際は、空気に触れないよう真空パックかジップロック+ラップを使うと風味が長持ちします。
また、捌くときに注意すべき点として「小骨の多さ」が挙げられます。特に背びれ周りや腹骨周辺は細かい骨が残りやすいので、しっかりと骨抜き・すき取りを意識することで食感がぐっと良くなります。
セイゴのおすすめ食べ方3選|初心者でも簡単で美味しいレシピ

セイゴは小型のスズキで身もやわらかく、家庭でも扱いやすい魚です。
小骨が気になるという声もありますが、調理法を選べば美味しく仕上がります。
ここでは、初心者でも簡単に作れる定番レシピを3つご紹介します。
唐揚げ|小骨ごと食べられる万能メニュー
セイゴの定番料理といえば「唐揚げ」。中骨や小骨ごとカリッと揚げれば、骨まで美味しく食べられます。特に15〜20cm程度の小型の個体は、丸ごと揚げるのがおすすめです。
下処理をしたら、酒・醤油・しょうが・にんにくで10〜15分ほど下味をつけ、片栗粉をまぶして高温の油で二度揚げします。外はサクサク、中はふんわりで、白身の上品な旨味を楽しめます。
レモンやポン酢でさっぱりと食べるのもよく合い、おかずとしてもおつまみとしても万能です。
塩焼き|シンプルながら旨味を感じる定番料理
素材の味を活かしたいなら「塩焼き」が一番。セイゴの本来の甘みや風味を感じられるシンプル調理です。20cm以上のサイズなら三枚おろしにせず、そのまま開いて塩を振って焼くのが◎。
表面の水分をしっかりと拭き取ってから塩をふり、グリルまたはフライパンで皮目から焼いていきましょう。皮はパリッと、身はふっくらに仕上がります。
大根おろしやすだちを添えると、より上品な味わいに。塩加減ひとつでご飯のお供にも、お酒のアテにもぴったりです。
つみれ汁|クセが少ないセイゴにぴったりの優しい味わい
骨が気になる人におすすめしたいのが「つみれ汁」。セイゴの身をすり身にして団子にすることで、小骨や臭みも気にならず、体に優しい料理になります。
三枚におろした身を包丁で細かくたたき、しょうが・みそ・片栗粉・酒を加えてよく混ぜて団子状にします。それを沸騰した出汁に入れ、野菜と一緒に煮込めば完成です。
味噌仕立てでも醤油ベースでも美味しく、冷えた季節には特に喜ばれる一品。子どもや高齢の方にも食べやすく、家庭料理として重宝されます。
セイゴを食べる前に知っておきたいことまとめ

セイゴはスズキの若魚で、サイズや釣れた場所によって食味や安全性に差があります。小型であるほど身が柔らかく、調理法を工夫すれば非常に美味しく食べられる魚です。
特に唐揚げや塩焼き、つみれ汁などのレシピは初心者にも扱いやすく、家庭でも気軽に楽しめます。私自身も、傷つけてしまったセイゴを持ち帰って美味しく調理した経験があります。
とはいえ、地域や環境によって個体差があるため、釣った場所やサイズに応じてリリースを検討するのも大切です。安全に美味しくいただくためにも、下処理や保存方法をしっかり押さえておきましょう。
もしセイゴ以外のスズキ系の味についても気になる方は、以下の記事も参考にしてください。
▶ ヒラスズキの刺身は美味しい?寄生虫リスクやレシピまで解説!
▶ シーバスは食べられる?味・刺身・食べ方を釣り人目線で徹底解説!
釣りと食をつなぐ一歩として、セイゴを美味しくいただく体験が、きっと釣りの楽しさをさらに広げてくれるはずです。
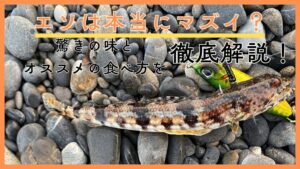


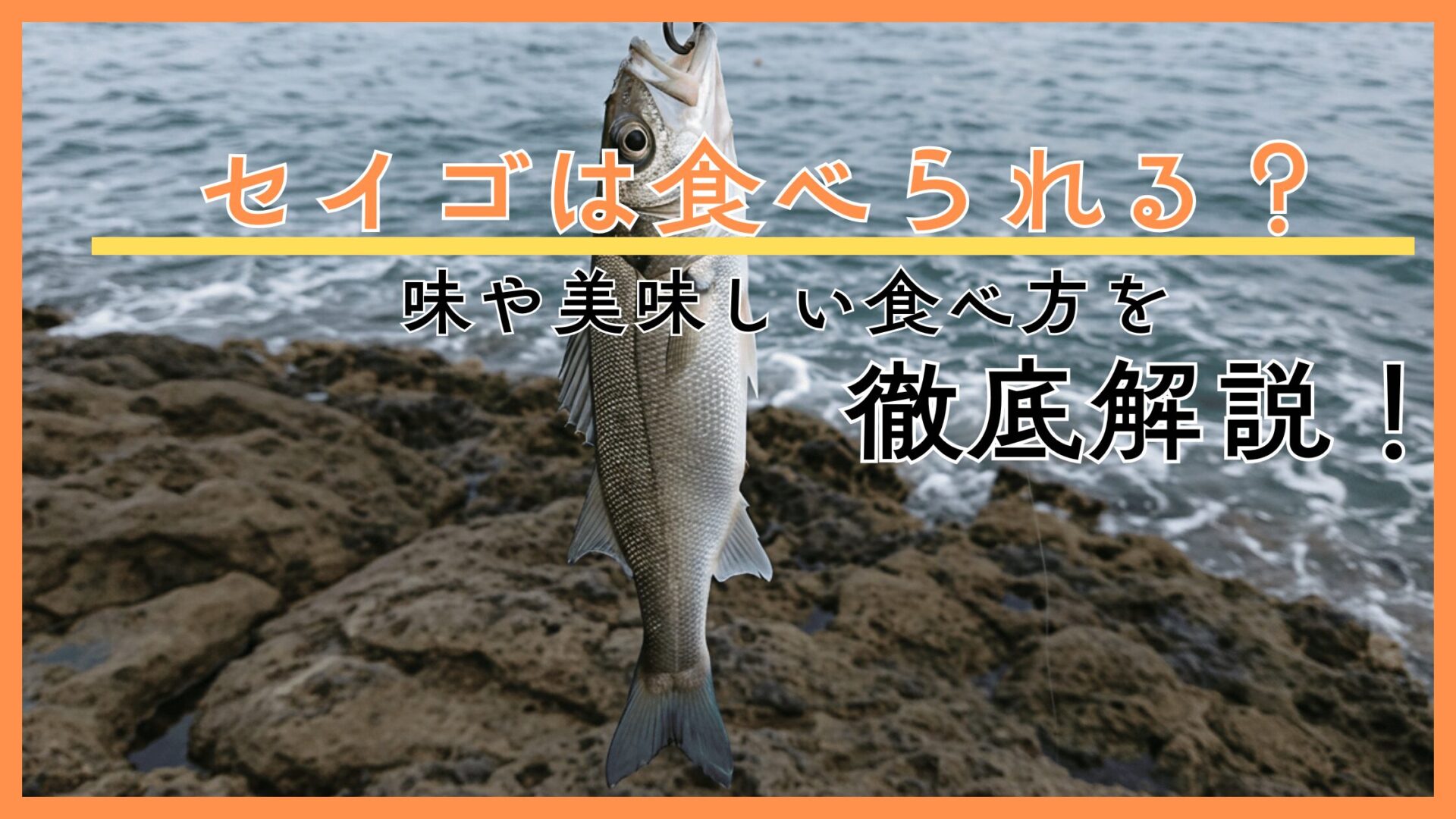
コメント