こんにちは。つりはる代表のはるです。
「豆アジっていつ釣れるの?」「今って狙える時期?」——そんな疑問を持つ方のために、豆アジがよく釣れる時期や狙い方のコツをわかりやすくまとめました。
実は、豆アジの接岸時期には明確な“釣れる季節”があるだけでなく、水温や潮、地域の違いによって釣果が大きく左右される魚でもあります。
この記事では、月別の釣れやすいタイミングや、エサ釣り・アジングの使い分け方など、初心者〜中級者の方が「いつ行けば釣れるのか」を判断しやすい情報を丁寧に解説しています。
これから豆アジ釣りを始めたい方も、もっと釣果を上げたい方も、ぜひ参考にしてみてください。
豆アジとは?釣れる時期・シーズンをわかりやすく解説!

「豆アジ」とは、一般的に5〜10cm程度の小さなマアジのことを指します。
地域や釣り人によっては「小アジ」とも呼ばれますが、実際には10〜15cm前後のやや大きな個体を“小アジ”と区別することが多く、それ以上になると普通に「鯵」とサイズ感で呼び分けられている事が多いですです。
豆アジは群れで回遊しやすく、防波堤や漁港から数釣りが楽しめることから、ファミリーフィッシングや初心者に特に人気のターゲットとなっています。
また、サイズが小さいため骨が柔らかくて食べやすく、南蛮漬けや唐揚げなどにすると丸ごと美味しく食べられるのも嬉しいポイントです。
ちなみに私自身、鯵をルアーで釣る「アジング」という釣りが好きで、シーズンになると毎年のように30cmを超える“尺鯵”を狙って出かけています。
釣って楽しいのはもちろんですが、サイズが大きくなると骨も太く、調理の際に骨を抜いたり気をつかったりする手間がかかるのが正直なところです。
その点、豆アジは骨が細くて柔らかいので丸ごと食べやすく、料理のしやすさという点ではむしろ豆アジの方が好きだったりします。
アジングで豆アジを狙うのは簡単ではありませんが、軽いジグヘッドや極細ワームを使って繊細なアタリを拾う感覚はとても楽しく、ゲーム性の高い釣りとして毎年楽しみにしているジャンルです。
この記事では、そんな豆アジが釣れやすい時期やシーズンの特徴を、月ごとの傾向を交えながらわかりやすく解説していきます。
「今って釣れる?」「いつからが狙い目?」といった疑問がある方は、ぜひこのまま読み進めてみてください。
豆アジのシーズンは6月〜11月が中心
豆アジ(10cm前後の小型アジ)は、毎年6月頃から釣れ始め、11月頃までがシーズンとされています。
この時期は水温が安定し、アジが沿岸部へと群れで回遊してくるため、防波堤や漁港からも手軽に狙えるのが特徴です。
中でも夏から秋にかけて(8月〜10月)は、最も数釣りがしやすいタイミング。
回遊してくる豆アジの数が多く、朝夕のマズメ時や常夜灯のある夜釣りでは入れ食いになることもあるほどです。
一方で、5月まではまだ海水温が低く、アジの回遊が少ないエリアも多いため、釣果はかなり不安定。
12月以降は一気に釣れなくなる地域も多く、シーズンオフに入るイメージです。
つまり、6月から11月の間が「豆アジを狙うならここ!」という時期。
特に夏〜秋は、初心者でも比較的簡単に釣果を出しやすいため、釣行計画はこの時期に合わせるのがおすすめです。
日本海側と太平洋側でも釣れ始めの差がある
豆アジの釣れ始めには、日本海側と太平洋側で大きな違いがあります。
これは海水温の上昇タイミングや潮流(黒潮・対馬海流など)の影響によるもので、同じ「6月」でも状況は大きく異なることがあります。
一般的には太平洋側の方が1ヶ月前後遅い傾向があります。
例えば、日本海側の地域では6月の初旬から豆アジが好調になる年が多く、堤防等で100匹近く釣れる事も。
一方、太平洋側の一部では、7月になってもまだ群れが接岸せず姿が見えないケースも珍しくありません。
この差は毎年の水温や潮の流れ次第で前後しますが、地域によって1ヶ月以上のズレが出ることもあるため、全国一律で考えるのは危険です。
「例年この地域は○月頃から釣れ出す」という地元の情報や釣果速報をチェックして、タイミングを見極めるのが釣果アップへの近道です。
初心者におすすめの狙い目時期は?
「豆アジ釣りを始めてみたいけど、いつ行けばいいかわからない…」という方におすすめなのは、夏から秋(7〜10月)の期間です。
この時期は、岸近くに豆アジの群れが入ってきており、数釣りがしやすいシーズン。
釣り場も混み合いますが、初心者でもちょい投げやサビキ釣りで簡単に釣れるチャンスが多いため、入門にはぴったりのタイミングです。
特に8〜9月の夕マズメ〜夜にかけては、常夜灯まわりに群れが入ってくることが多く、短時間で10〜30匹以上釣れることも珍しくありません。
反対に、春(3〜5月)や冬(12〜2月)はサイズは出やすいですがアジの接岸が少なく、釣れても数が出にくいため難易度が高めです。
初めてチャレンジするなら、まずは夏から秋の釣りやすいタイミングを狙うのが失敗しにくくおすすめです。
豆アジ釣りに適したタイミングとは?エサ釣りとアジングの使い分け

「豆アジは簡単に釣れる」と思われがちですが、実は釣り方によって適した時期や状況がまったく異なります。
特にエサ釣り(サビキ釣り)と、ルアーで狙うアジングでは釣果の出やすい季節や時間帯も変わってくるため、時期に合わせて上手に使い分けることがポイントです。
この章では、豆アジ釣りでよく使われる2つの釣法について、それぞれどの時期に向いているのかを詳しく解説していきます。
「どっちを使えばいいかわからない」「失敗しないタイミングで行きたい」という方は、ぜひ参考にしてみてください。
サビキ釣りに適した時期(豆アジ編)
豆アジを数釣りしたいなら、最も手軽で成功率が高いのがサビキ釣りです。特に6月〜10月にかけては、岸近くまで群れが寄るため、防波堤や漁港などの足場の良い場所からでも十分に狙うことができます。
この時期は春に孵化したアジが5〜10cmほどに成長し、豆アジサイズとなって群れで回遊しはじめます。
特に夏場(7〜9月)は活性も高く、アミエビのコマセを撒くだけで足元に大量の群れが集まる光景もよく見られます。
アジの活性が高い時は、コマセ無しのサビキ針のみでも入れ食いになることも。
また、日中の明るい時間帯でも釣果が出やすく、ファミリーフィッシングや初心者にも最適です。特に風が穏やかで波が少ない日には、豆アジが表層に浮いてくることも多く、短時間でも手軽に10〜30匹以上釣れることも珍しくありません。
夜釣りでも常夜灯のあるポイントでは、プランクトンが集まり、それを追って豆アジの群れが入ってくることがあります。
夕マズメ〜夜の時間帯は特にチャンスが多く、夜のサビキ釣りでも豆アジが入れ食いになる状況もしばしば見られます。
一方で11月以降は海水温の低下とともに豆アジの群れが沖へ離れていき、サビキ釣りでは釣果が出にくくなります。
豆アジ狙いでサビキ釣りを楽しみたい場合は、6月〜10月の暖かい時期に狙うのが最適です。
アジングが効果的なシーズン(豆アジ編)
豆アジをルアーで狙う「アジング」は、実はサビキ釣りよりも少し難易度が高い釣り方です。
とはいえ、シーズンをうまく選べば、豆アジでも十分に釣果を上げることができ、軽いジグヘッドで繊細なアタリを取る楽しさは格別です。
特におすすめのタイミングは、夏から秋(7〜10月)にかけて。
この時期は水温も高く、岸近くまで群れが接岸してくるため、1インチ前後の小型ワームでも十分に反応が得られやすいシーズンです。
夕マズメから夜にかけて、常夜灯の下でスローに誘えば小さなアタリを拾う練習にも最適です。
逆に、春(3〜5月)や冬(12〜2月)は豆アジの数自体が少なく、アジングで狙うにはやや厳しい時期になります。
その分、夜間の常夜灯周りに残っている“居付き”の豆アジを狙うゲーム性の高い釣りとして楽しむこともできますが、ある程度経験がある方向けと言えるでしょう。
豆アジは口が小さく吸い込みも弱いため、ジグヘッドのフックサイズや重さ、ワームの柔らかさなどにもこだわる必要があります。
「釣る」というよりも「掛ける」テクニックが必要になる分、ハマると奥が深く、上達を実感しやすいのが豆アジングの魅力です。
豆アジはサイズが小さいぶん、「誰でも簡単に釣れる」と思われがちですが、実は狙って釣るのは意外と難しいターゲットです。
むしろ30cm近い大型のアジの方が、口も大きく吸い込みも強いため、釣るのはずっと簡単だったりします。
それでも私自身は、この小さなアタリを繊細に拾って掛ける“豆アジング”のゲーム性がとても楽しく、毎年のように狙っています。
たとえ釣果は少なめでも、「1匹を絞り出す面白さ」があるのが、豆アジ釣りの醍醐味だと感じています。
▼豆アジングのおすすめのワームやジグヘッドについては別記事で解説しています▼


最初は数釣りが楽しめる夏〜秋にかけての高活性期から始め、アタリの取り方や合わせの感覚に慣れるのがおすすめです。
釣果に差が出る!水温・潮・時間帯・天候の関係

「同じ時期に釣りに行ったのに、自分だけ釣れなかった…」という経験はありませんか?
実は、豆アジ釣りでは水温・潮の動き・時間帯・天候といった自然条件が大きく釣果を左右します。
特に豆アジはサイズが小さく、海のちょっとした変化にも敏感に反応する繊細なターゲットです。
時期を選ぶだけでなく、「いつ・どんな状況で釣るか」を意識することで、同じ場所でも釣果に大きな差が出ることも珍しくありません。
ここでは、豆アジが釣れやすくなる水温の目安、潮のタイミング、狙い目の時間帯や天候の傾向について詳しく解説していきます。
豆アジが活性化する水温の目安
豆アジを安定して釣るには、「いつ釣れるか」だけでなく海水温がどれくらいかを知っておくことも大切です。
豆アジは15〜23℃程度の水温で活性が高まりやすく、18〜20℃前後がもっとも安定して釣れやすいと言われています。
特に6月〜10月は、水温がこの範囲にあることが多く、豆アジが接岸しやすくなるため、数釣りのチャンスが増える時期です。
逆に、海水温が15℃を下回る冬場や、23℃を超える真夏の昼間などは、岸近くの豆アジの活性が一気に落ちたり、沖へ離れてしまう傾向があります。
ただし、いくら水温がちょうどよくても、豆アジは遊泳力が低く、潮の流れが強い場所や水深のあるエリアには留まりにくいという特性もあります。
そのため、ポイントによっては条件が揃っていても「そもそもいない」というケースもあるため、“釣れる場所選び”も重要です。
釣行前に「今日は釣れるのかな?」と迷ったときは、近くの港や潮通しの良いポイントの水温を調べてみるのがおすすめ。
最近では釣具店のサイトや海釣り公園の公式サイト、気象庁の海況データなどでもリアルタイムで水温をチェックできるので、ぜひ活用してみてください。
潮の動き・時間帯・天気を味方にするコツ
豆アジを狙ううえで、水温と並んで重要なのが潮の流れ・時間帯・天気といった自然の変化です。
「隣の人だけ釣れてる」「昨日は爆釣だったのに今日はダメ…」というような差は、こうした環境条件のちょっとした違いで生まれていることが多いのです。
まず潮の動き潮が止まっている時間帯(潮止まり)には極端に活性が落ちることがあります。
特に豆アジは泳ぐ力が弱く、エサが流れてくる状況=潮が動いているタイミングの方が圧倒的に釣れやすくなります。
次に時間帯朝夕のマズメ時(夜明け前後・日没前後)に岸近くへ回遊する傾向があり、豆アジも例外ではありません。
昼間に釣れる日もありますが、安定して釣果を出したいなら、マズメ狙いが鉄則です。
また、夜釣りでは常夜灯のあるポイントを狙うと、光に集まったプランクトンや小魚を追って豆アジが寄ってきます。
特に夕マズメから夜にかけての「常夜灯+潮が動いている時間」は、釣果が爆発するゴールデンタイムです。
最後に天気 曇りや小雨などで光量が抑えられている日は、豆アジの警戒心が薄れて昼間でも活性が上がりやすくなることがあります。
逆に、真夏のピーカン(快晴・無風)などは警戒心が強くなり、豆アジが沖に出てしまって釣れないこともあります。
このように、豆アジ釣りでは自然条件を“読む力”がそのまま釣果につながります。
「いつ釣りに行くか」だけでなく、「その日のどの時間にどんな場所でどんな状況か」を意識することで、1匹でも多くの魚と出会える確率がぐっと高まります。
まとめ|豆アジの釣れる時期を知れば釣果アップに直結!

豆アジは6月〜10月頃がもっとも釣果を出しやすい時期で、水温や潮、時間帯、天候といった条件にうまく合わせることで、初心者でも数釣りを楽しむことができます。
特に夏〜秋にかけての夕マズメ〜夜間の常夜灯周辺は、エサ釣りでもアジングでも釣果が出やすいベストタイミング。
逆に、春や冬は難易度が高いため、はじめての豆アジ釣りなら水温が安定する夏以降を狙うのがおすすめです。
また、豆アジは群れが入っていなければどれだけ技術があっても釣れない魚なので、事前の釣果情報チェックや水温確認も重要なポイント。
「今どこで釣れてる?」「今日の潮は?」といった情報をうまく活用して、ぜひ自分にとっての“当たり日”をつかんでください。
季節や状況を見極めて挑めば、豆アジ釣りは簡単で楽しく、そして奥が深い最高のターゲットになります。
ぜひ今回の記事を参考に、次回の釣行をより充実したものにしていただければ幸いです。
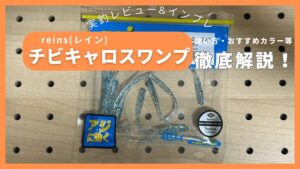





コメント