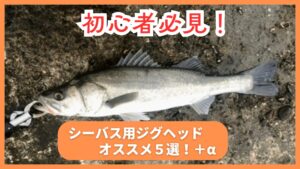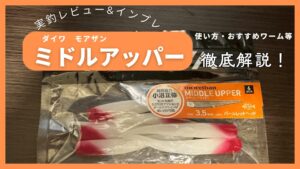「シーバス釣りにはワームが効くって聞くけど、正直どれを選べばいいのか分からない…」
そんな悩みを持つ初心者〜中級者の方へ向けて、この記事では実釣実績のあるシーバス用のワームのおすすめ10選をご紹介します。
私はこれまでにシーバスを1,000匹以上釣り上げてきました。
その実釣経験をもとに、ワームの選び方や使い方、状況別のおすすめルアーなどをまとめました。
経験者だからこそ分かる「初心者が最初に選ぶべきワーム」や「釣れない時の見直しポイント」なども含めて、わかりやすく解説します。
シーバス釣りは全国各地の港湾、河川、サーフなどで楽しめる人気ジャンルですが、その反面「ワームの種類が多すぎて迷う」「選び方が分からない」「使い方が合っているか不安」といった声も多く聞かれます。
この記事ではワームが釣れる理由や選び方の基本から、実際に釣果が出ているおすすめモデルまでを徹底解説。
さらに「釣れない時の見直しポイント」や「カラー・サイズの選び分け」など、初心者がつまずきやすい点にも丁寧に触れていきます。
なお、ジグヘッドの選び方については別記事で詳しく解説していますので、この記事では主にワーム本体の特徴や使い分けに焦点を当ててご紹介していきます。
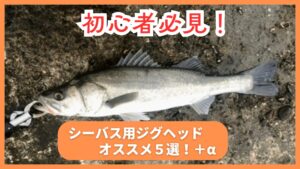
すでにワームを使っているけど釣果が出ていない方はもちろん、これからシーバスゲームに挑戦したいという方にもぴったりの内容です。
シーバス ワームのおすすめモデルを知り、釣果アップへの一歩を踏み出しましょう!
なぜシーバスにワームがおすすめなのか?その理由と使いどころ

ワームといえば「ソフトルアー」の代表格。シーバス釣りにおいてもワームの存在は欠かせません。
一見すると地味で派手さがない分、初心者からすると「本当にこれで釣れるの?」と不安になるかもしれませんが、むしろ状況次第ではハードルアーを上回る釣果を叩き出す実力派です。
ここでは、私がこれまで1,000匹以上のシーバスを釣ってきた経験から、なぜワームが効くのか、どういった場面で使うべきなのかをお伝えします。
ワームが釣れる理由は“自然な動き”
シーバス釣りにおいてワームが効果的な最大の理由は、その自然な動きにあります。ワームはソフト素材でできており、水の流れやロッド操作に対してしなやかに反応し、まるで生きたベイトのようなアクションを生み出します。
特にプレッシャーが高いフィールドや、活性が低い状況ではシーバスも警戒心が強くなり、ハードルアーのような派手なアクションには見切りをつけられがち。そんなときに、ゆらゆらと漂うようなワームのナチュラルな動きが、まさに“食わせの一手”になります。
実際に私も、ハードルアーでは何の反応も得られなかった状況で、ワームに切り替えた途端に連発したというケースは何度も経験しています。
「本物っぽさ」が伝わるからこそ、シーバスのバイト(食いつき)を引き出せる。それがワームの強さです。
ハードルアーとワームの違い
ハードルアーとワームの違いを端的に表現するなら、「攻めのハード」vs「食わせのソフト」です。ハードルアーは広範囲を素早く探るのに適しており、サーチ能力が高く、アピール力も抜群です。
一方でワームは、ピンポイントやスレたエリアをじっくりと丁寧に攻めるのに向いています。波動やフラッシングは控えめですが、その分違和感が少なく、警戒心の強い魚にも口を使わせやすいのが魅力です。
また、ハードルアーは一定の形状・動きを持つ完成品ですが、ワームはジグヘッドとの組み合わせやアクションの付け方で自在に調整できるという柔軟性もあります。
この柔軟さが、ベイトパターンが日々変化するシーバス釣りにおいて大きなアドバンテージになるのです。
初心者にも扱いやすい?実際の使い勝手
結論から言えば、シーバス釣りにおいてワームは初心者にとって非常に扱いやすいルアーです。
がシンプルで派手さこそありませんが、その使い方は意外にも直感的で、難しいテクニックを必要としません。
たとえば「ミノーやバイブレーションはアクションをつけるのが難しい」と感じている方でも、ワームなら“ただ巻き”で十分に釣果が出せるという点が大きなメリットです。
リールをゆっくり巻くだけで、柔らかいワーム本体が自然な揺らぎや微振動を発し、ベイトに近い波動を生み出してくれます。
また、シーバスは状況によってレンジ(泳層)やベイト(餌の種類)を選り好みする魚ですが、ワームはジグヘッドの重さやアクションの工夫で、そういった変化にも柔軟に対応できるという利点もあります。
これは、たとえば「今日はベイトが小さいから小さめのワームで」「レンジが深いから重めのジグヘッドで」といった調整が簡単にできる、ということです。
さらに、ワームはロストしても比較的安価に補充できるのも嬉しいポイントです。
ハードルアーは1個1,500〜2,000円ほどすることも珍しくありませんが、ワームは数本入りで数百円。ジグヘッドも1個100〜300円程度で購入できます。つまり、「根掛かりが怖くて攻められない」という初心者でも、ワームなら気軽にリスクを取って攻めることができるのです。
私が釣りを始めたばかりの頃、最初にヒットさせたのも実はワームでした。
ハードルアーでは反応がなかった港湾エリアで、5gのジグヘッドにピンク系のピンテールワームをつけて、岸際をゆっくり巻いていたらゴンッという強烈なバイトが。これがシーバス釣りにどっぷりハマるきっかけにもなりました。
もちろん、使い方次第で釣果は変わりますが、ワームは“失敗しづらく、当たりを引きやすい”ルアーだと感じています。特に初心者の方には、まずワームで釣果を出すことで釣りの楽しさを実感してほしい。そう強く思っています。
デメリットと注意点も理解しよう
シーバス釣りにおいてワームは非常に優れたルアーですが、万能というわけではありません。
その特性を理解せずに使ってしまうと、「釣れない…」と感じてしまう場面も出てきます。ここでは、ワームのデメリットと注意点を整理しておきましょう。
まず最も大きなデメリットは、アピール力が控えめであるという点です。
ハードルアーに比べると、ワームは波動や音、フラッシングといった視覚・聴覚的な刺激が少ないため、広範囲にいるシーバスを引き寄せる力が弱い傾向があります。特に水が濁っていたり、風や波が強いときには、そもそも存在に気づいてもらえないというケースもあります。
また、ワームはフグや小魚にかじられてボロボロになることがあります。
特に夏場や水温が高い時期はフグの活性も高く、せっかく投入したワームが数投で千切れてしまう…という事態も珍しくありません。ハードルアーに比べて消耗が早いことは事前に覚悟しておく必要があります。
さらに、ワームを使うにはジグヘッドとのセッティング作業が必要です。
初心者にとっては「まっすぐ刺せない」「すぐズレる」といった小さなストレスが積み重なることも。とはいえ、最近はガイド穴付きのワームや専用設計のジグヘッドなど、初心者でも綺麗にセットできるアイテムが増えているので、それらを選ぶことで解決できます。
そしてもう一つの注意点はワームの動きが“地味すぎる”がゆえに、使い方次第では魚に気づかれないまま通り過ぎてしまうこともあるという点です。
たとえば、流れの速い河口などでは軽いジグヘッドでは沈みきらずに漂ってしまい、レンジが合わなくなることがあります。逆に重すぎるとボトムをズル引きになって根掛かりの原因になるので、状況に応じたセッティングが重要です。
とはいえ、こうしたデメリットは事前に理解しておけば十分対処できるものばかりです。
ワームは“釣れるルアー”であることに変わりはありません。弱点を理解し、その上で状況に応じて使い分けることこそ、釣果を安定させるコツだと私は考えています。
釣れるシーバスワームのおすすめ選び方|形・サイズ・カラー・リグの基本

「釣れるワームを使いたい」と思っても、実際に釣具屋やネットショップを見ると、その種類の多さに圧倒される方も多いのではないでしょうか。
でも安心してください。基本的なポイントさえ押さえれば、初心者でも的確に自分に合ったワームを選ぶことができます。
ここでは、シーバスに効くワームの“選び方”を、形状・サイズ・カラー・リグの観点から順番に解説していきます。
ワームの形状は大きく分けて2タイプ(ピンテール/シャッドテール)
シーバス用のワームには数多くの種類がありますが、形状に注目すると大きく2つのタイプに分類されます。
それが「ピンテール系」と「シャッドテール系」です。それぞれの特徴を理解すれば、どんな状況でどのワームを選べばよいかが見えてきます。
まずピンテール系は、細長くシンプルなシルエットが特徴で、先端が細くなっているストレート形状のワームです。
動きは控えめですが、ナチュラルでスレに強いのが魅力。バチ抜けパターンや、プレッシャーが高い状況で活躍します。
細身ゆえにダート(横方向の跳ね)アクションを付けやすく、リアクションバイトを狙う場面にも有効です。
一方のシャッドテール系は、尾の部分が“ヒレ”のように広がった扇形をしており、巻くだけでテールがプルプルと揺れてアピール力が強いのが特徴です。
広範囲を探りたいときや、水が濁っているとき、シーバスの活性が高い場面ではこちらが向いています。泳ぎが安定しているため、初心者にも扱いやすいタイプです。
実際、私も「ピンテールで反応がなかったけれど、シャッドテールに変えた途端に連発した」という経験が何度もあります。逆に、派手なシャッドテールで見切られていた場面で、ピンテールに切り替えたらスレたシーバスがヒットしたことも。ワームの形状を変えるだけで釣果が劇的に変わることは珍しくありません。
結論として、どちらか片方だけを使うのではなく、「使い分ける」前提で両方持っておくことが重要です。まずはスタンダードなシャッドテールで広範囲を探り、反応がなければピンテールに替えて食わせにシフト。こうしたローテーションが、安定した釣果への近道になります。
サイズの選び方|状況別に使い分けよう
シーバス釣りにおいて、ワームのサイズ選びは釣果に直結する重要な要素です。なんとなく見た目やパッケージの印象で選んでいると、せっかく魚がいても口を使わせることができないこともあります。
まず基本として、3インチ〜4インチのサイズがシーバスワームのスタンダードです。全国的に見ても、このサイズ帯が最もバランスが良く、多くのアングラーに支持されています。特に港湾部や河川、湾奥エリアなどの都市型フィールドでは、これらのサイズが「大きすぎず、小さすぎず」という感覚で、扱いやすさ・食わせ能力ともに優秀です。
一方で、マイクロベイトが回遊している春や初夏などは、2インチ前後の小型ワームが有効になることがあります。シーバスが小型のイナッコやハク(ボラの稚魚)を捕食しているときは、「大きいルアーは無視、小さいものにだけ反応する」なんて状況も。
そんな時こそ、小型ワームの出番です。逆に秋の落ちアユパターンなど、ベイトが10cm以上ある場合は、4.5インチ〜5インチクラスの大型ワームも十分に有効です。
また、フィールドの規模によっても適切なサイズは変わってきます。港湾部など小規模エリアではナチュラルな小型ワームが強い一方、サーフや河口のような広大なエリアでは、遠投性能や目立ちやすさの観点から、やや大きめのワームが活躍します。こうした“フィールドとベイトのサイズ感”をリンクさせる意識が、釣果アップに直結します。
私の実釣経験でも、普段3.5インチのシャッドテールで釣れていた河川エリアで、2インチのピンテールに変えた途端、スレた魚が口を使ってくれたことがありました。
逆にサーフでは、3インチだと飛距離が足りず、4.5インチの重めセッティングでようやく釣果が出たというケースも。
結論としては、常に1サイズ上と下の選択肢を持っておくこと。
メインサイズに加えて、食いが渋いとき・ベイトが大きいときに備え、柔軟に使い分けられるようにしておくのがベストです。サイズ感は「釣れるか釣れないか」を左右する、見落とせない要素なのです。
カラーの選び方|明るさ・水質・時間帯がカギ
「カラーは見た目の好みで選べばいい」と思われがちですが、シーバス釣りでは状況に応じた色の使い分けが、釣果に大きく影響します。
実際、同じワームでもカラーを変えただけで反応が一変することはよくある話です。
まず基本的な考え方として、明るい場所・クリアな水質ではナチュラルカラー、濁った水質やローライト時はアピール系カラーが効果的とされています。
たとえば昼間の晴天、河川や港湾で水が澄んでいるようなシチュエーションでは、クリア、グリーン、ワカサギカラーといった自然に近い色が、警戒心の強いシーバスに口を使わせやすくなります。
逆に、雨後の濁りや夜釣り、朝マズメや夕マズメといった光量が少ない時間帯では、チャート、ピンク、ブラック、ホワイトといったシルエットがはっきり出るカラーが有効です。
濁った中でも目立つカラーで存在感を出し、視認性とバイト誘発力を両立させることができます。
また、ベイトの種類に合わせたカラー選びも重要です。例えばバチ抜けシーズンにはクリアレッド系、アミパターンでは透明感のあるピンクやオレンジ系、イナッコやサヨリが多い時期は銀ラメ系やナチュラルグレー系が有効。ベイトパターンを読み、それに合った色を選ぶことで「自然なマッチング」が成立します。
私自身の経験では、ナイトゲームで反応がなかったワームを白に変えた途端に連発したことや、クリアウォーターでチャートを使って完全に無視されたのに、グリーンにしただけで釣れ始めたケースなど、「色だけでここまで違うのか」と驚く場面が何度もありました。
結論としては、最低でもナチュラル系・アピール系の2色は常備しておくことを強くおすすめします。状況やベイトに応じて適切なカラーに素早く切り替えることが、シーバスゲームにおける大きな武器になります。迷ったときは“その場の水質”と“時間帯の明るさ”を基準に、色を選んでみてください。
ジグヘッドとの組み合わせ方|レンジキープが釣果を左右する
シーバスワームの性能を最大限に引き出すには、ジグヘッドの選び方と組み合わせ方が極めて重要です。実は、同じワームでもジグヘッドの重さや形状が違うだけで、レンジ(泳層)やアクションの質が大きく変わってしまうんです。
まず大前提として、シーバスはその日のベイトの位置=レンジに合わせて狙うのが基本です。例えば水面直下を泳ぐバチを追っているときに、重すぎるジグヘッドでボトムを引いても見向きもされません。逆に、ベイトが沈んでいるのに軽すぎて沈められないと、シーバスの視界に入らないままスルーされてしまいます。
そのため、水深・流れの強さ・風の有無などを考慮して、ジグヘッドの重さを選ぶ必要があります。港湾部や河川なら5g〜7g、サーフや河口では10g〜14g程度が目安です。最初は軽めで試して、ボトムに着くまでの時間やアタリの有無を見ながら調整すると良いでしょう。
また、形状にも注目です。水の抵抗を受けにくくスイム姿勢が安定するラウンド型、ダートアクションに特化した矢じり型、ボトムを攻めやすいフットボール型など、シチュエーションに応じた形状を選ぶことでワームの性能を活かし切ることができます。
個人的には、初心者のうちはラウンド型ジグヘッドを中心に使うのがおすすめです。どんなワームにも相性が良く、引くだけで安定した泳ぎが得られるので、まずはそこからスタートし、慣れてきたら徐々にバリエーションを増やしていくと良いでしょう。
ちなみに、ジグヘッド選びについては別の記事で「用途別のおすすめモデル」や「状況別の使い分け」について詳しく解説していますので、より深く知りたい方はそちらもぜひチェックしてみてください。
🔽シーバス用ジグヘッドの選び方についてはコチラ🔽
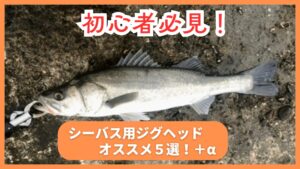
結論として、ワームとジグヘッドの組み合わせは「釣れるかどうか」に直結する要素。レンジを正確にキープできるセッティングを意識することで、ワームの動きがより自然に見え、シーバスのバイトを誘発しやすくなります。道具の選び方一つで釣果が変わる──それがルアーゲームの奥深さであり、面白さでもあるのです。
最強のシーバス用ワームおすすめ10選【初心者〜中級者向け】

ここからは、私が実際に釣果を上げてきたシーバス ワームのおすすめ10選をご紹介します。
単体ワームの紹介を中心に、初心者でも使いやすいジグヘッドもセットになったモデルや、アジングロッドのようなライトゲームロッドでも使える小型ルアーまで幅広く紹介していきます。
どれも実績に裏付けされたモデルばかりで、初心者でも扱いやすく、釣れる場面が明確なアイテムばかりです。
釣行前のルアーボックス選びに、ぜひ参考にしてみてください。
ミドルアッパー|汎用性抜群の超定番シャッドテール
「迷ったらコレ」と断言できる、シーバス用ワーム界の大定番がこの「ミドルアッパー」です。
Daiwaのモアザンシリーズの代表的なワームで、幅広いシチュエーションで使える抜群の汎用性を誇ります。
最大の魅力は、ただ巻きでもしっかりテールが水を掴んで安定したナチュラルな泳ぎを演出してくれる点。
派手すぎず地味すぎず、まさに“ちょうどいい波動”で、プレッシャーが高いエリアでも見切られにくく、しっかりバイトを引き出してくれます。
特に効果的なのは港湾部・河川・湾奥などの小規模フィールド。
水深が浅めの場所でもしっかりと泳がせることができ、流れが強い場面でもバランスを崩さずキープできます。もちろんサーフや外洋でも、ジグヘッドの重さを変えれば対応可能。
私もミドルアッパーでは何十本というシーバスを釣ってきましたが、特徴的なのは「活性が低いときでもバイトが出る」こと。朝マズメに軽く巻くだけで食ってきたり、ボイルが散ったあとの沈黙状態でヒットさせたこともありました。どんなタイミングでも仕事してくれる安心感があります。
カラー展開も豊富で、ナチュラル系からアピール系まで選びやすく、複数持っておいて損はありません。
初めてシーバス用ワームを使う方には、まず最初に試してほしい1本としておすすめします。
オススメのジグヘッドの組み合わせは同じDaiwaの「シーバスジグヘッドSS」です。
この組み合わせだと、ワームを上下逆にセッティングする事によってダートアクションも可能になります。
▼さらに詳しく知りたい方はコチラからどうぞ▼
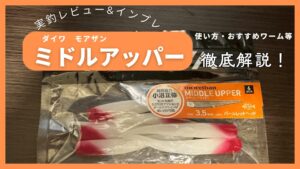
R32|ナチュラル&バチ抜け攻略の定番ピンテール
バチ抜けシーズンに絶対持っておきたい1本が、マーズの「R32」です。
ピンテールタイプの中でも特にナチュラルな動きを得意とし、港湾部・干潟・河口域など、ベイトサイズが小さくなりがちなエリアで絶大な効果を発揮します。
このワームの最大の魅力は、わずかな水流にも反応して微細に揺れる繊細なアクションです。
シーバスがバチ(ゴカイ類)やアミ、小型ベイトを意識しているタイミングでは、強い波動よりもこのような微弱な動きの方がバイトにつながりやすくなります。
特におすすめしたいのは、夜のデッドスローリトリーブ。
潮のヨレに沿ってゆっくりただ巻きするだけで、R32がわずかに震えながら流れに乗り、まるで本物のバチやアミのように見せてくれます。その自然さは、スレたシーバスの警戒心をも打ち破るほど。何も反応がなかった状況でR32に変えた途端、ボイルが起きたという経験もあります。
また、ピンテールながら軽量ジグヘッド(3g前後)でもしっかり動きが出せる点もポイント。
水面直下を漂わせたい場面や、ドリフトで使いたいときにも最適です。これにより、都市型フィールドの常夜灯下やシャローエリアなど、ナチュラルアプローチが求められる場面に強い武器となります。
カラーは赤系・ピンク系・クリア系が定番ですが、私の経験上はやや白っぽい半透明系(いわゆる「シラウオ系」)が最も安定した釣果を出してくれています。鉄板カラーと言っても過言ではありません。
「シーバスが目の前にいるのに食わない」
「見切られている気がする」
そんなときこそ、ナチュラルの極み・R32を試してみてください。その静かな存在感が、バイトを引き出してくれるはずです。
▼さらに詳しく知りたい方はコチラからどうぞ▼


デスアダー |圧倒的な大型シルエットの名作ルアー
バス用ワームとして圧倒的な知名度を誇るdepsのデスアダーですが、実はシーバスやヒラメにも効果抜群なことから、ソルトでも人気が高いワームです。
サイズ展開は複数ありますが、シーバス・ヒラメ狙いで特におすすめなのが6インチ。
いわゆる「デスロク」と呼ばれるサイズで、一見かなり大きいですがソルトゲームとの相性の良さでも有名です。
最大の特徴は、超大型シルエットによる圧倒的なアピール力。
一見すると食いにくそうなサイズ感ですが、ワーム形状が非常にシンプルかつ完成度が高いため、驚くほど吸い込みやすいのがポイントです。
テールはピンテール形状で、派手に動きすぎず、アクション自体は非常にナチュラル。
そのため、強い存在感を出しつつも、違和感を与えにくく、アピール力と食わせ能力を高い次元で両立しています。
かなり大型ワームなのでランカーシーバス狙いはもちろん、実際には小型のシーバスでも普通に口を使ってくるのでサイズを問わず使えるのも強みです。
サイズ感で敬遠されがちですが、「ベイトが大きい」「魚の活性が低い」「他のワームに反応しない」場面では、むしろデスアダーが最後の切り札になることも少なくありません。
アルカリシャッド/コアマンVJ|“反則級”と呼ばれる最強完成ルアー
コアマンVJシリーズの純正ワームとして知られる「アルカリシャッド」は、シャッドテール系ワームの中でも非常に完成度が高く、シーバス釣りの新定番として多くのアングラーに愛用されています。
このワームの大きな特徴は、頭部がやや太めで自立性があり、ジグヘッドにしっかりフィットする構造になっていること。
リグとの相性がよく、泳ぎが安定しやすいため、ジグヘッドを変えてもその性能を活かしやすい設計です。特にVJとの相性は抜群で、まさに“専用機”といっても過言ではありません。
アクションは巻きの安定感とテールの振動が両立しており、シーバスが広範囲に散っているような場面でも、ナチュラルかつアピール力抜群の波動で確実に存在をアピールしてくれます。
チャート系やナチュラル系カラーが多くラインナップされており、あらゆる水質に対応できるのも魅力です。
特にサーフやオープンウォーターで強さを発揮する一方で、都市型港湾や運河エリアでも使いやすい万能選手です。
私自身も、港湾エリアでスレきったシーバスを狙う際にアルカリシャッドを投入し、反応がなかった状況を打破した経験が何度もあります。
また、純正ワームでありながら単体販売もされており、補充しやすいのもポイント。
VJヘッドにセットするもよし、別のラウンド型ジグヘッドで自由にセッティングするもよしと、カスタマイズ性が高い点も嬉しい特徴です。
結論として、「とりあえず1本釣りたい」「信頼できる波動が欲しい」と思ったときに頼れるのがこのアルカリシャッド。
VJシリーズの拡張パーツとしても、単体ワームとしても活躍する“二刀流ワーム”として、ぜひ1パックはボックスに忍ばせておきたい存在です。
▼さらに詳しく知りたい方はコチラからどうぞ▼

アルカリ|ダートもスイミングもこなせる万能ピンテール
ピンテールの定番として名高いのが「アルカリ」です。
先ほど紹介したアルカリシャッドの“シャッドテールなし”バージョンとも言えるこのワームは、ナチュラルさと操作性のバランスに優れ、ドリフト・ダート・ただ巻きのすべてに対応する万能モデルとして根強い人気を誇ります。
アルカリの大きな魅力は、アングラーの操作に対するレスポンスの良さ。
軽くトゥイッチを入れると左右にキレのあるダートを見せ、流れに乗せると自然なドリフトアクション、ただ巻きすればタイトなスイミング姿勢で泳ぎ続ける。1本であらゆる演出ができる柔軟さが、釣り人にとって非常にありがたい存在です。
特に都市型河川や水路、干潟の流れのあるシャローエリアとの相性がよく、ピンテールならではの“無抵抗感”がスレた個体に口を使わせてくれます。
ドリフトで見せるシルエットは非常にナチュラルで、水中で浮遊するベイトのような錯覚を与えるのか、スローな展開で明確なバイトが得られることも多いです。
また、ダートアクションを組み合わせることでリアクションバイトも狙えるため、活性が低い魚に対してもアピールできるのがポイントです。
私は港湾部でのデイゲーム中、風で濁りが入った状況下でもアルカリを小刻みにダートさせて誘った結果、渋い中で唯一バイトを引き出せた経験があります。
カラーラインナップも豊富で、ピンクグローやクリア系、ナチュラル系などあらゆる状況に対応可能。
さらにVJヘッドとの互換性も高く、セッティングの自由度が高い点も、釣り場での戦術を広げてくれます。
結論として、アルカリは“これ1本で何でもこなせる”万能ピンテール。
初心者でも扱いやすく、上級者が使えばより繊細な演出も可能なため、あらゆるレベルのアングラーにおすすめできます。
バチ抜けやベイトが細いときの食わせはもちろん、アピール重視の使い方でも結果を出せる、まさに懐の深い1本です。
スリートラップ|プレッシャーの高い場面で輝く1本
ハイプレッシャーな状況でも口を使わせたい──そんなときに強力な武器になるのが、「スリートラップ」です。
一見シンプルなシルエットのピンテールですが、独特のマテリアルと高いバランス性能で、食わせの極みとも言える存在感を発揮してくれます。
最大の特徴は、水流やロッド操作に対する反応の良さ。
ただ巻きはもちろん、ドリフトやリフト&フォールといったさまざまなアプローチに対応し、どの動きでも「自然すぎるほど自然な波動」を生み出します。特に、スレきった港湾部やボートゲームなどでの実績が高いのも頷けます。
個人的に印象的だったのは、冬の夜、常夜灯下で明らかにシーバスがいるのに、どんなワームにも反応しなかったとき。
最終的にスリートラップを軽量ジグヘッドにセットし、ドリフト気味に流したら、明暗の境から突如として激しいバイトが出たんです。まるで見切られた他のワームとは“違う何か”があるような、そんな不思議なワームです。
サイズ展開も絶妙で、小さすぎず大きすぎない絶妙なボディサイズが、偏食気味なシーバスの“警戒心の境界線”を越えてくれる印象です。水中での存在感が自然で、違和感を与えずに食わせまで持ち込める稀有なモデルだと思います。
また、素材自体がややソフトなので、吸い込みが非常に良く、フッキング率も高いのが特徴です。アタリがあっても掛けきれない…という悩みを持つ方には、ぜひ一度試してみてほしい一本です。
結論として、スリートラップは「他のワームで釣れないときの切り札」。
メインで使うよりも、“ここぞ”という場面で投入して結果を出してくれるタイプのワームです。引き出しを一つ増やす意味でも、タックルボックスに忍ばせておく価値があるルアーです。
ビーチウォーカー ハウル|本来はヒラメ用、でもシーバスにも効く!
ハウルシリーズは、DUO(デュオ)から発売されているサーフのヒラメゲーム向けに開発されたジグヘッドとワームがセットになった完成型ルアーですが、実はシーバスアングラーの間でも“隠れた実力派”として注目されています。
飛距離・泳ぎ・レンジキープ性能のバランスが非常に優れており、シーバスにも効果抜群です。
このルアーの強みは、何と言っても安定した遠投性能。重心が前方にある設計で、空気抵抗が少なく、軽い力でもスーッと飛んでいく感覚があります。
サーフや広い河口、外洋系ポイントで“もう少し先を攻めたい”という場面に強いのは大きな武器です。
また、ハウルワーム特有のタイトなピッチの泳ぎが、流れの中でも崩れずに自然なアクションを維持してくれます。
私の経験では、ヒラメ狙いで投入した際に明らかに上層を意識していたシーバスが連続でヒットしたことがあり、「これはシーバスにも効くな」と確信したモデルです。
特におすすめしたいのは、潮目や払い出しの先にいるシーバスを狙うような場面。軽量ジグヘッド+シャッドテールの組み合わせでは届かないエリアでも、ハウルならしっかり飛んで、かつキレイに泳ぎます。
着底からのリフト&フォールも得意なので、低活性の底ベッタリの個体にもアプローチ可能です。
もちろん本来はヒラメ用設計なのでフックも太軸で強度があり、かつ根掛かりしづらい設計。安心して強引なファイトができるのも、シーバス狙いでは嬉しいポイントです。
また、ヘッドとワームのカスタム性も高く、好みのカラーリングで自分なりの組み合わせを作るのも楽しい要素です。
結論として、ハウルは「遠投できて、しっかり泳いで、底も取れる」三拍子揃った万能型完成ルアー。シーバス専用ではないからこそ、ライバルと差をつけられる一本とも言える存在です。
▼さらに詳しく知りたい方はコチラからどうぞ▼

ガルプ!ベビーサーディン|もはや餌。圧倒的集魚力の“匂い系”ワーム
「とにかく1本釣りたい」「絶対にボウズを避けたい」というときに強烈な効果を発揮するのが、バークレイの「ガルプ!ベビーサーディン」です。
このワームは、従来のワームとは一線を画す強烈なニオイ(フォーミュラ)を含ませた“匂い系ワーム”で、視覚だけでなく嗅覚でも魚を引きつけるというアプローチが可能です。
シーバスだけでなくどんな魚種にも有効で、ワームを水面に垂らしたまま竿を放置していた所シーバスがヒットした事があります。もはや餌ですよこれ。
最大の特徴は、圧倒的な集魚力。
特に港湾部や運河、水路など、回遊性が低くてスレやすいフィールドでは、匂いの力がモノを言います。
ピンテール型の微波動+ニオイの拡散によって、活性の低い魚にもスイッチを入れやすく、食い渋り対策としての信頼度はトップクラスです。
中でも顕著なのが、セイゴ〜フッコクラス(20〜50cm)の個体への爆発的効果。
ワームでは反応しなかった群れにベビーサーディンを投入した途端、立て続けにヒット…という場面は一度や二度ではありません。
私自身、真冬の夜釣りで「今日は厳しいかな…」と思っていた時に、ベビーサーディンだけで10本以上のセイゴを引き出した経験があります。
また、小型ゆえに小さな吸い込みでもしっかりフッキングできるのもメリット。
ショートバイトが多発する状況や、スローな展開でも安心して使えるのは初心者にとって心強いポイントです。
ただし、素材が柔らかくて消耗が早いため、予備を多めに持っておくのがおすすめです。
使い方は至って簡単。
軽量ジグヘッド(1.5〜3g)にセットして、ただ巻きかドリフトが基本。ストップ&ゴーでも効果があり、まるで本物のベイトが漂っているような錯覚を与えてくれます。
カラーはホワイト、チャート、クリア系など定番を揃えておけばOK。匂い成分は釣行中にも補充可能な液体タイプも別売されており、「ニオイで釣る」という戦略を最大限に活かすことができます。
結論として、ガルプ!ベビーサーディンは通常のワームで反応しない状況を打破できる“奥の手”。
セイゴ〜中型シーバス狙いでは圧倒的な安定感を誇り、初心者の“初めての1匹”にも強くおすすめできる1本です。
▼さらに詳しく知りたい方はコチラからどうぞ▼

ガルプ!サンドワーム|バチ抜けシーバス攻略の最強ルアー
ベビーサーディンと同じくガルプ!シリーズのワームの中でも、バチ抜けシーバス狙いで高い実績を誇るのがサンドワームです。
ガルプシリーズ最大の特徴である強烈な匂いによる集魚力に加えて、サンドワームはバチのような細長いシルエットをしており、バチ抜けパターンの最強ルアー候補です。
こちらも小型のワームなので基本的な使い方は、メバリングで使用するような小型のジグヘッドと組み合わせるスタイル。
軽量ジグヘッドと組み合わせることで、ナチュラルに漂わせる釣りが可能になります。
バチパターンの際は、表層を流れに乗せて漂わせるような釣り方が効果的です。
派手なアクションは不要で、ただ流すだけでもシーバスが口を使ってくれます。
一方で、バチ抜け以外のシーバスが沈んでいる状況では、ボトム付近をネチネチと探るだけで、スレたシーバスも簡単に反応が出ます。
匂いの効果でバイトが深くなりやすく、ショートバイトが少ないのも特徴です。
「どうしても食わせたい」「活性が低くて口を使わない」そんな場面で、最後に投入したい切り札的ワームです。
シーバスをワームで釣れないときの見直しポイント|よくある失敗とオススメ改善策

「おすすめのワームを使っているのに釣れない…」「バイトがないどころか、アタリすら感じない…」そんなとき、原因はワームそのものではなく、“使い方”や“状況の把握不足”にあることが多いです。
ここでは、釣れない原因としてありがちな落とし穴を4つ取り上げ、それぞれの改善策とともに詳しく解説していきます。
レンジがズレてないか?ジグヘッドを調整しよう
シーバス釣りで「反応がない」と感じたとき、真っ先に見直してほしいのが“レンジ(泳層)”のズレです。 ワームが水面下を泳いでいるのか、中層なのか、それともボトムを這っているのか──その位置がシーバスのいる層と合っていなければ、どんなに釣れるワームでも魚には届きません。
特に初心者にありがちなのが、「とりあえず3gのジグヘッドをつけて巻く」だけのスタイル。たしかに万能ではありますが、水深や流れの強さによっては、ワームが意図しない位置を泳いでしまうことも多々あります。
私もかつて、3時間まったくアタリがなかったポイントで、ジグヘッドの重さを5gから10gに変更しただけで連発に転じた経験があります。理由は明白で、シーバスが底ベッタリに張り付いていたのに、軽すぎてレンジが合っていなかったからです。
レンジの調整には主にジグヘッドの重さを変えるのが基本です。
例えば:
・表層〜中層狙い:5〜7g前後
・中層〜やや下:7〜15g
・ボトム攻略:15〜25g
というのがひとつの目安です。
また沈下スピードやラインの太さ、風の有無も影響するため、「実際に沈むまでのカウントダウン」をとる癖をつけると感覚がつかみやすくなります。
特にナイトゲームでは水中が見えないため、カウントダウンでレンジを意識することがバイトの鍵になります。一定の層を通したときにアタリが出れば、そこを重点的に攻める──これだけで釣果は大きく変わります。
結論として、釣れないときは「ワームが悪い」と決めつける前に、まずレンジを疑い、ジグヘッドの重さを変えること。わずかな調整が、沈黙の時間を一変させてくれることがあります。
カラーやサイズの選択に問題がないか
ワームの見た目は“釣り人の好み”で選びがちですが、シーバスの視点に立ったカラーやサイズ選びができていないと、釣果につながりにくくなります。実は「色と大きさのミスマッチ」が、バイトを遠ざけている大きな原因の一つなんです。
まずカラー選びについて。基本ルールは「水質と光量に合わせる」ことです。
・澄んだ水×日中=ナチュラル系(クリア、イワシ、グリーンなど)
・濁り×ローライト=アピール系(チャート、白、黒、ピンクなど) というのが鉄則。
明るい色は光を拾いやすく、暗い色はシルエットがくっきり出るため、状況によって使い分ける必要があります。
私の体験でも、澄潮のデイゲームでチャートカラーを投げてもまったく反応がなかったのに、グリーンに変えたとたんに一発でヒットしたというケースがありました。
「目立てば釣れる」ではなく、「自然に馴染むか」が重要なのです。
次にサイズ選びですが、これも非常に重要です。
ベイトが小さいときに4インチ以上のワームを投げても、見切られる可能性が高くなります。特に春先や夏の初期はハク(ボラの稚魚)やアミがベイトになることが多く、2.5〜3インチ程度の小さめサイズがマッチします。
逆に、秋の落ちアユやコノシロパターンのように、10cm以上のベイトが入ってくる場面では、3.5〜4.5インチの大型ワームでもしっかりとバイトが出ます。「小さいから釣れる」「大きいから目立つ」と単純に考えず、今いるベイトに合わせてチューニングしていくことが大切です。
釣り場でベイトのサイズ感がわからないときは、ボイルしている魚の動き方や跳ねの高さ、水面に浮いているベイトの群れなどを観察して判断しましょう。何も見えないときは、とりあえず3インチを基準に、前後1インチのワームをローテーションするのが無難です。
結論として、釣れないときはカラーとサイズを固定せず、柔軟に調整していく意識が必要です。
釣果を上げている人ほど、ワームの“外見”を頻繁に変えています。「ワームは正しいのに釣れない」と感じたら、まずは色とサイズの見直しから始めてみてください。
アクションの付け方が不自然になっていないか
シーバスにワームを見切られる原因のひとつが、「不自然すぎる動き」です。せっかく正しいレンジに通していても、アクションの付け方が雑だったり、違和感のある動きをしてしまうと、スレたシーバスは一瞬で見切ってしまいます。
特にピンテール系のワームは、もともと波動が少なくナチュラルな動きを得意とするため、過度なロッド操作やスピードの速すぎるリトリーブは逆効果になることがあります。
「釣れる動き」と「騒がしい動き」は違うという意識が重要です。
私の実体験でも、釣りを始めたばかりの頃は「動かせば釣れる」と信じて、トゥイッチやリフト&フォールを頻繁に入れていました。しかし、思うような釣果が出ず、試しに“ただ巻き”で流れに乗せるだけの操作に変えたところ、急にバイトが連発。そこから「動かしすぎは逆効果」だと学びました。
シーバスは特に“流れの変化”に敏感な魚です。
ドリフトやヨレに乗せたスローリトリーブなど、“自然にそこに漂っていたような動き”が一番効果的なことも多々あります。つまり、無理に動かすよりも“何もしない”ほうがよく釣れることがあるのです。
もちろん、活性が高い状況ではリアクションバイトを狙ってロッド操作を入れるのも有効ですが、やりすぎると逆にシーバスに違和感を与えることがあります。特に冬や早春などの低水温期にはスローでナチュラルな動きが基本です。
おすすめは、基本はただ巻きで探り、反応がなければ軽くトゥイッチやステイを混ぜるというスタイル。
最初から複雑なアクションを入れるのではなく、段階的に変化を加えていくほうが、スレた魚には効果的です。
結論として、アクションが効かないときは「もっと動かす」ではなく、「もっと自然にする」という逆のアプローチを心がけてみてください。シーバスは本能で“変なもの”を見抜きます。ワームを「生き物のように」動かす意識が、釣果の差につながります。
場所やタイミングが合っていない場合の対策
ワームも選んだ、レンジも合っている、アクションも意識している──それでも釣れないとしたら、「そもそも魚がいない時間・場所にいる」可能性が高いです。どれだけ完璧なルアー操作をしていても、フィールドにシーバスが回遊していなければ当然バイトは出ません。
シーバスは時間帯と潮の動きに強く影響される魚です。特に釣れやすいのは「マズメ時」(朝・夕の薄暗い時間帯)と「潮が動くタイミング(上げ潮・下げ潮の流れ始め)」です。逆に、潮止まりや日中のピーカン無風時はかなり厳しいことも多いです。
私自身、何度も「この場所は釣れない」と思い込んでいたポイントで、時間を変えただけで爆釣した経験があります。
夜の干潮どまりではノーバイトだった場所が、翌日の夕方の上げ潮に変わった瞬間、30分で3本というような展開になったことも。
つまり、「釣れない=ワームのせい」ではなく、時間と潮の問題だったというケースが非常に多いのです。
また、場所選びも大切です。常夜灯の下・橋脚周り・流れの変化点・ベイトが溜まりやすいワンドや障害物周辺など、魚が身を潜めたりベイトを待ち構えるスポットを重点的に狙うことが、釣果を出すための大前提になります。
おすすめは、「1つの場所で粘りすぎず、30分〜1時間で見切って移動する」という判断力を持つこと。特に潮が止まったタイミングでは大きくポイントを変える、もしくは潔く休憩を取って潮が動き始めるタイミングを待つという選択も有効です。
釣れない原因を“自分の腕”や“ルアーの性能”に求めがちですが、シーバスは移動性の高い魚。どれだけいいタックルやルアーを使っても、魚がいなければ釣れません。
だからこそ、「今日はどこに魚がいるのか」「今はチャンスタイムなのか」を判断する“釣り場に対する観察力”が何よりも重要になります。
結論として、釣れないときは場所と時間の“そもそも”を疑うことが大切です。潮位、ベイト、明暗、地形…そうした複数のヒントを手掛かりに、的確なタイミングと場所を見極めていくことが、シーバス釣りの真の奥深さなのです。
まとめ|シーバスワームを使いこなして釣果アップを狙おう

この記事では、シーバス釣りにおけるワームの選び方・おすすめモデル・釣れない時の対処法まで、実戦ベースで解説してきました。最後に改めて、ポイントを整理しつつ、これから実践していくうえで大切にしてほしい考え方をお伝えします。
まず大前提として、シーバスはナチュラルな動き・レンジコントロール・アプローチの柔軟さに非常に敏感なターゲットです。 だからこそ、ワームの特性を理解し、それを状況に応じて使い分けることが、釣果アップの鍵を握ります。
今回紹介した「ミドルアッパー」や「R32」「デスアダー」などは、いずれも状況別に“効く理由”が明確なモデルです。反応がないときは、それまで使っていたワームが悪いのではなく、「その時の魚の状態に合っていなかった」だけという場合がほとんど。そのズレを“合わせにいく意識”が非常に大切です。
また、「VJシリーズ」「ハウル」「ガルプベビーサーディン」などは、初心者でも使いやすく、なおかつ“あと1本がほしいとき”や“反応が薄いときの保険”として活躍するモデルです。 状況に応じてメインとサブを切り替えるという引き出しの多さも、シーバス釣りでは大きな武器になります。
釣れないと感じたときには、ワーム自体だけでなく、レンジ・カラー・サイズ・アクション・場所・時間帯といった複数の要素を一つずつ見直していきましょう。 その一つひとつの選択が正解に近づいたとき、シーバスはきっと応えてくれるはずです。
結論として、「どのワームを使うか」ではなく、「どう使いこなすか」が大切です。この記事を参考に、ぜひ自分なりのスタイルを築きながら、1本1本の価値ある釣果を積み上げていってください。
そして最後にひとつ。
釣れるワームに“正解”はありません。その日、その瞬間、その場所に合った一手を見つけ出すこと──それが、シーバス釣りの一番の楽しさであり、最大の奥深さです。