ルアー釣りする人には同じみの「シーバス」
料亭や寿司屋では「スズキ」として提供されている事がよくありますが
釣り人目線だと「シーバスって釣ったはいいけど、食べても大丈夫?」「まずいって聞いたことあるけど、実際どうなの?」そんな疑問を抱いたことはありませんか?
私自身、これまでに500匹以上のシーバスを釣ってきました。
基本はリリースが前提ですが、傷つけてしまった個体や、初めて釣ったときなどは責任を持って食べるようにしています。
実際に自分で調理して食べてみると、スーパーでは味わえないような“釣り人だけの特別な味わい”に出会えることも。
この記事では、「シーバスは本当にまずいのか?」という評価の真相から、刺身で食べるときの注意点、生息地によるリスク(河口やドブ川)、安全に美味しく食べる調理法まで、実体験をもとに詳しく解説していきます。
ちなみに、同じスズキ属でも「ヒラスズキ」は刺身でも絶品な魚として知られています。
ヒラスズキに関しても、私が実際に年間100匹以上釣って実食してきた経験をもとに
味・寄生虫リスク・おすすめレシピなどをまとめた別記事も公開しています。
▶ ヒラスズキの味について徹底解説!寄生虫やマルスズキとの違いも紹介
この記事を読めば、シーバスを安全に、そして美味しく楽しむための知識が手に入ります。
ぜひ最後までご覧ください!
シーバスは食べられるのか?|釣り人目線でのリアル評価

シーバス(スズキ)は「釣って楽しい魚」として有名ですが、「食べる」となると評価が大きく分かれます。実際に私の釣り人仲間の間でも「シーバスはまずい」という声があれば、「意外と美味しい」という評価もあります。
この記事では、私が500匹以上釣って食べてきた経験をもとに、リアルな味の評価や注意点を解説します。
シーバスが「まずい」と言われる理由とは?
シーバスが「まずい」と言われる最大の理由は環境による個体差です。
特に河口や港湾部、ドブ川のような水質の悪い場所で釣れた個体は、どうしても臭みが強く出がちです。
身に泥臭さや生臭さが残るのは、水質に影響されているためです。
また、綺麗な場所で釣ってもそれが居付きの個体ではなく回遊の個体だった場合、ドブ川で育って遡上してきている可能性もあるので、
また、魚体のコンディションも影響します。痩せた個体や、真夏の高水温期に釣れたシーバスは、身に弾力がなく水っぽくなりがちです。このような個体は、どんな料理にしても味がぼやけてしまい、「まずい」と感じる原因になります。
私自身も過去に港湾で釣れたシーバスを刺身にしたところ、臭みが強くて食べきれなかった経験があります。調理前に臭いを確認したり、加熱調理に切り替えるのが無難です。
それでも「美味しい」と感じるシーンもある!
シーバスが「まずい」と言われる一方で、「美味しかった!」という声も確かにあります。
特に、海がきれいな外洋やサーフで釣れた個体は、食味が良くなる傾向にあります。
私も実際に、サーフで釣れた60cmオーバーのシーバスを塩焼きにして食べたときは、身のふわっとした食感と脂のノリが非常に良く、家族にも好評でした。
ただし、見た目や釣れた場所だけで安心するのはNGです。一見きれいな海で釣れたように見えても、実は上流のドブ川や汽水域から移動してきた可能性があるため、魚体のにおいやぬめり、体色のくすみなどをチェックすることが非常に重要です。
また、活かして持ち帰る・釣ってすぐに血抜き&内臓処理するといった工夫をするだけでも、食味はかなり改善されます。
シーバスは刺身で食べられる?安全に食べる為のポイント

シーバスを刺身で楽しみたい釣り人は多いと思います。
実際、身は白くて上品な味わいがあり、時期や個体によっては脂がのって非常に美味しいのも事実です。
ただし、生食にはそれなりのリスクも伴うため、安全に美味しく味わうためのポイントを押さえておく必要があります。
ここでは、私自身がこれまで100匹以上釣って刺身で食べてきた実体験をもとに、安全性や捌き方のコツを詳しく解説します。
刺身に適した鮮度と下処理のコツ
シーバスを刺身で食べるなら、第一条件は「抜群の鮮度」であることです。
釣った直後から適切な処理を行わなければ、生臭さや雑味が目立ってしまいます。
私が行っている基本処理は以下の3つです。
- ・釣れた直後に神経締め+血抜き
- ・内臓とエラをすぐに除去
- ・海水+氷で冷やして保冷(氷水はNG)
この処理を徹底するだけで、臭みの出方が大きく変わります。
また捌く際には、「皮引き・血合いの除去・筋切り」を丁寧に行いましょう。
皮下にある血合いや膜は生臭さの原因になりやすいため、思い切ってそぎ落とすのがポイントです。
おすすめは、釣ってから8〜24時間ほど寝かせて熟成させる方法。
活き締め後に冷蔵庫でラップ保存すれば、適度に旨味が増し、より美味しく仕上がります。
寄生虫の心配は?釣り人が気をつけるべき点
シーバスは海水魚でありながら、汽水域や淡水域にもよく入る魚です。
そのため、寄生虫リスクはゼロではないというのが実際のところ。
特にアニサキスや線虫の類が、ごくまれに内臓や身の中に見つかることがあります。
私自身はこれまで何匹もシーバスを刺身で食べていますが、アニサキスに出会ったのは一度だけ。
とはいえ、確率の問題ではなく、「見落とすかどうか」が安全性を左右します。
見落としを防ぐために私が意識しているポイントは以下の通りです。
- ・内臓を速やかに処理(寄生虫は内臓に集中)
- ・身を透かして白い糸状の異物がないかチェック
- ・刺身にする場合は5mm以下に薄く切る
また、70℃以上の加熱や−20℃以下での48時間冷凍で無害化できるため、不安がある場合はこれらの処理を行うと安心です。
「釣ったその場で刺身」はとても魅力的ですが、安全を優先し、ひと手間を惜しまないのが大切です。
私が実際に刺身で食べた体験談と感想
私はこれまで100匹以上のシーバスを釣ってきましたが、そのうち刺身で食べたのは10匹ほど。
特に秋から冬にかけて釣れたシーバスは脂が乗っていて、ほんのりとした甘味が感じられます。
見た目もきれいな白身で、熟成させることで旨味もアップし、ブリやタイに近い味わいになると感じています。
一方で、夏場や河川の上流寄りで釣れた個体は、やや水っぽかったり、独特の匂いが気になることもありました。
そういった場合には、生食よりも火を通す調理法にした方が無難です。
初めてシーバスを刺身にする方は、匂いをチェックしてから判断することをおすすめします。
安全な処理を徹底したうえで、身の色や弾力がしっかりしていれば、きっと驚くほど美味しいシーバス刺身が楽しめるはずです。
河口・ドブ川のシーバスは食べられる?場所別の食べるリスク解説

シーバスは汽水域を好む魚で、河口や都市部のドブ川などでもよく釣れます。
ただし「食べられるか?」という観点では、その釣れた場所によって安全性に大きな違いが出ることも事実。
私自身も、綺麗な海で釣った個体とドブ川の個体を食べ比べて、はっきりと味やにおいの違いを感じた経験があります。
ここでは、場所による味の傾向やリスク、そして見た目で判断するコツを紹介していきます。
河口のシーバスは美味?臭みや安全性を解説
河口で釣れるシーバスは、海水と淡水が混ざる汽水域にいることが多く、エサが豊富で比較的コンディションの良い個体が多いです。
実際、私が食べた河口域のシーバスは脂のノリも悪くなく、ほどよく締まった身質で、刺身でも十分美味しく感じました。
ただし、河口といっても周囲の環境によってリスクは変わります。
工場排水が流れ込んでいたり、生活排水が影響しているエリアでは、臭みが強く、身の色もくすんでいることがあります。
また、水質が濁っている場所では体表にヌメリが多く、匂いが手に残るような個体もいます。
そのような場合は無理に刺身にはせず、加熱調理を選んだ方が安全かつ美味しく食べられます。
私が基準にしているのは、「見た目の艶・エラの色・体表の匂い」。
この3点をしっかり確認すれば、かなりの確率で良し悪しを見極められます。
ドブ川や汚染エリアのリスクと避けるべき理由
ドブ川や都市部の排水路が絡むポイントで釣れるシーバスは、食べるのは避けた方が無難です。
というのも、そういったエリアでは水質が悪く、ヘドロや有機汚染物質を取り込んだ魚体が多いからです。
私が過去に食べてみたドブ川のシーバスは、皮を引いた時点で独特の臭みが強く、加熱してもその匂いが残るほどでした。
身も水っぽく、味に締まりがない印象。
釣ってすぐは見た目が綺麗でも、汚染エリアから回遊してきた可能性があるという点を忘れてはいけません。
特に夏場や長雨の後は、生活排水や工場排水の濃度が高まりやすく、そうした水を取り込んだ魚は当然体内にも影響が出ます。
「釣れた場所=その魚の履歴」ではないため、より慎重な判断が必要です。
釣った場所を見極める3つのチェックポイント
綺麗な場所で釣れたからといって、必ずしも「綺麗な個体」とは限りません。
シーバスは遊泳力が高く、汚れた場所と綺麗な場所を行き来していることもよくあります。
そのため、私は以下の3つをチェックしてから食べるかを判断しています。
- ①エラの色:新鮮であれば鮮やかな赤色。くすんでいる場合は要注意。
- ②体表のぬめり:ドブ川の個体は独特のぬめりや臭いが強い。
- ③内臓の状態:内臓が黒ずんでいたり、脂が黄色い場合は避けた方が良い。
また、実際に締めた時に出る血の色も一つの判断基準になります。
鮮やかな赤色なら健康な個体である可能性が高く、逆に黒ずんでいたり濁っていると、体調や環境が悪い個体かもしれません。
見た目・匂い・処理後の状態を総合的に判断することが、安全にシーバスを食べる上で最も重要です。
シーバスのおすすめ料理レシピ|いつも食べるレシピ紹介

刺身で楽しんだあとは、加熱調理やアレンジレシピでさらに美味しく楽しめるのがシーバスの魅力です。
私はこれまで100匹以上のシーバスを釣ってきましたが、傷ついてしまった個体などは持ち帰ってさまざまな料理に活用してきました。
ここでは、家庭でも手軽に再現できるおすすめ調理法を紹介します。
一手間加えるだけで、釣った魚が「食卓の主役」に変わる感覚をぜひ味わってみてください。
歯ごたえが楽しい「あらい」で清涼感を楽しむ
シーバスを氷水で締めて食べる「あらい」は、夏にぴったりの清涼感ある食べ方です。
三枚おろしにしたシーバスの身を薄めに切り、氷水で10秒ほどしめることで、キュッと身が引き締まり、刺身とは違った歯ごたえとさっぱりとした味わいが楽しめます。
【基本のあらいの手順】
① 三枚おろしにしたシーバスの皮を引き、刺身よりやや薄めにスライスします。
② 氷をたっぷり入れた冷水に身をくぐらせ、10〜20秒ほど優しく泳がせるように冷やします。
③ ざるなどにあげてキッチンペーパーで水気を拭き取れば完成。
④ 薬味とともに盛り付け、ポン酢や梅肉ソースなどのさっぱり系のタレでどうぞ。
ミョウガ・大葉・ネギなどの薬味を添えると、より涼やかな味わいが引き立ちます。
さらに、氷水に通す事で臭さを消す効果もあります。
私の場合、釣りから帰ってきて疲れている日でも、この調理法なら短時間で仕上げられるので重宝しています。
冷たい食感と独特の歯ごたえは、ビールや日本酒との相性も抜群です。シンプルながらも、釣り人ならではの贅沢な一皿といえるでしょう。
おしゃれに楽しむ「ハーブフライ」|見た目も美味しさもUP
シンプルなフライももちろん美味しいのですが、ひと手間加えて「ハーブフライ」にすると、グッとレストラン風になります。
シーバスの切り身に塩・コショウと一緒に乾燥バジルやタイムを軽くまぶし、パン粉に粉チーズを混ぜて衣にするだけで香り高い仕上がりに。
見た目もおしゃれになるので、家族や友人に出しても喜ばれます。
私はいつも、仕上げにレモンを添えて白ワインと一緒に楽しんでいます。魚のクセも感じず、子どもにも好評です。
油の温度は170〜180℃が目安で、あまり揚げすぎないようにすると身がふっくら仕上がります。表面はサクッと、中はジューシーに。
旨味の宝庫「アクアパッツァ」|釣り魚とは思えない一皿に
釣り魚をイタリアンに変身させるアクアパッツァは、見た目も華やかでパーティー料理にもぴったりです。
三枚におろしたシーバスの切り身を塩で下味し、オリーブオイルでニンニクを炒めたフライパンに投入。
あさりやミニトマト、オリーブとともに白ワインを加えて蒸し煮にするだけで、旨味たっぷりのスープが広がります。
仕上げにイタリアンパセリを散らせば完成。
「これ本当に自分で釣った魚なの?」というくらい、プロっぽい一皿に仕上がります。パンを添えてスープごと楽しめるのもポイントです。
シーバスの白身はクセがないので、どんな具材とも相性がよく、特に出汁の効いた料理では真価を発揮します。
まとめ|釣ったシーバスは食べても美味しい!正しい処理と見極めが大切

シーバスは「まずい」と言われることもありますが、実際には処理の仕方や釣った場所によって大きく味が変わる魚です。
私自身、これまでに100匹以上のシーバスを釣って食べてきましたが、新鮮で適切に処理されたシーバスは刺身でも絶品。加熱調理でも多彩なレシピで楽しめる、魅力あるターゲットです。
ただし、ドブ川や汚染水域の個体にはリスクがあるため、安全に楽しむには「釣り場の見極め」「丁寧な下処理」「保存方法の工夫」が重要です。
「せっかく釣ったなら美味しく食べたい」という釣り人の方は、ぜひ今回紹介した方法を参考に、安全かつ美味しくシーバス料理を楽しんでみてください。

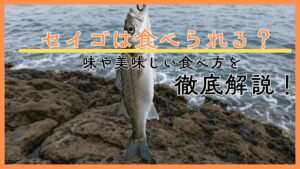

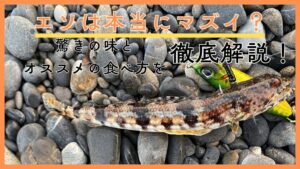


コメント