「ヒラスズキの刺身ってまずいって聞いたけど、本当?」「マルスズキとは違うの?」「寄生虫とか大丈夫?」——そんな疑問を持った方に向けて、今回はヒラスズキの刺身にまつわる“本当のところ”を、釣って食べてきた経験をもとに詳しく解説します。
私は、最近サーフでヒラスズキを狙う“砂ヒラ”にハマっており、昨年は年間で100匹近くを釣って、基本すべてを自宅で調理・実食してきました。
結論から言えば、ヒラスズキの刺身は「まずいどころか、むしろマルスズキより旨い」と感じています。
もちろん、まずいと言われる理由もゼロではありませんし、調理方法や保存状態によって味が変わるのも事実。
寄生虫や下処理の注意点も含め、美味しく安全に食べるためのポイントや、おすすめのレシピまで余すことなくご紹介していきます。
ヒラスズキの刺身はまずい?|味や食感のリアル評価

ヒラスズキの刺身と聞いて、あなたはどんな味を想像しますか?「まずい」という声もネットでは散見されますが、実際に釣って食べた人の多くが「うまい」と答える魚でもあります。この記事では、ヒラスズキの刺身の味や食感をリアルな実体験に基づいて解説しながら、誤解されがちな「まずい」という評価についても掘り下げていきます。
ヒラスズキの刺身の特徴とは?
ヒラスズキの刺身は、白身魚の中でも特に身が締まっており、上品な旨みが特徴です。透明感のある美しい身質で、歯ごたえがしっかりしていながらも滑らかな舌触りがあり、刺身好きにはたまらない食感です。
この魚は、荒磯やサーフといった潮通しのよいフィールドに生息しているため、引き締まった身をしています。脂のノリは控えめですが、旨味が凝縮されており、熟成させることでさらにその深みを楽しむことができます。
「まずい」と言われる理由と実際の評価
ヒラスズキの刺身が「まずい」と言われることがあるのは、その食味に好みが分かれるためです。
脂の少なさや、締まった身質が「パサついている」と感じられる場合もあり、サーモンやブリのような脂系の魚が好きな人には物足りなさを感じさせるかもしれません。
しかし、筆者は昨年だけで砂ヒラ(サーフで釣れるヒラスズキ)を100匹近く釣り、ほぼすべてを自ら調理して味わってきましたが、結論としてヒラスズキの刺身は非常に美味しい魚だと感じています。
特に、釣ってすぐの活け締め後に血抜き
し、数日寝かせてから刺身にすると、弾力のある歯ごたえと淡い旨味が際立ちます。
また、マルスズキと比べて臭みが少なく、身の繊維が細かく整っている印象があります。
「まずい」という声の多くは、血抜きや締め処理が不十分な個体や、適切な熟成がされていないケースに多いと考えられます。
マルスズキとの刺身の違い|味・食感・見た目で比較

ヒラスズキを刺身で食べたことがある人なら、一度は「マルスズキとどう違うのか?」と気になったことがあるはずです。
見た目は似ていても、実際に食べ比べてみるとその違いは想像以上に大きいと感じます。
ここでは、ヒラスズキとマルスズキの生態的な違いや、それが刺身の味・食感・見た目にどう影響するかを詳しく解説していきます。
ヒラスズキとマルスズキの生態の違い
ヒラスズキとマルスズキは、どちらも見た目は非常によく似ているため、釣り初心者の方は区別がつきにくいかもしれません。
しかし、実はその生息環境や生活習性が大きく異なっており、それが肉質や味にも直結しています。
「ヒラスズキ」は、基本的に外洋に面した磯やサーフ波打ち際といった波や流れの強い場所に生息しています。
荒波を受けながら遊泳するため、筋肉が発達しており、身は引き締まり弾力のある質感になりやすい傾向があります。
また、潮通しの良いエリアで生きていることで、体内に余計な脂が付きにくく、脂肪分が控えめで、透明感のある白身をしています。
「マルスズキ」は内湾や河口、汽水域、港湾部などの比較的穏やかな水域を好んで生息します。荒波に揉まれることが少ないため、筋肉の発達は緩やかで、やや柔らかくフワッとした身質になる傾向があります。
また、生活環境の影響からやや脂乗りが良く、血合い部分が多いことも特徴です。
こうした生態の違いは、魚体の形状や色味にも現れますが、それ以上に刺身として口にしたときの食感や味わいに大きな影響を及ぼしています。
マルスズキとの刺身での味・食感の違いはここに出る!
刺身で実際にヒラスズキとマルスズキを食べ比べてみると、その差は想像以上に明確です。食べた瞬間の歯ごたえや旨味の出方、そして脂の乗り具合まで、同じスズキ属とは思えないほどの違いを感じることができます。
「ヒラスズキ」の刺身は、身がしっかりと引き締まっており、コリッとした食感が非常に心地よいです。
噛むたびに旨味がじわっと広がり、淡白ながらも奥深い味わいを楽しめます。
釣ってすぐよりも、1〜2日寝かせて熟成させた方がより旨味が際立ち、より高級魚らしい味わいになります。
白身魚らしい上品さと、荒磯育ちの力強さが共存しているのが魅力です。
「マルスズキ」は、脂がやや多く、舌に吸いつくようなねっとりした食感が特徴です。
こちらも美味ですが、どちらかといえば「もっちり系の白身」が好みの方に向いています。
味わいはやや控えめでクセも少なく、薄口の刺身醤油やポン酢でさっぱりいただくとその特徴が生きてきます。
見た目にも違いがあり、ヒラスズキは血合いが少なく、やや透明感のある純白の身をしています。マルスズキは、やや白濁し血合い部分が目立つため、盛り付け時に少し工夫が必要です。こうした細かい違いも、釣り人や料理好きの間では好みを分ける大きなポイントになっています。
ヒラスズキの刺身は寄生虫に注意?|リスクと対策

ヒラスズキの刺身は非常に美味しいものの、「生魚」となる以上、寄生虫リスクについても正しく理解しておくことが大切です。
私が昨年釣ったヒラスズキは約100匹。
そのうちアニサキスが1匹
小さな卵のような寄生虫(恐らくクドア)3回程度見られました。
この経験からも、**リスクは極めて低いものの“ゼロではない”**というのが実感です。
このセクションでは、代表的な寄生虫の特徴と、安全に刺身で食べるための対策を解説していきます。
アニサキスやその他の寄生虫の可能性は?
ヒラスズキは青物やサバ系ほどアニサキスのリスクは高くありませんが、完全に無視できるわけではありません。
特に春先や秋口など、水温変化の大きい時期には内臓や筋肉に寄生していることが稀にあります。
筆者の実体験でも、100匹中アニサキスの確認は1回のみでしたが、見つけたのは切り身にしてからのこと。
つまり、釣った直後に目視で確認できるとは限らないということです。
また、ヒラスズキで時折見られるのが**「クドア」**と呼ばれる寄生性粘液胞子虫の一種です。
これは筋肉に白い濁りが出るのが特徴で、見た目にも違和感があります。
クドア自体は人体に害がないとの声も聞きますが、一部種では食中毒の原因になる可能性も指摘されています。
私自身はクドアで当たった事ないですが、実際に釣友がクドアでお腹を壊した事があったので、リスクはやはりあります。
これらの寄生虫は、魚の種類や釣れた場所によっても発生頻度が異なるため、地域差にも注意が必要です。
特に内湾や河口域で釣れた個体は、より慎重に確認することをおすすめします。
安全に食べるための下処理と保存方法
ヒラスズキを安全に刺身で食べるためには、釣った直後の処理と保存方法が極めて重要です。
まず、釣り上げたら即座に締めて、できるだけ早く内臓を取り除くことでアニサキスの筋肉への移動を防げます。
また、食べるまでの間に冷蔵保存をする場合、できれば1〜2日熟成させる間にも5℃以下を保つことが理想です。万全を期すなら、-20℃で24時間以上冷凍するとアニサキスは死滅します(ただし、身の質感は多少落ちる可能性があります)。
クドアに関しては、加熱または冷凍によって死滅させることが可能です。
刺身で食べる場合には、カット時に身に白い小さい卵のような物がないかをチェックし、異常があればその部位は廃棄しましょう。
私も、釣ったヒラスズキは必ず目視で身の状態をチェックしてから調理しています。
きちんとした下処理と保存を行えば、安全に刺身として楽しむことが可能です。
ヒラスズキは刺身以外でも美味しい!おすすめレシピ集

ヒラスズキというと「刺身で食べる魚」という印象が強いかもしれませんが、加熱調理でもその美味しさはしっかり活きます。
むしろ、刺身よりも「旨味」が際立つ料理も多く、家族にも喜ばれるメニューに仕上がります。
実際、筆者も釣ったヒラスズキの大半は塩焼きやムニエルなどにして食べており、釣った当日に食べるなら火を入れた方が美味しいと感じることも多いです。
このセクションでは、手軽にできて失敗しないレシピと、美味しく仕上げるコツを紹介します。
アクアパッツァ|旨味が染み出すイタリアン料理
家族からの人気ナンバーワンでよくリクエストされるのがコレ。
ヒラスズキの身から出る繊細な出汁が、トマトやアサリの旨味と合わさって極上の一皿に。
材料(2人分)
- ヒラスズキ切り身:2切れ
- ミニトマト:6個
- アサリ:200g
- オリーブオイル:大さじ1
- にんにく:1片(スライス)
- 白ワイン:100ml
- 水:50ml
- 塩・胡椒:少々
- パセリ(あれば):少々
作り方
- フライパンにオリーブオイルとにんにくを入れて弱火で香りを出す。
- ヒラスズキを皮目から焼いて軽く焼き色をつける。
- ミニトマト・アサリ・白ワイン・水を加えて蓋をして5〜7分蒸し煮。
- アサリが開いたら、塩・胡椒で味を調整し、仕上げにパセリを散らして完成。
ムニエル|シンプルだからこそ引き立つ白身の甘さ
ふっくらしたヒラスズキの身にバターのコクが加わる、定番の洋風メニュー。
材料(2人分)
- ヒラスズキ切り身:2切れ
- 塩・胡椒:適量
- 薄力粉:適量
- バター:20g
- サラダ油:小さじ1
- レモン(お好みで):適量
作り方
- ヒラスズキに塩・胡椒を振り、薄力粉をまぶす。
- フライパンにバターとサラダ油を熱し、両面を中火で焼く(片面約3〜4分)。
- 焼き色がついたら器に盛り、レモンを添えて完成。
唐揚げ|外はサクッ、中はふんわり!釣り人定番の調理法
タンパクな味わいにしっかり引き締まった身は、唐揚げとの相性もバツグンです。
クドさがないのでバクバク食べられますよ。
一口大に切れば、お弁当やおつまみにも最適です。
材料(2人分)
揚げ油:適量
ヒラスズキの切り身:200g(骨・皮なし)
醤油:大さじ1
酒:大さじ1
おろし生姜・おろしにんにく:各小さじ1
片栗粉:適量
作り方
- ヒラスズキを一口大に切り、醤油・酒・おろし生姜・おろしにんにくで10分漬け込む。
- キッチンペーパーで水分を軽く拭き取り、片栗粉をまぶす。
- 170〜180℃の油で2〜3分揚げ、カラッと仕上がったら完成。
釣り人が教える!熟成&火入れのコツとは
釣り人ならではの視点で言うと、釣ってすぐより1〜2日熟成させた方が旨味がグッと増すのがヒラスズキの魅力です。
刺身ではもちろん、火を通す料理でもこの「熟成」の工程は非常に効果的。
特に背身は締まりが強くなり、しっとりとした口当たりになります。
熟成方法としては、以下のステップが基本です。
- 釣ったらすぐに血抜き・神経締めをしてクーラーボックスへ
- 家に帰ったら内臓とエラを取り除き、キッチンペーパー+ラップで包む
- 冷蔵庫(0〜3℃が理想)で1〜2日保存
火入れの際は、表面をしっかり焼いて中はふっくら残すように調理すると、ヒラスズキ特有のしっとりとした食感が生きてきます。
また、アラやカマなどは冷凍保存しておき、寒い時期に潮汁や鍋に使うと絶品。ヒラスズキは捨てる部位がほとんどなく、まさに「全身がごちそう」な魚です。
ヒラスズキの刺身まとめ|「まずい」は誤解?食べてこそわかる本当の魅力
ヒラスズキの刺身は「まずい」と思われがちですが、実際にはしっかりとした食感と上品な旨味を持つ美味な魚です。
マルスズキとの比較でも、刺身に適した締まった身質やクセの少なさが際立ちます。
また、寄生虫のリスクはゼロではないものの、適切な処理と保存を行えば安全に楽しめます。
刺身だけでなく、ムニエル・唐揚げ・アクアパッツァなど、さまざまな料理でその美味しさを発揮してくれるのも魅力です。
筆者自身、サーフで釣ったヒラスズキを年間100匹以上食べてきた経験から断言します——ヒラスズキは、知れば知るほど旨い魚です!
ヒラスズキを釣ったら、まずは「熟成」や「締め方」にこだわって、美味しさを最大限に引き出しましょう。
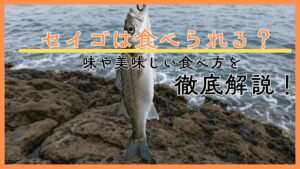


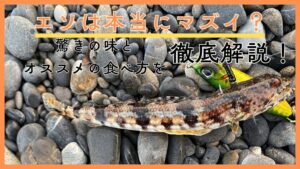


コメント